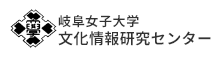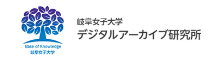【公開講座】学校DX戦略コーディネータ講座 ~ 学校DX戦略とその理論 ~
趣 旨:
学校DX戦略コーディネータは,学校や教育機関においてデジタルトランスフォーメーション(DX)戦略の計画,実施,および評価をし,効果的に推進する役割を担う専門家を育成します。
プログラム:
1.「次期教育課程と教育DX」
武藤久慶氏(文部科学省・教育課程課長)
動 画
内 容
1. 諮問の背景と現代社会の課題
次期学習指導要領の改訂が議論されている背景には、現代社会が直面する多岐にわたる課題があります。武藤課長は、中央教育審議会への諮問文の内容を踏まえ、主に以下の5つのトレンドと課題を挙げました。
1.1. 深刻な人口減少と個人のエンパワーメントの必要性
日本の人口減少は深刻な状況にあり、近い将来、少ない人口で残りの人口を支える極めて厳しい社会が想定されています。このような状況では、**一人ひとりが最大限に能力を発揮し、社会を支える存在となる「エンパワーメント」**が不可欠です。教育は、この個人のエンパワーメントを促進する上で極めて重要な役割を担います。
1.2. 加速するグローバル化と多様性への対応
外国人の増加、日本人の海外進出など、グローバル化は加速の一途をたどっています。2067年には人口の1割が外国人になるとの推計もあり、将来の子どもたちは、異なる常識、宗教、価値観を持つ人々と共に働く、あるいは地域社会を形成することが当たり前の世界で生きていくことになります。ソニーとホンダのEV提携など、企業間の協業も国境を越えて活発化しており、教育もこうした多様性と協働を前提とした社会に対応していく必要があります。
また、社会政策の側面では、ダイバーシティ&インクルージョンが重視されており、SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」が掲げられています。これは、不登校の子ども、特別支援を必要とする子ども、外国人児童生徒など、多様な特性を持つ子どもたち一人ひとりに「個別最適な教育」を提供していくという高い目標を示しています。この高い目標を達成するためには、従来の教育方法では限界があり、ギガスクール、教育データ、ICT活用、DXといった強力なツールが必要不可欠であると認識されています。
1.3. Society 5.0の実現とデジタル社会の「作り手」・「使い手」の育成
政府全体で取り組むSociety 5.0は、仮想空間と現実空間を高度に融合させ、人間中心の社会を創造することを目指しています。AIやロボティクスなどデジタル技術が社会のあらゆる領域に行き渡る中で、教育関係者は、**デジタル化社会の良き「作り手」(ハイエンドな人材)と賢い「使い手」(すべての人々)**の両方を育てる必要があります。
Chat GPTの登場に象徴されるように、AIやロボットで代替可能な仕事が減少する一方、代替不可能な仕事は増加する傾向にあります。教育は、子どもたちがこのような社会で活躍できるよう、AIが得意な領域(スピード、知識量、大量データ解析など)と人間が得意な領域(創造性、対人コミュニケーションの深い部分など)を見極め、人間の強みを伸ばす方向性を模索する必要があります。
1.4. デジタル化がもたらす負の側面への対応
デジタル化には、フィルターバブルやエコーチェンバーといった負の側面も存在します。子どもたちのスマホ所有率が上昇する中で、パーソナライズされた情報が偏って流れてくる状況を認識している人が少ないことは危険であると指摘されています。
子どもたちが不健康な情報の渦に巻き込まれないよう、教育はICTを単なる学習ツールとしてだけでなく、デジタルとの賢い付き合い方を意図的・計画的に教える必要があります。これには、情報を批判的に捉える力、デジタル社会を創造するプログラミングスキル、そしてデジタルから意識的に距離を置く選択肢も含め、包括的な情報モラルやメディアリテラシーの育成が求められます。
1.5. 加速する変化のスピードと生涯にわたる学びの必要性
技術や知識の変化は激しく、人的資本の価値が失われるスピードも加速しています。企業の寿命が短くなり、職業寿命は長くなる「人生100年時代」においては、マルチステージの人生モデルが常識となります。転職や転業が当たり前となる中で、**生涯にわたって学び続け、自らの人生を主体的に「かじ取りする力」**が極めて重要になります。この「自らの人生をかじ取りする力」を初等中等教育のうちに身につけさせることの必要性が強調されています。構造的な人材不足が予測される中で、企業や職場に働き方・生き方を決めてもらうのではなく、個人が主体的に決定する時代が到来しており、学校教育、リスキリング、生涯学習、そしてデジタルがその不可欠な一部として貢献する形が求められます。
諮問文では、少子高齢化、グローバル化、AI、そして不確実性の高まりといった時代背景のもと、人生100年時代において、子どもたちが主体的に学び続け、自らの人生をかじ取りする力を身につけることの重要性が増していると結論づけられています。
2. 現行指導要領の課題とデジタル活用の可能性
日本の教育はPISA調査で世界トップクラスの学力を示している一方で、いくつかの課題も抱えています。
2.1. 学びに向き合えない子どもの増加と多様なニーズへの対応
子どもたちの多くは、授業が「簡単すぎる」または「難しすぎる」と感じており、特に中学校では「難しすぎる」と感じる生徒が増加しています。従来の紙ベースでの一斉指導では、成績上位層と下位層の子どもたちに十分な対応ができていないという構造的な課題があります。
子どもたちの認知特性は多様であり、教室には様々な特性を持つ子どもたちが共存しています。しかし、統計的には、小中学校で学習面・行動面に困難を抱える子どもが約8.8%いるにもかかわらず、高等教育への接続率は著しく低い(大学学部学生在籍率は0.32%)という現状があります。これは、多くの子どもたちが自分なりの賢い学び方や効率的な学び方を獲得できないまま高等教育に接続できていないことを示唆しており、少子化が進む中でこの状況を放置することはできないと指摘されています。
Z世代の子どもたちは、興味のあるコンテンツに個別にアクセスし、視聴スピードすら自分で決めるなど、学習ペースに対する多様なニーズを持っています。こうした背景から、一斉指導のみに依存する従来の教育モデルは限界に近づいており、個別最適化された多様な選択肢の必要性が強調されています。不登校の子どもたちへの調査からも、「自分のペースに合った手助けがある学び」「好きなことを追求できる学び」への強いニーズが明らかになっています。
このような多様な子どものニーズに応え、誰も取り残さない教育を実現するためには、教育DXが強力なツールとなり得ます。デジタル技術を活用することで、一人ひとりの意欲を高め、可能性を開花させることができると期待されています。
2.2. 現行指導要領の浸透と「深い学び」への課題
現在の学習指導要領は「主体的・対話的で深い学び」を目指していますが、その浸透は道半ばであると認識されています。
自律的な学習能力の不足: PISA調査(2022年)では、日本の生徒は高い学力を示しながらも、「自力で勉強をこなす」「勉強の予定を立てる」「学びの進み具合を評価する」「オンライン学習リソースを活用する」といった自律的な学習能力に自信がないという結果が出ています。生涯にわたって学び続けることが求められる時代において、これは大きな懸念材料です。
知識の「記号設置」と概念理解の不足: 知識を現実と関連付けて理解する、概念を習得する、深い意味理解を促すといった点が弱い傾向にあります。例えば、数学の「関数」を単なる計算問題として捉え、未知の数字を予測できるというその本質的な意味や感動を理解していない、歴史の「鎌倉幕府」を単なる暗記で終え、なぜ元寇が御恩と奉公の関係を崩壊させ、幕府滅亡に繋がったのかという因果関係をストーリーとして理解していないといった例が挙げられています。また、「等しい」という言葉の意味を誤解している子どもの存在も指摘され、**概念が腹落ちしないまま問題演習を行う「記号設置」**の状態が課題とされています。デジタルツールは、このような概念理解を深める上で有効な可能性を秘めています。
自分の考えを表現する能力の不足: 自分の考えを述べることや議論することが苦手な子どもが多いという課題も根強く存在します。TOEFLのスピーキングテストの例を挙げ、日本の学校教育が、リスクを冒して挑戦することと無難に生きることのどちらが良いかといった**「自分の考えを持ち、その理由を説明する」訓練**が十分ではないことを指摘しています。
当事者意識の希薄さ: 政治や社会問題に対する自分の考えを持ち、議論し、社会を変えられると考える子どもの割合が低い傾向も課題です。AIの専門家である川村先生の言葉を引用し、将来、自分で何をするかを決める「意思決定の仕事」が残り、言われたことをこなす「作業」はAIに代替される時代において、「夢を突き詰めること」「自分で何がやりたいか」という主体的な動機づけが不可欠であると強調しています。
これらの課題は、全体として日本の学力レベルは高いものの、教育の「弱み」となっていると総括されています。深い意味理解や概念の習得、自律的な学習能力、そして主体的な社会参加の意識を高めるためには、デジタル活用が大前提となると武藤課長は述べています。
2.3. ギガスクール活用の現状と課題
ギガスクール構想は緒に就いたばかりであり、実体験の格差やデジタル化の負の側面を指摘する声も存在します。しかし、武藤課長は、デジタルとリアルのバランスを取り、「デジタルの力で学びを支える」という視点で次の指導要領を考えていく姿勢を示しました。
PISA調査から見るICT活用:
適度なICT活用は学力向上に寄与: PISA調査の分析によると、ICTを「全く使わない」場合よりも、「1時間から5時間程度」適度に使用する場合の方がスコアが20ポイント増加するという結果が出ています。一方で、使いすぎは学力低下に繋がる可能性も示唆されています。
日本の学習規律の高さ: デバイス使用による「注意散漫」な生徒の割合が、OECD加盟国の平均3人に1人に対し、日本はわずか5%と世界で最も低いというデータが示されました。これは、日本の教育現場がこれまで培ってきた学習規律、教室環境の整備、教師の集中させる技術、発問の工夫などが国際的に高いレベルにあったことを示唆しています。
「残すべきもの」と「リニューアルすべきもの」: 日本の教育が培ってきた優れた側面(学習規律など)の中で、新たな時代においても残すべきものは意図的に残し、時代遅れになったものはリニューアルしていくという意識的な取り組みの重要性が述べられています。
ICT活用の具体例:
日常的なICT活用: ICTが日常になった教室では、紙とデジタルを使い分けたり、両方を活用したりする場面が増えています。
多様な学びの深化:
部活動での練習録画とプロの動画との比較による改善点の話し合い。
理科の実験動画記録による検証。
ルールメイキングにおける意見の即時共有と少数意見の可視化による深い議論。
これらの事例は、デジタルツールが、これまで時間的制約などで難しかった**「質的な学びの深化」**を可能にする強力な手段であることを示しています。ルールメイキングのような「主体的に社会参加する教育」は、手間と時間がかかるため、DXなしには成り立たないと武藤課長は強調します。
諮問文では、これらの課題に取り組む上で、教師の努力と熱意に過度に依存せず、持続可能な形で学校教育を継承・発展させることを前提に、これからの時代にふさわしい指導要領を検討していくことが述べられています。
3. 教育DXがもたらす変革とカリキュラム改革
教育DXは、単なるツールの導入に留まらず、学習の保証、個別最適化、カリキュラムのあり方そのものに変革をもたらす可能性を秘めています。
3.1. 学びの保証と個別最適化の推進
デジタル技術は、学びの個別化を強力に推進します。
個別指導と学習進度の管理: 動画教材やドリルなどを活用することで、子どもたちは自分のペースで学習を進めることができ、教師は手が空くことで、すべての子ども一人ひとりの進捗を確認し、必要な指導や支援をきめ細やかに行うことが容易になります。
多様な学習方法の選択: インターネット上には様々な良質なデジタル教材が存在し、子どもたちは自分に合った学習方法を見つけることができます。熊本市の事例のように、自治体が高品質なデジタル教材を開発し、他自治体にも開放するといった動きも出ています。
「文房具」としてのICT: ICTは、教師の指導ツールであると同時に、子どもたちにとっての「学びのための文房具」であり、学習の基盤となるツールとして捉えられています。
3.2. ICT活用の「手段」と「目的」
ICTはあくまで**学習を改善するための「手段」**であり、それ自体が目的ではありません。個別最適化された学びと協働的な学びを一体的に充実させ、「主体的・対話的で深い学び」の授業改善を進めることで、資質・能力の育成に繋がるという全体像が示されています。
効果的なICT活用: 主体的な授業改善に取り組んでいる学校ほどICTを積極的に活用しており、ICTを活用することで自分のペースで学べたり、動画で学習内容が理解しやすくなったり、考えや意見を伝えやすくなると感じる子どもほど、平均正答率が高い傾向が示されています。これは、ICTが漫然と使われるのではなく、目的意識を持って「主体的・対話的で深い学び」の方向で活用されることが重要であることを示唆しています。
情報活用能力の重要性: 一方で、ICTが「手段」として機能するためには、一定期間使い続けることで操作スキルを習得し、活用できるようになる必要があります。さらに、**「情報活用能力」は、言語能力や問題発見能力と並ぶ「学習の基盤となる資質・能力」**として位置づけられています。情報技術を適切に活用して自分の考えを形成し、問題解決や対話的なコミュニケーションを促進するこの能力は、まさにそれ自体が「目的」であるとされています。情報モラル、メディアリテラシー、AIに関する知識などを含め、情報活用能力を抜本的に向上させていく必要性が強調されています。
3.3. 教員の「教えすぎ」と児童の「学びすぎ」の課題
一部で「教えない方が良い」「子どもに任せるべき」といった誤解が生じていることに対し、武藤課長は、教師の適切な介入と支援の重要性を強調します。
教師の積極的な関与: 成功している実践例では、教師がクラウド上で子どもの学習状況をモニタリングし、指導・支援を行っています。自己決定できる前提を整えるための手引きの作成や、質の高い資料の準備など、教師が周到に準備した上で子どもたちの自律的な学習を促しています。
「間違いの修正」と深い学び: 新潟県の事例では、子どもが自分の間違いを修正するプロセスで成長を実感し、その経験をポートフォリオとして蓄積・振り返ることで、自己調整能力やメタ認知能力を高めている様子が紹介されました。これは、ICTを活用することで、このような深い学びのプロセスをより効果的に実現できることを示しています。
「調べる」ことの本質: スライド作成などの学習活動において、「調べる」ことが単なる情報収集で終わってしまい、そこからの整理・分析、自分の意見の形成、新たな問いの創出に繋がっていないという課題も指摘されています。デジタル思考ツールなどは便利ですが、フォーマットに流されるだけでなく、本質的な思考を促す教師の指導が不可欠です。
「参照点」の重要性: デジタルは、子どもたちが模範となる「参照点(reference)」を容易に見つけられる強みを持っています。例えば、野球選手のプレー動画やダンスの動画を参考にし、それを模倣・改善することで、驚くほどスキルが向上する事例が挙げられています。しかし、このデジタルの強みが、プレゼンテーションや英語学習、議論の場において十分に活かされていない現状も指摘されています。
3.4. カリキュラム・オーバーロードと「中核的概念」の重視
現在の教育課程は、教科書が過去50年で大幅に厚くなるなど、**「カリキュラム・オーバーロード」**の状態にあり、これが教員の負担増大の一因となっています。
パフォーマンス課題と深い学び: 愛知県春日市の事例では、室町時代をテーマに、教師があえて構造的な板書を行わず、子どもたちに「政治」「貿易」といった視点やヒントを与え、自分で情報を整理・分析し、構造化する活動(パフォーマンス課題)を行っています。NHKなどの質の高い映像資料や付箋を活用し、共同や議論を通じて最終的に成果をまとめて発表するこの学習は、深い意味理解を促します。
入試改革との連動: 定期テストでも教科書の持ち込みを許可し、「多面的に」「根拠となる資料やデータを引用して」説明させるなど、知識の丸暗記ではなく、思考力・判断力・表現力を重視する取り組みがなされています。
「中核的概念」の重視: 今後の指導要領では、AIの発展状況を踏まえ、個別具体的な知識の集積だけでなく、**「概念の習得」「深い意味理解」「学ぶ意味や社会とのつながり」**を重視し、それらを直結するような授業改善に繋がる内容を目指すとされています。教科の「中核的な概念やアイデア」を中心に、目標や内容を分かりやすく構造化することで、カリキュラムのスリム化を図りつつ、子どもたちの学力を向上させる可能性が模索されています。例えば、歴史においては、個々の用語の暗記よりも、「なぜ室町時代と鎌倉時代は本質的に異なったのか」といった「本質的な問い」を追求することで、関連する知識が磁石のように引き寄せられ、より深い理解に繋がると考えられています。
3.5. 時間の再配分と教員の「余白」の創出
教育DXと効率化を進めることで、教員と子どもの活動時間を再配分し、教育の質を高める取り組みも行われています。
研究開発学校の事例(東京都目黒区):
小学校の標準授業時間45分を40分に短縮し、年間127時間の「余剰時間」を創出。
この時間を活用し、**「個人の興味関心に基づく探究活動」「振り返りから生まれた問いの追求」「体験活動の増加」「表現力・対話力の育成プログラム」「教員の研修や子どもとの個別対話」**など、多様な取り組みを実施しています。
この取り組みは、DXによる効率化が前提であり、教員に「余白」を生み出し、それが最終的に子どもへの教育の質向上に繋がるという好循環を生み出しています。
終わりに
次期学習指導要領は、ギガスクールや教育DXが十分に推進されることを前提として検討されます。武藤課長は、現在の指導要領とギガスクールの学校現場への徹底的な実装が、次期指導要領への最も重要な準備行為であると結びました。
(文責:久世)
2.「GIGAスクール時代に相応しい授業のために」
東原義訓氏(信州大学名誉教授・東原学び研究所)
動 画
資 料
内 容
学校DX戦略とその理論:未来を生きる子どもたちのために
未来を生きる子どもたちのために教育システムにおいて「当たり前」とされてきた概念を問い直し、学校DX戦略として3つの柱が提示されました。
1. 新たな価値を創造する対話的な学び
ギガスクール環境の最大の強みである1人1台の端末とクラウドを活用し、多様な他者との対話を通じて新たな価値創造や課題解決能力を育むことを目指します。
対話的学びの5つのレベル
東原先生は、タブレットを活用した対話的学びを以下の5つのレベルで捉え、レベル5の「新たな価値の創造」を目指すことの重要性を強調しています。
レベル1:発表
児童生徒が自分の考えをタブレットに入力し、数名が発表する。
レベル2:全員で共有
児童生徒全員がタブレットに入力した内容を共有し、お互いの考えを見る。
レベル3:質問・意見の書き込み
共有された考えに対し、質問や意見を書き込む。
レベル4:比較・分類
みんなの考えを比較・分類し、構造化する。
レベル5:新たな価値の創造
友達の考えや対話を通じて自分の考えを修正・深化させ、新たなものを創造する。これはOECDの「ラーニングコンパス」にも通じる考え方です。
授業展開のポイント
対話的な学びを促進するための授業展開のポイントは以下の3点です。
共有できる形でのアウトプット: 自分の考えをタブレット(例:スプレッドシート)に書く。
吟味する時間の確保: 友達の考えをじっくり読んで吟味する時間を十分に取る。
考えのバージョンアップ: 友達の考えを踏まえ、自分の考えをより良いものに改善・表現する時間を持つ。特にこの「改善」のプロセスが重要であると述べられています。
実践事例:国語と公民の授業
具体的な実践事例として、小学校での国語の授業と、中学校での公民の授業が紹介されました。
国語の授業(小学校):
「ごんぎつね」の物語におけるごんの気持ちの変化について、児童が各自の考えをスプレッドシートに記述。
その後、友達の考えを読み、自分の考えを修正・改善する時間を設けた結果、先生の指導なしでも児童の考えが大きく改善されることが確認されました。これは、他者の意見に触れることで、子どもたちが想定以上の学びを得られることを示しています。
公民の授業(中学校):
「路線バス廃止問題」という村の課題に対し、生徒が役場の担当者として解決策をスプレッドシートに記述。
次に、記述した内容をJamf Proなどのデジタルホワイトボードの付箋に落とし込み、色分けや矢印で関係性を示すなどして「構造化」する作業を実施。
この構造化の作業を通じて、生徒たちは新しいことに気づき、より深い学びに繋がったと報告されています。ここで重要なのは、構造化の要素が教科書や資料の概念ではなく、「友達の考え」のキーワードであるという点です。これにより、単なる知識の整理に留まらない、共同による新たな価値創造が促されます。
これらの実践から、小学2年生といった低学年でも構造化の作業が可能であり、それが深い学びに繋がることが示唆されました。新しい気づきや因果関係の理解、そして新しい考え方の創造に繋がるとして、ギガスクール時代の事業スタイルとして推奨されています。
2. 時間を基準とした教育システムからの脱却
日本の教育システムは長らく「時間を基準」としており、同じ時間の中で同じ内容・同じ方法で教育が行われてきました。しかし、このシステムが本当に適切なのかという問いに対し、東原先生は「3タウの原則」と学生の研究成果を提示し、脱却の必要性を訴えかけます。
「3タウの原則」と最新の研究結果
1970年代に筑波大学の中山和彦先生が提唱した「3タウの原則(3τの原則)」は、ある単元を習得するのにかかる時間は、最も速い子どもと最も遅い子どもで約3倍の差があるというものです。
東原先生の指導学生がギガ端末を活用して行った卒業研究では、この3タウの原則が現在の教育現場でも変わらず存在することが実証されました。
研究内容: 算数のシンプルな計算問題15問を解くのにかかった時間を計測。
結果: 最も速い児童(約150秒)と最も遅い児童(約500秒)の間には約3倍の時間の差が見られました。
重要な示唆: 最も遅い児童であっても、彼らが必要とする時間をかければ、正答率は最も速い児童とほとんど変わらないという結果が得られました。つまり、時間を基準としたテストでは「できる子」と「できない子」の差が生じるように見えますが、時間という制約を取り払えば、子どもたちの達成度には大きな差がないことを示唆しています。
これは、これまで「速い=できる子、遅い=できない子」という誤った思い込みがあったのではないかという問いを投げかけます。ペーパーテストのように時間制限がある環境では点数に差が出ますが、時間という枠を外してあげれば、子どもたちはそれぞれ必要な時間をかけて、同等の達成度に至ることができるのです。
教育実践への示唆と成果
この研究結果は、学校現場の先生方に大きな気づきをもたらし、事業のやり方に変化をもたらしました。
授業の変化: 子ども一人ひとりに必要な時間と、適した補充学習を確保する学習方法を取り入れた。
学力調査の結果: 文部科学省の学力・学習状況調査の結果を見ると、これまで見られた成績下位層が減少し、むしろ満点に近い方に偏った正規分布とは異なる(右側に偏った)グラフへと変化しました。
このことから、時間を基準とした教育システムを見直し、子ども一人ひとりに必要な時間と、適した学習の機会を与えることで、これまで想定された以上の成果を子どもたちが成し遂げられる可能性が示されました。義務教育の時間が「無駄なものにしてはいけない」貴重な時間であるという認識のもと、ギガスクール時代だからこそこの変革が可能になるという期待が述べられています。
3. 教員の自己研鑽と総合啓発のための仕組みの構築
学校DXを進める上で、教員のスキルアップや意識改革は不可欠です。東原先生は、教員の自己研鑽と相互啓発を促すための3つの仕組みについて考察しています。
ギガスクール時代にふさわしい授業イメージの共有と自己評価
授業スタイルの振り返り:
教員が自身の授業がギガスクール時代にふさわしいものになっているかを確認するための「振り返りシート」を作成。
「授業の開始」「自律的な学び」「個別最適な学び」「対話的な学び」「振り返り」という5つの観点に基づき、3段階(望ましいA、中間B、望ましくないC)で評価できるようにしています。
例えば、「授業の開始」では、端末がすぐ活用できる状況がB、子どもが自ら学習活動を開始できる状況がAと定義。
「対話的な学び」では、他者参照後に自分の考えをバージョンアップさせるまで行っていればAとしています。
自己評価とレーダーチャート:
教員がこれらの項目について自己評価を行うと、自動的にレーダーチャートが作成され、自分の得意な点や改善すべき点が視覚的に把握できます。
これにより、校内で他の先生と共有することで、互いに学び合う機会が生まれます。夏休みなどには、1学期の授業を振り返り、2学期に向けた改善目標を宣言する研修も行われています。
教師の専門性の再認識:
対話的な学びを進める中で、子どもたち任せにできる部分と、教師の専門的な指導が不可欠な部分の見極めが重要であることが改めて浮き彫りになりました。先生が介入すべきタイミングと方法が、より深い学びに繋がると強調されています。
教員一人ひとりに寄り添う個別相談
集合研修では限界がある教員の育成に対し、個別相談の形を取ることで大きな効果が得られることが示されました。
個別最適化された授業づくり:
東原先生が学校を訪問し、教員一人ひとりと個別に45分程度の打ち合わせを実施。
教員それぞれの「授業の開始を変えたい」「自律的な学びを促したい」といったニーズや目標に基づき、具体的な授業案の作成をサポートします。
先生からの指示ではなく、「何がやりたいのか」「どうしたいのか」を丁寧に聞き出し、具体的なアイデアや他校の事例を紹介しながら、自律的な思考を促すアプローチが取られています。
学校全体の変革:
この個別相談を3年ほど続けた結果、学校全体として授業スタイルが大きく変化してきたことが実感されています。
子どもの個別最適な学びだけでなく、教員にとっても個別最適化された研修が非常に有効であることが示唆されました。
自己研鑽・相互啓発のための物理的空間の創出
教員がリフレッシュし、新たな発想を得られるような環境の重要性が語られました。
非日常的な空間の提供:
学校や役場の既存の空間から離れ、リラックスして自由に議論できる「アイススペース高木」という空間を地元自治体と協力して創設。
このスペースでは、職員会議の一部や講演会、教育委員会のミーティングなどが行われ、非日常的な空間が思考の切り替えや発想のリフレッシュに繋がる効果が期待されています。
窓から見える景色や、夕方にはお酒を飲みながら議論できる雰囲気など、精神的なゆとりをもたらす空間設計の重要性が述べられています。
まとめ
学校DXを推進する上で最も重要なのは、子どもたちの将来の姿を描くことです。現在の教育システムのままでは、変化の激しい未来を生きる子どもたちにとって不十分であり、デジタル技術、特にクラウドの力がその変革を大いに助けることになります。
情報活用能力の育成はもちろんのこと、SNSのようなデジタル世界の特性を理解し、適切に判断できる力を養うことも不可欠です。教育に携わる者が、これからの時代に求められる力を深く理解し、共通認識のもとで戦略的にDXを進める必要があります。
東山先生は、1978年からの教育情報化の経験に基づき、今回の3つの柱(対話的な学び、時間基準からの脱却、教員の自己研鑽環境整備)に焦点を当て、従来の「当たり前」を問い直し、具体的な工夫が効果を上げている事例を紹介しました。これらの実践は、他地域でも応用可能であり、少しずつ学校を変革していく手応えを感じていると締めくくられています。
(文責:久世)
3.「セカンドGIGAへの展望と課題」
堀田龍也氏(東京学芸大学大学院教育学研究科・教授)
動 画
資 料
内 容
1. GIGAスクール構想の現状と進展
GIGAスクール構想は、2020年のスタート以来、小中学校の児童生徒に1人1台の情報端末を配備し、授業改善を進めてきました。特に2022年度以降は多くの地域で本格的な活用が始まり、当初は「とにかく使ってみる」段階でしたが、現在は教科の学習と並行して、児童生徒一人ひとりが自分のペースで納得して学べるような授業改善へと移行しています。
1.1. 授業風景の変化
• 個別最適化された学びと協働学習: 児童生徒が教科書を読み込み、端末で情報をまとめ、クラウド上で共有することで、互いの進捗を確認し、助け合いながら学習する場面が増えています。教師は個々の進捗や努力に合わせて助言や指導を行います。
• 「学びに価値を感じる」ことの重要性: 当初はふざけてしまう児童生徒もいますが、学びに価値を感じ始めると、自分のペースで学べ、困ったときに教師だけでなく友達にも聞けるため、主体的に学びに向かう態度が育まれます。
• 体験とデジタルの融合: 理科の実験では、体験の重要性を前提としつつ、実験の経過を動画で撮影するなど、デジタルを活用して学びを深める事例が増えています。デジタルはリアルな学びを支えるツールとして機能しています。
• デジタルだからこそ可能な学び: 小学1年生がゴミ収集車の仕組みを学ぶ際に、写真を拡大して観察するなど、デジタルデバイスだからこそ可能になる詳細な観察や情報整理が行われています。
• 情報取り出しスキルの重要性: 児童生徒が自分のペースで学ぶには、教科書などの情報から必要な情報を自力で取り出すスキル(情報取り出し)が不可欠であり、義務教育段階でその訓練を積むことの重要性が強調されています。
• デジタル教科書の活用: 中学校の英語デジタル教科書では、ネイティブ音声でリスニング練習を繰り返せるため、児童生徒が自分のペースで反復学習を行うことが可能になります。小学校の算数デジタル教科書では、平行四辺形の面積を求める際に、図形を「切ったり動かしたり」して視覚的に理解を深めることができます。
1.2. アウトプットと学びの深化
• スライドによる共同編集: 児童生徒がスライドで学習内容をまとめる際、クラウド上で共同編集することで、他の児童生徒のまとめ方を参考にしたり、自分のまとめ方を多様化させたりすることができます。
• 進捗の可視化と相互支援: 個々の児童生徒の学習進捗を一覧で共有することで、「一人ですらすら」進める子から「一人でできた次も人に聞くんじゃないか」と自信がない子まで、それぞれの状況に合わせて助け合う文化が生まれています。
• 教え合いによる学びの深化: 早く進む児童生徒が、わからない友達のために説明動画を作成するなどの活動は、クラスへの貢献だけでなく、問題の本質をより深く理解することにつながり、高度な学びを促します。
• 「自分の学びは自分で責任を持つ」主体性の醸成: 堀田先生は、「分からないことは調べる」「他の人に聞く」「自分でできるようにする」といった、自分の学びに対する責任を持つ姿勢が主体性を育むと強調しています。
• 個別指導の質の向上: 自律的に学ぶ児童生徒が増えることで、教師は発達に障害のある子や心の弱い子、外国人児童生徒など、より手厚い支援が必要な児童生徒に時間を割くことができるようになります。
• 学習権の保障: 端末の持ち帰りやクラウドでの情報共有が日常的になることで、不登校や体調不良などで学校に来られない児童生徒もオンラインで学習に参加し、学習機会が保障されます。
• 心理的安全性と多様な学び方: 児童生徒が一人で学ぶだけでなく、友達と協力して学ぶことも増えています。教室内の心理的安全性が確保されることで、児童生徒は安心して学びに取り組めます。また、自分の考えが似ている人との確認や、異なる意見の人との意見交換など、状況に応じて多様な学び方を選択できるようになることが推奨されています。
1.3. 教師の役割と学級経営
• 振り返りの重要性: 学習内容だけでなく、自分の学び方(うまくいった点や改善点)を振り返る活動を区別して行うことで、より深い学びにつながります。
• 「教える」ことの継続: 児童生徒に任せる場面が増えても、教師が分かりやすく説明したり、明確な指示を出したりする場面は依然として重要です。実物投影機などを活用した丁寧な説明は、デジタル化が進んでも変わらず必要とされます。
• 学習規律と学級経営: 児童生徒が安心して学べる環境を提供するために、教師の学級経営の力量が試されます。清掃活動や机の整頓など、集団で学ぶ上での基本的な規律は引き続き重要です。
• 基礎的学力の定着: ドリル学習など、基本的な学びを疎かにすることなく、デジタルの利点を活かしながらも基礎を大切にする姿勢が重要です。
• タイピングスキルの必要性: 情報活用能力の基礎として、キーボード入力(タッチタイピング)の習得が非常に重要であり、児童生徒にしっかりと身につけさせるべきだと強調されています。
1.4. ICT活用の効果と学力
• Jカーブ効果: ICT活用は、導入当初は慣れないために効果が見えにくいものの(Jカーブ)、慣れてくると子どもの変化や教師の授業デザインの変化によって、劇的に効果が向上するという研究結果が紹介されました。
• 学力向上への寄与: GIGAスクール構想によって進められた「主体的・対話的で深い学び」に取り組んでいる学校では、全国平均や県の平均と比較して学力が高い傾向にあり、特に「思考・判断・表現」の能力が大きく伸びています。
• 知識・技能と思考・判断・表現のバランス: 基礎的な知識・技能はもちろん重要ですが、それを踏まえた上で、自分の力で考え、他者とコミュニケーションを取りながら学ぶ力を育むことが大切です。
________________________________________
2. 学力に関する誤解とCBT化の動向
2.1. 学力評価の多層性と注意点
• 学力の多層性: 「学力が上がった/下がった」と一括りにするのではなく、どの学習内容や活動が重要だったのか、どの児童生徒に合っているのかなどを、より詳細に分析する必要があります。
• 他校との比較の難しさ: 全国学力・学習状況調査の結果を単純に比較することの限界が指摘されています。問題も異なり、点数のわずかな差で優劣を判断するのは適切ではありません。
• 基礎学力と応用的な学び: 基礎的な学力が高度な学びを支えるのは当然であり、ICT活用は基礎的な学力を効率的に習得させ、より高度な学びに時間を割くためのものです。
• デジタルと紙の二項対立の超越: 「紙の方が良い」という意見は、紙で学んできた世代の前提に立っており、デジタルに慣れ親しんだ現代の児童生徒にとっては当てはまらない可能性があります。デジタル批判にはビジネス的な背景もあるため、冷静な判断が求められます。
• 「学ぶ力」「学ぶ意欲」の重要性: 学力は、学んだ結果身についた力だけでなく、「学ぶ力」や「学ぶ意欲」、学ぶスキルも含まれます。生涯にわたって学び続ける現代において、後者を育むことが非常に重要です。
2.2. CBT化の進展と準備の必要性
• 全国学力・学習状況調査のCBT化: 全国学力・学習状況調査がCBT(Computer Based Testing)に移行することが公表されています。2025年度の中学校理科から始まり、2027年度には小学校の国語・算数、中学校の国語・数学もCBT化されます。
• CBT化への準備: 各教育委員会は十分なネットワーク速度を担保し、学校はCBT経験を積む必要があります。文部科学省が提供するCBTプラットフォームの活用や、動画を用いた出題形式、マウス操作による回答など、従来の紙のテストとは異なる形式への慣れが求められます。
• 個別最適化された評価: CBT化により、児童生徒それぞれの理解度や進捗に合わせて問題を変えることが可能になり、採点や集計も迅速に行われるため、より早いフィードバックが可能になります。
________________________________________
3. 次期学習指導要領に向けた議論の方向性
2024年12月25日、文部科学大臣から中央教育審議会に対し、次期学習指導要領(2030年全面実施予定)に関する諮問が出されました。
3.1. デジタル化の課題意識と基本的な考え方
• 日本のデジタル化の遅れ: デジタル化における課題として、日本の現状の遅れや、実体験における格差、デジタル化の負の側面(依存、いじめなど)が挙げられています。
• デジタルとリアルの融合: 今後は「デジタルかリアルか」「デジタルか紙か」といった二項対立ではなく、デジタルの力でリアルな学びを支えるという基本的な考え方が示されています。バランス感覚を持って、最適な組み合わせを積極的に考えていくことが求められています。
3.2. 審議すべき内容のポイント(デジタル関連)
• 生成AIの影響と学習内容の問い直し: 生成AIの急速な発展は、学校で学ぶべき内容そのものを問い直すきっかけとなります。検索すれば分かるような知識の詰め込みではなく、教科の本質的な見方・考え方や、より大局的な学びが重要になります。
• 情報活用能力の抜本的向上: 情報社会において、情報活用能力(情報をうまく取り扱う能力、端末を使いこなす能力)の抜本的な向上が求められています。小学校からの教科としての情報教育や、現在の技術家庭科、高等学校の情報科のあり方を含め、カリキュラム全体の改善の中で検討されます。
• 教科書のあり方の検討: 教科書が分厚く、教師の負担となっている現状を踏まえ、今後の教科書の内容や分量、デジタル化の範囲などが検討されます。児童生徒が自立して学ぶことを前提とした教科書のあり方が模索されます。
• デジタル学習基盤を前提とした学び: 端末やネットワーク、クラウドといったデジタル学習基盤を前提に、児童生徒が自分で学びを自己調整し、教材や方法を選択できるような指導計画や学習環境をどう構築していくかが議論されます。当然ながら、その中での教師の指導性のあり方も重要な論点となります。
(文責:久世)
コーディネータ:村瀬康一郎氏(岐阜女子大学教授)
🔳 e-Learning(オンデマンド講座)
学校DX戦略コーディネータ概論【Ⅰ】 ~ 教育DX時代における新たな学び ~
学校DX戦略コーディネータ概論【Ⅱ】 ~ 学校DX戦略の策定と展望 ~
学校DX戦略コーディネータ概論【Ⅲ】 ~ カリキュラム開発と学びのデザイン ~(構想中)