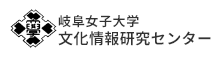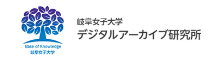【e-Learning】実践研究Ⅱ
第1講 デジタルアーカイブの基礎
林 知代(岐阜女子大学・講師)
1.何を学ぶか
デジタルアーカイブの定義や歴史的背景、そしてその専門職であるデジタルアーキビストの役割について解説しています。当初は公文書の保存が主な目的でしたが、次第に知的財産の活用や災害教訓の継承、さらには社会基盤としての共有へとその概念が拡大してきました。特に「ジャパンサーチ」に代表される情報のネットワーク化が進む中で、資料のデジタル化技術だけでなく著作権の処理や利活用の企画を行える人材の重要性が強調されています。最終的に、デジタルアーカイブは単なる保管場所ではなく、新たな文化創造を支えるための不可欠なインフラとして位置付けられています。
2.学習到達目標
① デジタルアーカイブとは何か説明できる。
② デジタルアーカイブがどのように発展してきたかについて具体例をあげ説明できる。
③ デジタルアーキビストに求められている能力について具体的に説明できる。
3.課 題
① デジタルアーカイブとは何か自身の立場で説明しなさい。
② デジタルアーカイブがどのように発展してきたか説明しなさい。
③ デジタルアーキビストに求められている能力は何か自身の立場で説明しなさい。
④ デジタルアーカイブの定義は、時代や社会のニーズと共にどう変化してきましたか。
⑤ デジタルアーキビストにはどのような能力が求められますか
⑥ ジャパンサーチは社会でどのように活用されているのですか
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.動画資料
【AI動画】
6.テキスト
第2講 デジタルアーカイブ開発と活用プロセス
櫟 彩見(岐阜女子大学・准教授)
1.何を学ぶか
デジタルアーカイブの開発プロセスとその具体的な活用方法について解説しています。アーカイブの利用は単なる資料の提示にとどまらず、データの分析を通じた課題解決や、新しい知見を生む知的創造サイクルへと発展することが示されています。運用面では、著作権やプライバシーに配慮した7つの選定評価項目に基づき、公開の適否を判断する重要性が説かれています。また、デジタル化の工程は記録・保存・発信・評価という循環するプロセスで構成されており、終わりなき活動であると定義されています。特に記録段階においては、対象に応じた撮影計画や機材準備、音声や環境データの収集など、多角的な手法が求められます。全体を通して、デジタルアーカイブを持続的な知的基盤として構築するための実践的な指針がまとめられています。
2.学習到達目標
① デジタルアーカイブの活用について具体例を挙げて説明できる
② 資料の選定評価について説明できる。
③ デジタルアーカイブのプロセスや記録方法について説明できる。
3.課 題
① デジタルアーカイブの活用について具体例を挙げて説明してください。
② 資料の選定評価の課題について説明してください。
③ デジタルアーカイブのプロセスや記録方法について説明してください。
④ デジタルアーカイブの活用における提示、課題解決、知的創造の三つの目的は何ですか。
⑤ 資料を公開する際の「選定評価」の基準を詳しく教えてください。
⑥ デジタルアーカイブの「記録」から「評価」までのプロセスを具体例を挙げて述べてください。
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.動画資料
【AI動画】
6.テキスト
第3講 デジタルアーカイブの評価とメタデータ
谷 里佐(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
デジタルアーカイブの適切な運用と評価について解説した講義テキストです。組織が自らの達成度を客観的に測定するための自己点検ツールを紹介し、特に重要視されるメタデータの国際標準や記述の指針を詳しく説明しています。また、すべての人が利用しやすい環境を整えるためのユニバーサルデザインの視点についても言及しています。後半では、岐阜女子大学が提案する地域資料向けの項目設定を例に挙げ、情報の二次活用を促す具体的な記述方法を提示しています。全体を通して、資料の保存から利活用までを円滑に進めるための標準化と評価の枠組みを学ぶ構成となっています。
2.学習到達目標
① 「デジタルアーカイブアセスメントツール」の内容について説明できる。
② 記述のための国際標準、国際指針などの事例について説明できる。
③ 資料(情報資源)のメタデータ記述ができる。
3.課 題
① 「デジタルアーカイブアセスメントツール」の評価項目の内、あなたが重要だと思う項目について、なぜそう思うかを含めて説明してください。
② 具体的に何か資料(情報資源)を一つ取り上げ、その資料のメタデータ記述項目を設定した上で実際の記述を行ってください。
③ デジタルアーカイブの質を評価するために用いられる主要な指標やツールの役割は何ですか。
④ 異なる機関の間で情報を共有するためにメタデータの国際標準が必要な理由は何ですか。
⑤ ダブリン・コアの15要素にはどのような項目が含まれますか?
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.動画資料
【AI動画】
6.テキスト
第4講 デジタルアーカイブの利活用
熊崎康文(岐阜女子大学・准教授)
1.何を学ぶか
デジタルアーカイブの定義から、博物館や図書館における具体的な利活用事例までを網羅的に解説しています。過去の文化遺産をデジタル化して次世代へ継承するだけでなく、地域の観光や教育、生涯学習の拠点として役立てる重要性が説かれています。国全体の取組として、複数の機関を繋ぐプラットフォームであるジャパンサーチや、総務省・内閣府による構築ガイドラインについても紹介されています。さらに、近年改正された博物館法に基づき、デジタル技術を用いた業務の変革(DX)を推進し、社会的・経済的価値を創出することが求められています。最終的には、デジタル情報を共有・連携させることで、知の地域づくりを実現することを目指した内容となっています。
2.学習到達目標
① 図書館におけるデジタルアーカイブの実践例を具体的に説明できる。
② 博物館におけるデジタルアーカイブの実践例を具体的に説明できる。
③ デジタルアーカイブの共通利用について説明できる。
3.課 題
① 図書館におけるデジタルアーカイブの実践例を具体的に説明しなさい。
② 博物館におけるデジタルアーカイブの実践例を具体的に説明しなさい。
③ デジタルアーカイブの共通利用について説明しなさい。
④ デジタルアーカイブの構築は地域社会の活性化や次世代への伝承にどう貢献しますか。
⑤ 日本の国家戦略におけるデジタルアーカイブの連携と基盤整備には何が必要ですか。
⑥ 博物館や図書館がデジタル化を推進する上で直面する実務的課題は何ですか。
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.動画資料
【AI動画】
6.テキスト
第5講 デジタルアーカイブによる地域活性化
久世均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
岐阜女子大学が提唱する「知の増殖型サイクル」を用いた、デジタルアーカイブによる地域活性化の取り組みを解説しています。飛騨高山の伝統的な木工技術や日本遺産をデジタル化し、適切に保存・活用することで、新たな知的価値を創造する仕組みを提案しています。このサイクルは、伝統産業の振興や観光資源の創出、さらには教育現場での教材活用まで多岐にわたる分野に応用が可能です。大学は知の拠点として、過去の歴史的資料を次世代へ継承し、地方創生に向けたイノベーションを牽引する役割を担っています。最終的に、アーカイブの活用と研究のフィードバックを通じて、持続可能な地域社会の発展を目指す内容となっています。
2.学習到達目標
① デジタルアーカイブと地域課題解決について説明できる。
② 地方創成イノベーションの創出について具体的に説明できる。
3.課 題
① 飛騨高山匠の技デジタルアーカイブにより,地域の文化産業を振興するための方策を3つ挙げて説明しなさい。
② デジタルアーカイブの活用が地域活性化や地方創成イノベーションに果たす役割は何ですか。
③ 知的創造サイクルは地域資源の保存と新たな知の創出をどのように繋ぎますか
④ 大学アーカイブが知の拠点として地域文化の継承や産業振興に貢献する方法は何ですか。
⑤ 地域学習でアーカイブを教材化する際の課題は何ですか?
⑥ 伝統技術の「技とこころ」をオーラルヒストリーで保存する方法とは?
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.動画資料
※本映像は本学の学部の授業(情報の管理と流通)の内容の一部を利用して提供しています。
【AI動画】
6.テキスト
7.資料
第6講 文化はどのように記録するの?
加藤 真由美(岐阜女子大学・准教授)
1.何を学ぶか
デジタルアーカイブの対象となる文化の定義や、それを後世に継承するための具体的な記録手法について解説しています。文化とは人々の生活様式や精神活動の総体であり、時代の変化に合わせてその姿をデジタル化し、社会で共有する重要性が説かれています。情報の収集から保存、発信、評価に至る4つのプロセスが示され、特に記録段階における留意点が詳しくまとめられています。さらに、人物撮影やドローンによる空撮など9種類の撮影技術を紹介し、多角的な視点から情報を残す方法を提案しています。単なるデータの蓄積に留まらず、背景にある人々の想いや関連資料を併せて記録することで、新たな文化創造に繋げることが本資料の核心です。
2.学習到達目標
①デジタルアーカイブの対象である“文化”について説明できる。
②記録に応じて,多様なデジタル化の方法を説明できる。
③記録の際の留意点について説明できる。
3.課 題
① 身近な“文化”をひとつ挙げ,具体的な記録方法を挙げてください。
② ①で挙げた記録方法の特性を説明しなさい。
③ デジタルアーカイブの対象となる「文化」の定義とコミュニティとの関係性はどのようなものか。
④ 文化をデジタル化する具体的なプロセスや手順は?
⑤ 人々の思いや背景を記録する際の重要なポイントは?
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.動画資料
【AI動画】
6.テキスト
7.資料
③ 沖縄おうらい
第7講 デジタルデータはどのように管理・流通するの?
加藤 真由美(岐阜女子大学・准教授)
1.何を学ぶか
激変する現代の情報社会において、文化的な資産をデジタルデータとして蓄積・活用することの意義を説いています。特にデジタルアーカイブの構築に焦点を当て、メタデータを用いた効率的な情報の管理と、多様なメディアを通じた情報の流通が重要であることを解説しています。信頼性の高いデータを誰もが利用できる状態で保存することは、社会課題の解決や新たな価値創造の基盤となります。日本におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の現状や、国際的な動向を踏まえつつ、デジタル技術を扱う人材に求められる知識や役割についても言及されています。
2.学習到達目標
①デジタルアーカイブの資料データの管理に必須であるメタデータの役割について説明できる。
②データの流通について多様な発信方法があることを理解し,説明できる。
③情報社会においてデータの管理と流通が重要である理由を説明できる。
3.課 題
① デジタルアーカイブにおいて,なぜ管理と流通が重要なプロセスであるのか,具体例を挙げて説明しなさい。
② Society 5.0において、デジタルアーカイブが果たす役割と社会的な意義は何ですか。
③ メタデータがデータの管理や検索に果たす役割とは?
④ メタデータの標準化や他機関との連携はどう行う?
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.動画資料
【AI動画】
6.テキスト
7.資料
② 情報の発信と伝達
第8講 デジタルアーカイブと知的財産権(1)
吉川 晃(岐阜女子大学・特別客員教授)
1.何を学ぶか
デジタルアーキビストが実務で直面する知的財産権や著作権の基礎知識を網羅した講義録です。著作権が無方式主義により自動発生することや、死後70年という長い保護期間を持つ点など、法的な基本原則が詳しく解説されています。また、教育現場でのオンライン授業に関する補償金制度や、クリエイティブ・コモンズのような柔軟な権利運用の仕組みについても触れています。権利処理の重要性だけでなく、肖像権や地域の慣習といった法的明文のない要素への配慮も強調されているのが特徴です。最終的には、適切な契約書の作成や正確な知識に基づいた運用が、文化振興とアーカイブ構築の両立に不可欠であると説いています。
2.学習到達目標
① デジタルアーキビストに著作権処理の能力が必要であることについて具体的に説明ができる。
② 著作者の権利について具体的に説明できる。
③ 著作権の契約書を作成できる。
3.課 題
① デジタルアーキビストに著作権処理の能力が必要であることについて具体的に説明しなさい。
② 著作者の権利について具体的に説明しなさい。
③ 著作権の契約書を作成しなさい。
④ デジタルアーキビストがアーカイブの構築から運用において果たすべき権利処理の役割は何ですか。
⑤ デジタルアーカイブの実務において、契約書の作成や肖像権、地域の慣習への配慮はなぜ重要ですか
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.動画資料
【AI動画】
6.テキスト
第9講 デジタルアーカイブと知的財産権(2)
坂井知志(岐阜女子大学・特別客員教授)
1.何を学ぶか
デジタルアーカイブ構築における知的財産権と実務上の課題を解説した講義録です。専門家としての主観を排し、第三者的な視点で著作権などの法的制度を批判的に検討することの重要性が説かれています。日本外交文書や震災記録といった具体例を通じ、膨大なデータの利便性と、複雑な権利関係や個人情報保護のバランスをどう取るべきかが示されています。単なる技術論にとどまらず、理念・技術・制度を統合的に捉え、他機関との連携や二次利用を促進する仕組み作りが、知識基盤社会の実現に不可欠であると結論付けています。
2.学習到達目標
① デジタルアーカイブの実践における著作権に関する課題について説明できる。
② 著作権のデジタルアーカイブの活用に関する課題について具体例を挙げて説明できる。
3.課 題
① デジタルアーカイブの実践における著作権に関する課題について説明しなさい。
② 著作権のデジタルアーカイブの活用に関する課題について具体例を挙げて説明しなさい。
③ デジタルアーカイブの構築において理念と技術と制度を統合する重要性は何か。
④ 複数のアーカイブが連携し知識基盤社会を築くための実践的課題は何か。
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.動画資料
【AI動画】
6.テキスト
第10講 ジャパンサーチとデジタルアーカイブ活用基盤
高野明彦(国立情報学研究所・名誉教授)
1.何を学ぶか
日本の多様な文化資産を統合的に検索・活用できるプラットフォーム、ジャパンサーチについて解説しています。このサービスは、国立国会図書館が中心となり、各分野の専門機関(つなぎ役)と連携して、書籍、文化財、メディア芸術などのメタデータを集約しています。単なる検索サイトにとどまらず、APIを通じた外部サービスへの展開や、利用者が独自の展覧会を作れる「マイノート」機能などを備えた、デジタルアーカイブの活用基盤を目指しているのが特徴です。また、著作権や権利情報を個別データごとに明示することで、二次利用を促進し、新たな知的創造を支援する役割を担っています。最終的に著者は、デジタルアーカイブが過去の記録を継承するだけでなく、現代のコミュニティを支える知識基盤として、人や活動の新たなネットワークを形成していくことの重要性を説いています。
2.学習到達目標
① ジャパンサーチの目的について説明できる.
② メタデータの連携方法について具体例を挙げて説明できる.
3.課 題
① ジャパンサーチについての課題について説明しなさい.
② ジャパンサーチAPIの活⽤例について具体例を挙げて説明しなさい.
③ ジャパンサーチがデジタルアーカイブのハブとして果たす役割と設立の目的は何ですか。
④ デジタルアーカイブを社会基盤として根付かせるための今後の戦略と価値は何ですか。
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像資料
【AI動画】
6.テキスト
第11講 世界のデジタルアーカイブの発展とその活用
時実象一(東京大学大学院情報学環)
1.何を学ぶか
多種多様な記録物を保存する世界のデジタルアーカイブの現状と活用事例を網羅的に解説しています。書籍や新聞、映画といった伝統的な文化遺産から、ウェブページやゲーム、SNS上の震災記録などの現代的なデジタル資産まで、保存対象が拡大している様子が示されています。インターネットアーカイブやヨーロピアーナといった主要なプラットフォームの役割に加え、各国の法的課題や運営体制の違いについても触れています。また、ウィキペディアタウンのような市民参加型の活動を通じて、地域資料がデジタル化され共有される意義を説いています。全体として、過去の記憶を未来へ繋ぐための技術的、社会的な取り組みの広がりを概観できる内容です。
2.学習到達目標
① 世界のデジタルアーカイブの動向ついて説明できる.
② 世界のデジタルアーカイブを俯瞰して,その活用の変化について具体例を挙げて説明できる.
3.課 題
① ジャパンサーチについての課題について説明しなさい.
② ジャパンサーチAPIの活⽤例について具体例を挙げて説明しなさい.
③ 世界のデジタルアーカイブには、どのような多様な種類と具体的な活用事例が存在しますか。
④ 主要なポータルサイトや組織は、デジタル資産をどのように収集しネットワーク化していますか。
⑤ 著作権侵害で係争中のオープンライブラリーの現状は?
3.プレゼン資料
【AIプレゼン】
4.映像資料
【AI動画】
6.テキスト
第12講 デジタルアーカイブと法制度の現在地点
福井健策(骨董通り法律事務所・パートナー弁護士)
1.何を学ぶか
デジタルアーカイブ構築における法制度の現状と課題を専門的な視点から解説したものです。主な焦点は、複雑な著作権法の仕組みと、許諾を必要とする原則および例外規定をいかに組み合わせて運用するかという実践的戦略に当てられています。さらに、法律が存在せず判断が難しい肖像権についても、民間ガイドラインによる点数化などの解決策が提示されています。また、2018年や2021年の法改正がもたらした検索サービスや絶版資料の利活用への影響についても詳しく触れています。後半では、デジタルアーカイブを社会の知識基盤として支えるための**「デジタルアーカイブ憲章」や政策提言の重要性が説かれています。全体として、権利の壁を乗り越え、文化資源を次世代へ継承するための官民一体となった指針**を示す内容となっています。
2.学習到達目標
① デジタルアーカイブの実践における著作権に関する課題について説明できる.
② 著作権のデジタルアーカイブの活用に関する課題について具体例を挙げて説明できる.
3.課 題
① デジタルアーカイブの実践における著作権に関する課題について説明しなさい.
② 著作権のデジタルアーカイブの活用に関する課題について具体例を挙げて説明しなさい.
③ デジタルアーカイブ憲章について,課題を説明しなさい.
④ デジタルアーカイブの構築において著作権や肖像権の権利処理が直面する主要な課題は何ですか。
⑤ 2018年や2021年の著作権法改正は、デジタルアーカイブの利活用をどのように促進させたのでしょうか。
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像資料
【AI動画】
6.テキスト
第13講 AIと人間の学び
赤堀侃司(東京工業大学・名誉教授)
1.何を学ぶか
生成AIの台頭という転換期において、人間ならではの学びの本質を問い直しています。著者の赤堀教授は、膨大なデータから推論するAIに対し、人間は共感や非認知能力、文脈の理解といった特性を持つことを強調しました。教育現場では、単なる知識の習得ではなく、問いを立てる力や情報の取捨選択、そして主体的にデザインする力を育むことが求められています。全編を通して、テクノロジーが進歩するからこそ、人間特有の感性や思考を磨く重要性が説かれています。AIとの共存時代における、新たな教育の指針を示す内容です。
2.学習到達目標
① 第1次AIブームから第2次AIブームへと移り変わり、変化した生成AIの学びについて説明することができる。
② 生成AIの発展により、私たちの学びに求められる7つの資質能力について説明することができる。
3.課 題
① 生成AIの進化から、これからの私たち人間の学びに求められる資質能力について説明しなさい.
② 生成AIが進化する中で人間が本来持つべき共感や感受性の役割は何ですか。
③ 膨大なデータを持つAIに対し人間が発揮すべき非認知能力とは何ですか。
④ AIが苦手とする「意味の理解」や日常の文脈とは?
⑤ AIが苦手な「意味の理解」を人間はどう補うべきですか
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像資料
【AI動画】
6.テキスト
7.資 料
① AIと人間の学び 壁の向こうで答えているのはAIか人か? (単行本)
② 第11講「AIと人間の学び」デジタルアーカイブin岐阜2023
第14講 人とAIの学習研究から考えるこれからの教育
益川弘如(聖心女子大学・教授)
1.何を学ぶか
聖心女子大学の益川弘如教授による、AI共生時代における教育の在り方をテーマにした講演録です。著者は、単なる情報の暗記やコピーではなく、「自分なりの言葉で説明できること」を人間ならではの価値ある学びと定義しています。教育現場での生成AI活用事例を通じ、AIを単なる効率化の道具ではなく、対話や思考を深めるためのパートナーとして利用する重要性が説かれています。また、人間固有の経験に基づくイメージ思考とAIの論理処理を比較し、AIには代替できない**「意味の理解」こそがこれからの学習の本質であると指摘しています。最終的に、技術革新が進む今こそ、主体的に知識を再構成する力**を育む授業への転換が必要であると結論付けています。
2.学習到達目標
① AI時代における「価値ある学び」について説明することができる。
② 人工知能や生成AIを活用した際の人間の学びの変容について説明することができる。
③ 生成AIを活用した具体的な授業事例から、学習観や授業観をとおして私たちの学びの本質を説明することができる。
3.課 題
① AI時代における「価値ある学び」とデジタル化された情報との関係について説明しなさい.
② 人工知能や生成AIの効果的な活用と私たちの学びの変容について説明しなさい.
③ AIと共生する時代において人間が行うべき価値ある学びの本質とは何か。
④ 生成AIを教育に活用する際、学習観や授業観をどう変容させるべきか。
⑤ 対話を通じた「知識の構成」においてAIができる役割は何?
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.動画資料
【AI動画】
6.テキスト
7.資料
① プレゼン資料
② 第12講「人とAIの学習研究から考えるこれからの教育」
第15講 人工知能(AI)とデジタルアーカイブの現状と未来
澤井進(岐阜女子大学・特任教授)
1.何を学ぶか
岐阜女子大学特任教授の澤井進氏による、人工知能(AI)とデジタルアーカイブの融合がもたらす未来像についての講義録です。著者は、デジタルアーカイブを「燃料」、生成AIを「機関車」に例え、両者が一体化することで正確で無害な学習データに基づく新たな文化の創造が可能になると説いています。特に、人類が蓄積してきた知恵をデジタル技術で継承する「デジタル文化遺伝子」という概念を提唱し、その重要性を強調しています。具体例として、古文書の解読や白黒映像のカラー化、AIによる作曲など、文化遺産の保存と活用の最新事例が紹介されています。最終的には、AI倫理という「レール」の上でこれらの技術を運用し、知的創造サイクルを回していく社会の在り方を展望する内容となっています。
2.学習到達目標
① 生成AIとデジタルアーカイブのそれぞれの機能からみた関係性について説明することができる。
② デジタルアーカイブを活用した人工知能との一体化によってもたらされる新たな可能性とは何か、説明することができる。
③ デジタル文化遺伝子というアイディアについて説明することができる。
3.課 題
① デジタル文化遺伝子の重要な役割とは何か、800字で説明しなさい。
② AIとデジタルアーカイブの一体化がもたらす未来のブレークスルーとは何か。
③ 質の高い学習データが生成AIの安全性や正確性に与える影響は何か。
④ デジタル文化遺伝子が知的創造サイクルをどう変える?
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.動画資料
【AI動画】
6.テキスト
7.資料
1.プレゼン資料
2.第13講「人工知能(AI)とデジタルアーカイブの現状と未来」
テキスト
【テキスト】
※ AI動画並びにAIプレゼンは、テキストを で分析し生成したものです。