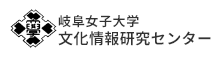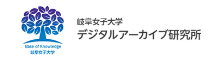【e-Learning】学校DX戦略コーディネータ概論【Ⅷ】 ~ デジタルアーカイブにおける新たな価値創造 ~
Ⅰ はじめに
デジタルアーカイブは,さまざまな分野で必要とされる資料を記録・保存・発信・評価する重要なプロセスである.このデジタルアーカイブは,わが国の知識基盤社会を支えるものであり,デジタルアーカイブ学会でも,デジタルアーカイブ立国に向けて「デジタルアーカイブ基盤基本法(仮称)」などの法整備への政策提言を積極的に行っている.今後,知識基盤社会おいてデジタルアーカイブについて責任をもって実践できる専門職であるデジタルアーキビストが必要とされている.ここでは,デジタルアーキビストの学術的な基礎として,デジタルアーカイブに関する歴史から我が国の動向並びにデジタルアーカイブの課題を学ぶ.また,この内容は,今後の学修におけるデジタルアーキビストの学びの地図となる.
Ⅱ 授業の目的・ねらい
・この授業は全15講に分かれて論述している.各講における参考文献並びに関連情報は,横のQRコードで示してある.各講においてこれらの参考文献などを読み込んで発展的な学修ができるように構成されている.
・各講の最後に研究課題が設定されており,個別で学修する場合にも,集団で学修する場合においても学修を深めるために主体的に研究課題を考えることが重要である.
・解が見えない地域課題を主体的に探求し,深化させ課題の本質を探り実践的な解決方法を導き出すための手法を研究する.
Ⅲ 授業の教育目標
・日本の目指す知識基盤社会を支えるのはデジタルアーカイブといっても過言ではありません.初期の文化遺産を中心とした展示やウェブ公開など提示中心から,いかに社会の全領域で知的生産やナレッジマネジメントに活用できるインターフェイス,横断的ネットワークなどの環境を確保するかの段階に入ったといえます.
・ここでは,15のテーマに基づいて,それぞれのテーマの中に研究課題を設定し,また,各講に学修到達目標を設定し,個々に学修の到達を確認することができる.
第1講 デジタルアーカイブの歴史とその課題
久世 均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
1994年頃に和製英語として誕生したデジタルアーカイブ(DA)の日本における歴史とその課題、特に知識基盤社会における役割を中心に概説しています。2001年以降、国策としてDA構築が進められたものの、欧米と比較して施策の遅れが指摘されており、近年は「共有」と「活用」の推進が重視されています。特に、岐阜女子大学(GWU)の取り組みが詳しく紹介されており、地域資源デジタルアーカイブを活用し、地域課題を解決するための「知の創造サイクル」を実践する人材育成を目指しています。GWUは、文部科学省の継続的な支援を受け、日本初の「デジタルアーキビスト」養成カリキュラムと資格認定制度を確立し、DAの実践的な体系化に大きく貢献しました。同大学は現在、デジタルアーカイブ学会の中心的なメンバー校として、知の増殖型サイクルDAの開発研究を地域貢献型の研究ブランドとして推進し、地方創生に寄与する姿勢を示しています。
2.学修到達目標
・ デジタルアーカイブの歴史について説明できる.
・ 知識基盤社会におけるデジタルアーカイブの必要性について事例をあげて説明できる.
3.研究課題
・ デジタルアーカイブの歴史をまとめて,何が変化して何が課題になっているかを話し合ってみなさい.
・ 日本におけるデジタルアーカイブの歴史的変遷と現状の課題は何ですか。
・ 欧米の先進事例と日本の施策にはどのような違いがありますか?
・ デジタルアーキビストにはどのような専門技能が求められますか?
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像
【AI動画】
6.テキスト
7.資料
第2講 デジタルアーカイブプロセス
久世 均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
従来のデジタルアーカイブ(DA 1.0)が抱える持続性の問題を考察し、持続可能なデジタルアーカイブ(DA 2.0)開発の必要性を論じています。事例検証の中心となるのは、2000年代初頭に沖縄の豊富な文化資源をデジタル保存・発信するために、巨額の予算を投じて制作された大規模事業「Wonder 沖縄」です。このプロジェクトは、高いアクセス数と技術的な賞を受賞するなど、当初は成功を収めましたが、ウェブコンテンツの配信は数年で終了してしまいました。この運用停止の背景には、デジタルアーカイブ構築が「成果物納品」を完成と見なす単年度の大型事業として進められ、コンテンツ公開後の継続的な維持管理や予算確保の計画が欠如していた点があると分析されています。結論として、「Wonder 沖縄」のアーカイブプロセスから長期保存・継承という重要な工程が抜け落ちていたことが、有用なデジタルアーカイブが消滅した根本的な原因であると指摘されています。
2.学修到達目標
・ 「Wonder沖縄」におけるWeb用コンテンツがなぜ消滅したかについて説明できる.
3.研究課題
・ 「Wonder沖縄」のアーカイブプロセスでは何が足りなかったのか.どうすれば持続可能になったのかを考えなさい.
・ デジタルアーカイブ1.0から2.0への持続可能な進化に必要な課題と改善点は何か?
・ 沖縄デジタルアーカイブ整備事業が目指した本来の目的と役割は何であったか。
・ 膨大な予算を投じたプロジェクトが運用停止に至った主な要因は何か。
・ 持続可能なデジタルアーカイブ2.0への改善策は?
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像
【AI動画】
6.テキスト
第3講 知のデジタルアーカイブ
久世 均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
2012年の提言を起源とする「知のデジタルアーカイブ」に関する研究会の議論を基に、社会の知識インフラの強化を目的としたデジタルアーカイブ化の現状と課題を概説しています。中心的な焦点は、図書館、博物館、文書館といったMLA(Library, Museum, Archive)機関が持つ知的資産のデジタル化を推進し、ネットワーク経由でのアクセス性を高めることです。研究会では、デジタル・ネットワーク社会に適合するためのシステム(技術)、人材育成、災害の三つのテーマに焦点を当て、掘り下げた共通理解を得るための議論が行われました。財政的・人的資源の不足、制度的制約といった課題を克服し、技術やノウハウの共有を進め、機関間連携(MLA連携)を強化することが重要な目標とされています。デジタルアーカイブはネットワーク化された社会の知識インフラの中核を担う可能性を持ち、その重要性は東日本大震災以降、災害に対する備えという側面からも高まっています。最終的な提言の目的は、公共的な知的資産の総デジタル化を進め、インターネット上で共有・利用できる仕組みの構築を図ることです。
2.学修到達目標
・ 知のデジタルアーカイブの提言について説明できる.
・ MLA連携などデジタルアーカイブの連携の必要性について説明できる.
3.研究課題
・ 知のデジタルアーカイブの提言を受けて博物館・図書館・公文書館の現状と課題について論述しなさい.
・ デジタルアーカイブを社会の知識インフラとして拡充するための主な課題は何ですか。
・ 図書館や博物館などの諸機関が連携することにはどのような重要性がありますか。
・ 知の地域づくりにデジタルアーカイブはどう貢献しますか
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像
【AI動画】
6.テキスト
7.資料
第4講 デジタルアーカイブの構築・連携のためのガイドライン
久世 均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
総務省が2012年に提言した「デジタルアーカイブの構築・連携のためのガイドライン」の抜粋であり、公共的な知的資産をデジタル化し、インターネット上での共有・利用を促進することを目的としています。この取り組みの究極的な目標は、貴重な資料へのアクセスを全国民に広げ、学習・研究を支援するとともに、知の地域づくりを推進し、地域経済の活性化に繋げることです。しかし、ブロードバンド基盤が整備されているにもかかわらず、多くの「知の記録組織」においてデジタルアーカイブの構築が遅れている点や、既存システムの陳腐化が課題として挙げられています。これを受け、本ガイドラインは、専門的でなく地域組織でも活用しやすいよう、運用マニュアル作成の参考となる指針を提供し、各組織がデジタルアーカイブを効率的に構築・連携できるよう策定されました。ガイドラインは、デジタルアーカイブの構築**、効果を高めるための連携、具体的な事例、そして導入のための実践的な手引きといった要素を網羅した構成となっています。
2.学修到達目標
・ 知の地域づくりの推進するために必要なことは何かを説明できる.
・ デジタルアーカイブの構築・連携において大切なことを説明できる.
3.研究課題
・ デジタルアーカイブの構築・連携のためのガイドラインをよく読んで,それぞれの組織のデジタルアーカイブ構築・連携の手引きを完成しなさい.
・ 知の地域づくりを推進するためにデジタルアーカイブが果たすべき役割は何ですか。
・ デジタルアーカイブの構築において組織間が連携することの重要性と利点は何ですか。
・ ガイドラインが推奨する運用マニュアルの作り方を示しなさい。
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像
【AI動画】
6.テキスト
7.資料
第5講 知の増殖型サイクルの情報処理システムの構成
久世 均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
デジタルアーカイブにおける「知の増殖型サイクル」という情報処理システムの構成と課題について解説しています。このサイクルは、資料の保管システムと利用システムに大きく分けられ、特にデータの分析・解析・加工処理のためのスキルや考え方、そして留意事項が焦点となっています。研究では、収集資料の選定、メタデータ、検索、分析処理に関するシステムの構成要素が詳細に検討されており、特に知的処理の可否や著作権に関する記録の重要性が指摘されています。さらに、新しい知の創造と次世代への伝承を可能にするためのデータ管理システムとして、Item PoolとItem Bankの構造と、そこで記録されるメタデータ項目についても説明されています。
2.学修到達目標
・ デジタルアーカイブのプロセスとして,知的創造サイクルをデジタルアーカイブに当てはめた知の増殖型サイクルについて説明できる.
3.研究課題
・ 知の増殖型サイクルにおけるメタデータの項目を作成してみなさい.なお,その際にDublin Core(ダブリン・コア)に配慮すること.
・ 知の増殖型サイクルにおいて保管システムと利用システムはどのように連携し機能しますか。
・ デジタルアーカイブにおける知的創造を支えるメタデータの役割と構成要素は何ですか。
・ 収集資料から新しい知を生成し次世代へ伝承するプロセスには何が必要ですか。
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像
【AI動画】
6.テキスト
第6講 知の増殖型サイクルの知的処理と流通システム
久世 均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
デジタルアーカイブにおける知の増殖型サイクルの構成、知的処理、および流通システムに関する研究課題を概説しています。このサイクルは、資料の保管、検索、分析、利用を繰り返すことで新しい知識が追加され、データの精度が向上することを目指しています。特に、利用目的に適した資料の検索、分析、加工処理の重要性が強調されており、そのためのメタデータの整備と横断検索の必要性が論じられています。また、知的処理に伴う著作権やプライバシーといった権利の課題についても触れており、CCライセンス(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)の適用や厳しいデータ選択条件の構築が求められています。最後に、サーチャー・アナリストによる検索結果の提供とインタラクティブな表示処理システムの開発が、効率的なデータ活用に不可欠であると指摘されています。
2.学修到達目標
・ デジタルアーカイブにおける知の増殖型サイクルの構成を説明できる.
3.研究課題
・ 「沖縄おぅらい」における知の増殖型サイクルはどのように構成されるか述べなさい.
・ 沖縄の学力向上における知の増殖型サイクルとは,どのようなサイクルになるか論じなさい.(参考:沖縄における教育資料デジタルアーカイブを活用した学力向上について)
・ 知の増殖型サイクルにおいてデジタルアーカイブはどのように新しい知識を生成し続けるのか。
・ 高度な知的処理を実現するためにメタデータと著作権管理はどのような役割を果たすか。
・ CCライセンスが知のサイクルに与える影響を述べよ
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像
【AI動画】
6.テキスト
第7講 知の増殖型サイクルを支えるメタデータの構成
久世 均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
「知の増殖型サイクル」を支える動的なメタデータの構成に焦点を当てており、特に地域資源のデジタルアーカイブ構築と運用における詳細なガイドを提供しています。地域資源を広義に定義し、その非移転性や有機的連鎖性といった特徴を説明した上で、地域再生には住民による創意工夫と総合的な取り組みが不可欠であると論じています。資料の主要な部分では、コンテンツを効率的に検索・利用するためのメタデータの役割、作成方法、および具体的な項目例(利用者用、管理者用、知の増殖型サイクル用)が詳細な表形式で提示されています。さらに、ダブリン・コアなどの国際的な標準との連携や、メタデータ付与作業における品質管理と効率性の重要性についても触れられています。
2.学修到達目標
・ 地域資源のメタデータの構成について説明できる.
3.研究課題
・ 地域資源のデジタルアーカイブのメタ情報の項目を考えてみなさい.そのうえで,それらの項目がなぜ必要なのか利用を考えて論述しなさい.
・ 地域資源の価値を高め、知の増殖型サイクルを回すためのメタデータの役割は何ですか。
・ 地域の多様な資源を体系化するために、どのようなメタデータの分類構成が必要ですか。
・ メタデータの付与作業を効率化するための具体的な工夫は何ですか?
・ 地域資源の「有機的連鎖性」とは具体的にどのような意味ですか?
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像
【AI動画】
6.テキスト
第8講 我が国におけるデジタルアーカイブ推進の方向性
久世 均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
日本におけるデジタルアーカイブ推進の方向性に関する提言の要旨をまとめたものであり、平成29年4月に関係省庁等連絡会・実務者協議会から出されたものに基づいています。主な焦点は、文化の保存・継承に加え、二次利用や国内外への発信を可能にするためのデジタルアーカイブの重要性です。また、知的財産推進計画2015に基づき、アーカイブ間の連携や基盤整備を促進する必要性が示されており、観光、教育、防災など多様な分野での活用が目指されています。さらに、デジタルアーカイブの構築と活用を持続的なものとし、その便益を国民のものとすることで、社会的、文化的、経済的発展に貢献することが重要であると強調されています。この中で、デジタルアーカイブが場所や時間を超えた情報アクセスを可能にし、イノベーションを推進する基盤となる「デジタルアーカイブ社会」のイメージが紹介されています。
2.学修到達目標
・ デジタルアーカイブ社会について説明できる.
・ オープンなデジタルコンテンツの必要性について具体例を挙げて説明できる.
3.研究課題
・ デジタルコンテンツのオープン化と著作権はどうしても利害が衝突する.デジタルアーカイブ社会においてオープンデータ化はなぜ必要で,そのために著作権をどのように改正する必要があるかについて論述しなさい.
・ 日本におけるデジタルアーカイブ推進の主な目的と社会的、経済的な意義は何ですか。
・ デジタルアーカイブの構築と利活用を促進するために、現在どのような課題がありますか。
・ アーカイブ推進における著作権の課題と法改正の方向性を述べなさい
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像
【AI動画】
6.テキスト
7.資料
第9講 デジタルアーカイブの構築・共有・活用ガイドライン
久世 均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
デジタルアーカイブの構築、共有、活用のための指針を詳述しており、2017年4月に策定された「デジタルアーカイブの構築・共有・活用ガイドライン」の主要な論点を解説しています。ガイドラインは、博物館や図書館だけでなく、大学、企業、官公庁など幅広い機関を対象としており、デジタル情報資源の整備と運用方法を報告しています。また、「デジタルアーカイブは構築して終わりではない」という考えに基づき、利用者ニーズへの対応や、Wikipediaを例にした利用者と一緒にアーカイブを育てていく仕組みの重要性を強調しています。さらに、「つなぎ役」(ハブ機能を持つ機関)や「成果物の還元」といった概念を通じて、国内のデジタルアーカイブ施策が欧米に比べて遅れている現状を踏まえ、今後の推進方向性や共通基盤の構築の必要性を示しています。
2.学修到達目標
・ デジタルアーカイブの構築・提供ついて説明できる.
・ アーカイブ機関が無理なくデータを整備・共有・連携できる共通基盤(プラットフォーム)の構築について,その機能を具体的に説明できる.
3.研究課題
・ 活用する場合は,メタデータを共有することで,様々なアプリの提供,付加価値の追加等を通じて,活用を行い,その成果物を保存・共有領域に還元し,再資源化することも期待されると報告されている.そのためには,具体的に何をすることが必要になるか述べよ.
・ 日本のデジタルアーカイブ推進において克服すべき現状の課題と解決策は何ですか。
・ 産官学の多様な機関が連携して構築を目指す共通プラットフォームの役割は何ですか。
・ デジタルアーカイブの「消滅」を防ぐために、共通基盤にはどのような役割が求められますか?
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像
【AI動画】
6.テキスト
7.資料
デジタルアーカイブジャパン推進委員会及び実務者検討委員会
3か年総括報告書 我が国が目指すデジタルアーカイブ社会の実現に向けて
第10講 知的財産推進計画に見るデジタルアーカイブ
久世 均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
知的財産推進計画2017におけるデジタルアーカイブの位置づけと、その推進の必要性について論じています。文化資源の次世代への継承と新たな価値創造を目的として、分野ごとのデジタルアーカイブ構築に加え、分野横断的な連携の強化が重要視されています。今後の方向性として、各アーカイブ機関、連携を担う「つなぎ役」、そして国のそれぞれの役割が具体的に示されており、メタデータ整備や統合ポータルの構築が主要な課題とされています。また、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、デジタルアーカイブの日常的な活用と、コンテンツ創出基盤としての社会実現を目指すことが強調されています。
2.学修到達目標
・ 知的財産推進計画を理解し説明できる.
・ 新たな価値創造とデジタルアーカイブの構築について具体例を出して説明できる.
3.研究課題
・ 知的財産推進計画とデジタルアーカイブとの関係を明確にして,知的財産計画の目的について論述しなさい.
・ 知的財産推進計画においてデジタルアーカイブはどのような役割と目的を持っていますか。
・ デジタルアーカイブ構築で欧米諸国と比べ遅れている点は何か?
・ 知的財産推進計画においてデジタルアーカイブの構築が重視される目的は何ですか。
・ デジタルアーカイブ構築における「つなぎ役」の具体的な役割は?
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像
【AI動画】
6.テキスト
7.資料
第11講 地域資源デジタルアーカイブによる知の拠点の形成
久世 均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
地域資源デジタルアーカイブを活用した「知の増殖型サイクル」の形成に焦点を当てた講義の抜粋です。具体的には、知識基盤社会におけるデジタルアーカイブの有効活用により、地域課題の解決や新たな知の創造、そして地方創生イノベーションの創出を目指す大学の取り組みについて説明されています。特に、「飛騨高山匠の技」に関するデジタルアーカイブを事例として取り上げ、このサイクルを産業技術、歴史、観光、教育の各分野に適用する具体的な方法が詳細に論じられています。また、大学アーカイブの機能と役割についても触れられており、大学が知の拠点として果たすべき主導的な役割が強調されています。
2.学修到達目標
・ デジタルアーカイブと地域課題解決について説明できる.
・ 地方創成イノベーションの創出について具体的に説明できる.
3.研究課題
・ 飛騨高山匠の技デジタルアーカイブにより,地域の文化産業を振興するための方策を3つ挙げて論述しなさい.
・ デジタルアーカイブは地域課題解決と地方創生にどのように貢献するのか。
・ 大学アーカイブの基本的な役割は何か?
・ デジタルアーカイブは地域課題の解決や地方創成にどのような役割を果たすか。
・ 知の増殖型サイクルにおいて収集された情報はどのように新技術へ繋がるか。
・ 匠の技をデジタル化することで、どのように雇用が生まれる?
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像
【AI動画】
6.テキスト
7.資料
第12講 知の拠点形成のための基盤整備
久世 均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
岐阜女子大学が推進する地域資源デジタルアーカイブによる知の拠点形成のための基盤整備事業について概説しています。具体的には、知識基盤社会において、大学独自の「知の増殖型サイクル」を活用し、地域の伝統文化産業の振興や観光資源の発掘といった地域課題の解決を目指す取り組みです。この事業は、飛騨高山の匠の技や郡上白山文化遺産をデジタルアーカイブ化し、その効果を社会経済的効果および意識的効果の測定を通じて定量的に分析する手法を確立しようとしています。また、デジタルアーカイブの活用を支える「サーチャー・アナリスト」や「コーディネータ」といった専門職の人材育成カリキュラム開発も重要な目標とされています。
2.学修到達目標
・ 知識基盤社会とデジタルアーカイブの関係について説明できる.
・ 知識循環型社会について具体的に説明できる.
・ 地域課題の解決とデジタルアーカイブについて説明できる.
3.研究課題
・ 大学が地域の知の拠点形成のための基盤整備に必要な要素は何か論述しなさい.
・ デジタルアーカイブは知識基盤社会においてどのような役割を果たし知を循環させるか。
・ 知の増殖型サイクルは地域課題の解決と新たな価値創造にどう貢献するか。
・ 地域の伝統文化を継承し振興するために大学が果たすべき役割は何か。
・ 地域資源の「遺贈価値」や「威信価値」をどう測定するのか
・ 飛騨高山の匠の技を次世代へ継承する具体的な手法は
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像
【AI動画】
6.テキスト
7.資料
第13講 デジタルアーカイブにおける新たな評価法
久世 均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
デジタルアーカイブの評価方法と国際標準化という二つの主要なテーマを扱っています。まず、ヨーロッパで開発された「Impact Playbook」について詳細に解説しており、これは文化機関がデジタルアーカイブ事業の多様な価値を評価し共有するための共通言語として機能するガイドラインです。このプレイブックは「設計」「査定」「物語」「価値評価」の4段階から成り、特に「社会的インパクト」「経済的インパクト」など4つの「戦略的視点」と「有用性レンズ」「学習レンズ」など5つの「価値レンズ」を用いて評価を具体化します。次に、経済産業省が推進するデジタルアーカイブの利活用促進のための国際標準化の取り組みについて説明しており、これはISOにおいて「デジタルアーカイブにおける権利情報の記述と表示」に関する国際標準の開発が承認されたことに焦点を当てています。この標準化の目的は、ウェブサイトごとに異なり利用の障壁となっていた権利情報**の記載内容と表示位置を統一し、二次利用の活性化と日本文化の国際的な利用促進を図ることです。
2.学修到達目標
・ 新たな評価法であるインパクト評価について具体的に説明できる.
3.研究課題
・ デジタルアーカイブの新しい評価について論述しなさい.
・ デジタルアーカイブの価値を多角的に測定するインパクト評価の意義と役割は何ですか。
・ 評価モデルを構成する視点やレンズは具体的にどのような変化を捉えますか。
・ 権利情報の国際標準化はデジタルアーカイブの利活用と信頼性にどう貢献しますか。
・ 評価結果を「物語(ナラティブ)」にする利点を知りたい
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像
【AI動画】
6.テキスト
第14講 デジタルアーカイブを活用した地域課題の解決手法
久世 均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
飛騨高山の「匠の技」という伝統文化産業が抱える後継者不足や海外展開などの地域課題に対し、デジタルアーカイブ(DA)を有効活用して解決策を確立するための研究について述べています。特に、新しい知を創造する独自の「知の増殖型サイクル」の手法を応用し、地域文化の創造を進めるデジタルアーカイブの新しい評価指標を提案しています。この評価指標は、住民の地域資源に対する認知度を定量的に分析するために、項目関連構造分析(IRS分析)を適用し、R-L表やそこから導出される注意係数および差異係数を用いて、広報や伝承方法を検証する論理的根拠を確立することを目指しています。本研究は、地域振興に資する伝統文化的事業の社会経済的効果および意識的効果を測定する実践的な取り組みとして、文部科学省の事業に採択されています。
2.学修到達目標
・ 「知の増殖型サイクル」の手法による地域課題に実践的な解決方法を確立することについて説明できる.
3.研究課題
・ 住民R(Resident)-地域資源L(Local Resources)認知度診断表から何がわかるか論述してみなさい.
・ デジタルアーカイブは地域課題を解決するためにどのような役割を果たしますか。
・ 知の増殖型サイクルは地域資源の保存と活用にどう貢献しますか。
・ 新しい評価指標は伝統文化の継承や財源確保をどのように支援しますか。
・ 地域資源の社会的価値を測る「IRS分析」の仕組みを詳しく知りたい
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像
【AI動画】
6.テキスト
第15講 首里城の復元とデジタルアーカイブの可能性
久世 均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
沖縄戦で多くが消失した首里城の復元プロセスにおいて、鎌倉芳太郎が戦前に収集し保存していた資料がいかに重要な役割を果たしたかを論じています。特に、鎌倉資料は、復元に不可欠な設計図や寸法を記した**『百浦添御殿普請付御絵図并御材木寸法記』などを含んでおり、資料の空白を埋めました。筆者は、この復元事例を「知の増殖型サイクル」に当てはめ、資料の保存が新たな文化資源や観光客増加、ひいては地域経済の活性化**につながることを示しています。また、この事例から、デジタルアーカイブの未来において、原資料と二次資料の「保存」がいかに重要であるかを提言しています。
2.学修到達目標
・ 鎌倉芳太郎と首里城復元の過程で説明できる.
・ デジタルアーカイブという視点から鎌倉芳太郎資料集について説明できる.
3.研究課題
・ 首里城の復元に鎌倉芳太郎の資料が重要であったかについてデジタルアーカイブの視点で論述しなさい.
・ 鎌倉芳太郎が戦前に収集した資料は首里城の復元にどのような役割を果たしましたか。
・ 首里城の復元プロセスは沖縄の文化資源や経済にどのような影響を与えましたか。
・ 知の増殖型サイクルの視点から見たデジタルアーカイブの将来像とは何ですか。
・ 首里城の取り壊しを救った鎌倉芳太郎と伊東忠太の活動について教えてください。
4.プレゼン資料
【AIプレゼン】
5.映像
【AI動画】
6.テキスト
資料
公開講座:沖縄デジタルアーカイブセミナー
Ⅳ 課題
課題1
テーマ1からテーマ8の中で,興味を持った研究課題についてさらに詳しく調べA4用紙1ページにまとめよ.
課題2
テーマ9からテーマ15の中で,興味を持った研究課題についてさらに詳しく調べA4用紙1ページにまとめよ.
Ⅴ アドバイス
課題1解説
テキスト並びに参考文献を参考に論述しなさい.
課題2解説
テキスト並びに参考文献を参考に論述しなさい.
Ⅶ テキスト
年表
1.年表
Ⅷ タキソノミーテーブル(教育目標の分類体系:タキソノミー)
タキソノミーテーブル(教育目標の分類体系:タキソノミー)情報の管理と流通
※ AI動画並びにAIプレゼンは、テキストを で分析し生成したものです。