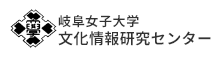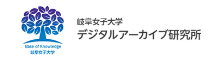【e-Learning】教育リソース・デジタルアーカイブⅠ
デジタル社会の教育の情報基盤として
【e-Learning】教育リソース・デジタルアーカイブ
Ⅰ はじめに
教育リソースのデジタル化の研究は、1960年代に始まり、教育論文・資料等の情報管理がERIC(Education Resources Information Center)等で進みだした。また、米国では教師教育の観点から教育実践での有意な資料を原記録として保管・分析がプロトコール運動として始まった。
学習システム研究会(岐阜・愛知の教員、大学関係者の会)では、1967年から教育実践の記録・保管・分析が(岩田晃教諭による)教師教育、教育実践資料のデジタル化の研究として始まった。その後、1970年代には、カナ・英数字を用いたCMIシステムとして、教材・学習材・教育実践研究資料等のデジタル管理とその教育利用が進みだした。
1978年には、小学校用のCMIシステムが開発され、一人一人の学習状況の検出、学習(指導)目標、コードに対応し、個に適した教材・学習材の利用が可能になった。その後、日本語処理が汎化し教育情報処理システムが開発されCMIシステムを基礎にした教育資料のデジタル利用が進みだし、2000年頃からは、映像・音声・文字・数値等のメディアの一体的な取り扱いが可能になり、教育リソース・デジタルアーカイブ(DA)として利活用が始まった。
教育リソースDAの教育実践研究資料を用いて、2010年代には沖縄の二つの小学校で学習指導力、学力の向上に役立てた。
教育リソースDAは、今後、このような教育研究を基礎にして、生成AIの教育利用、個別学習の自動化、主体的な学び、課題解決学習等で教育の質的向上、教師の働き方改革等のためのデジタル化の基盤として重要となる。
Ⅱ 授業の目的・ねらい
教育のデジタル化の発展と今後のOECDの個別学習の自動化、主体的な学び、課題解決学習等での利活用を考える。
Ⅲ 授業の教育目標
第1講~第15講の各研修目標に基づいて、テキストと動画教材を利用して教育リソース・デジタルアーカイブの活用ついて理解し、各講の課題に取り組むことで、教育リソース・デジタルアーカイブについて理解する。
第1講 教育リソースの初期のデジタル管理 ~教育資源のデジタル化の発展~
久世均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
950年代から現代に至るまでの教育リソースのデジタル管理と活用の変遷を解説しています。初期の1960年代には、アメリカのERICによる文献管理や、授業風景を数秒おきに撮影するプロトコール運動などを通じて、実践記録のデジタル化に向けた試行錯誤が始まりました。続く1970年代には、カナや英数字のみを扱うCMIシステムが登場し、レスポンスアナライザーを用いた学習反応のデータ分析や教材管理の基礎が築かれています。1980年代の日本語処理能力の向上や1990年代のマルチメディア化を経て、教育基盤はより高度なデジタルアーカイブへと進化しました。最終的にこれら蓄積された資源は、現代の教育DXや個別の学習ニーズに最適化された自動学習支援を実現するための重要な礎となっています。
2.内容
Ⅰ-1.教育資源の初期の管理(1960年代)
Ⅰ-1-1.ERIC等による教育資源の管理・流通
Ⅰ-1-2.教育実践資料の記録について
教材,カリキュラム等の資料の保管・提供の必要性-木田宏先生(昭和24年)
Ⅰ-1-3.アメリカのプロトコール運動(教育実践資料の原資料)
Ⅰ-1-4.教師等による教育実践の記録分析とデジタル保管の準備(1960年代)
Ⅰ-1-5.教育実践の記録例
Ⅰ-1-6.教育実践資料のデジタル化の準備
Ⅰ-2.教育実践資料のデジタル保管と利用(CMI)
~1970年代のコンピュータは英数字、カナ文字しか利用できなかった~
Ⅰ-2-1.教育実践研究用CMIの開発と利用
Ⅰ-2-2.何をコンピュータで記録・管理・分析
Ⅰ-2-3.教育資料項目と学習データの記録(Item LibraryとData pool)
Ⅰ-2-4.CMIの構成について
Ⅰ-2-5.教育実践のCMIの開発と利用
3.課 題
① 教育リソースのデジタル管理は1960年代から現代にかけてどのように発展してきましたか。
② プロトコール運動が教師教育に果たした役割を説明せよ。
③ 1960年代のERICにおける教育資源管理の特徴を述べよ。
4.プレゼン資料
5.動画資料
6.テキスト
第2講 教育リソースのマルチメディアとしての資料管理 ~教育リソース・デジタルアーカイブとしての発展~
久世均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
1970年代から現代に至るまでの教育リソースのデジタル化と、その管理システムの変遷を詳説しています。初期の日本語(漢字)処理機能の獲得から、映像や音声を含むマルチメディア・デジタルアーカイブへの発展プロセスが体系的にまとめられています。特に岐阜大学や国立教育研究所での実例を挙げ、教材データベースやメタデータの構成が教育現場でどう活用されてきたかを記述しています。また、地域資料の保存やGIGAスクール構想を見据えた、教育情報のネットワーク化と共有の重要性についても提言しています。最終的には、デジタル技術を用いた次世代の学習支援体制の構築を目指す内容となっています。
2.内容
Ⅱ-1.教育情報処理システム(1980年~)~日本語(漢字処理)の利用~
Ⅱ-1-1.教育情報の記録について
Ⅱ-1-2.メタデータの構成
Ⅱ-1-3.教育情報システムの出力例
Ⅱ‐2.マルチメディアデータ管理・流通(1995年~)
~デジタルアーカイブの提唱~
Ⅱ-2-1.映像・音声・文字等のメディアの一体的な記録
Ⅱ-2-2.デジタルアーカイブについて
Ⅱ-2-3.教育情報センター(国立教育研究所)
Ⅱ-2-4.地域教育資料のデジタルアーカイブ
Ⅱ-2-5.教育資料の記録の方法
Ⅱ-2-6.メタデータの構成
Ⅱ-2-7.管理・流通・検索のためのメタデータの構成
Ⅱ-2-8.利活用に関する項目
3.課 題
① 教育リソースのデジタル管理は、1980年代から現在にかけてどのように進化してきましたか。
② 1980年代の教育情報処理システムにおけるメタデータの課題は何か。
③ 教育リソースのメタデータにおける「4W」の構成要素を答えよ。
④ 1981年に開発されたSIS-TEM IVの主な機能は何か。
4.プレゼン資料
5.動画資料
6.テキスト
第3講 権利処理(権利と保管)
久世均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
教育現場におけるデジタル教材の活用と、それに伴う権利処理の重要性について解説しています。特に著作権、プライバシー保護、肖像権の三つの観点から、法的な留意点や許可取得の必要性が詳しく述べられています。教育機関が円滑に資料を利用できるよう、著作権法第35条の例外規定や、近年導入された授業目的公衆送信補償金制度についても具体的に紹介されています。また、二次利用を容易にするためのクリエイティブ・コモンズ・ライセンスや、文化庁の自由利用マークの活用が推奨されています。最終的には、資料を短期的利用と長期的保存に分類し、適切なメタデータを付与して管理するデジタルアーカイブの構築指針を示しています。
2.内容
Ⅲ-1.著作権
Ⅲ-2.プライバシー(個人情報保護法)
Ⅲ-3.肖像権(保護者の許可)
Ⅲ-4.実施上の注意
3.課 題
① 教育リソースの適切な権利処理において、著作権やプライバシー保護が果たす役割は何ですか。
② 著作権法第35条で複製が認められない事例を挙げなさい。
③ OECDが提唱したプライバシー保護の8原則を全て答えなさい。
④ クリエイティブコモンズの基本となる4要素を答えなさい。
4.プレゼン資料
5.動画資料
6.テキスト
第4講 教育リソースの教育実践研究での利用
久世均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
提供された資料は、沖縄県のB小学校において宮城卓司教頭(当時)が主導した、教育リソースの活用による学力向上の実践記録です。当初、全国最下位レベルの学力や厳しい家庭環境という課題に直面していましたが、教頭は「教頭だより」を発行して最新の教育理論を広め、QRコードを用いた授業動画の共有により指導の具体化を図りました。さらに、年間100時間に及ぶ授業参観とデータに基づくフィードバックを継続したことで、教師の指導力が向上し、児童が主体的に学ぶ姿勢へと変化しました。この取り組みの結果、全国学力・学習状況調査で全国上位に食い込む劇的な成果を収め、地域や進学先の中学校からも高い評価を得るに至りました。本資料は、デジタルアーカイブなどの教育資源と管理職の伴走支援が、学校文化を刷新する強力な手段となることを示しています。
2.内容
Ⅳ-1.教育リソースの利用の発展、教育資源の初期の管理(1960年代)
Ⅳ-1-1.戦後の木田宏による教材資料の収集・記録・管理・流通の必要性の指摘
~木田宏“新教育と教科書制度”(昭和24年2月)実業教科書~
Ⅳ-1-2.教育実践での教育事象の原記録
~アメリカのプロトコール運動での教育資料の記録~
Ⅳ-1-3.教育実践の総合的な記録・管理・分析での利用
~学習状況の検出・記録・管理の教師教育での利用~
Ⅳ-1-4.教育資料の日本語(漢字)データベースの利用(教育情報システム)
~日本語を用いた情報の利用が1980年頃から可能になる~
Ⅳ-1-5.コンピュータを用いた記録・分析結果による教師教育(カナ、英数字)~CMIシステムの開発とその利用~
Ⅳ-1-6.教育資料の日本語(漢字)データベースの利用(教育情報システム)~日本語を用いた情報の利用が1980年頃から可能になる~
Ⅳ-2.教育実践資料として、誤りの傾向、学びでの変化の検討
~正誤、誤答分布、クロス処理の利用~
Ⅳ-3.教育実践での利用例
~過去の教育実践研究資料の学習指導での利用~
Ⅳ-3-1.利用の手順
Ⅳ-3-2.過去の教育実践資料の抽出例について
Ⅳ-3-3.手引きの作成
Ⅳ-3-4.教頭だより
Ⅳ-3-5.シンポジウムより実践例の紹介(宮城卓司先生)
3.課 題
① デジタルアーカイブの教育リソースは授業改善と学力向上にどう貢献しますか。
② 授業改善において、具体的なデータ提示が重要な理由は何か。
③ 授業改善において、具体的なデータ提示が重要な理由は何か。
④ 授業改善において「理解・具体化・実践」のサイクルをどう回すか。
4.プレゼン資料
5.動画資料
6.テキスト
第5講 教育リソースの学習指導計画での利用 ~ 学習プログラムの開発 ~
久世均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
提供された資料は、教育リソースやデジタルアーカイブを活用した、効果的な学習指導計画の策定手法について解説しています。特に、教える内容の順序を決める「系列化処理」の重要性が強調されており、過去の学習データや統計的な分析を用いて最適な学びの順序を導き出す方法が示されています。具体例として、物理の学習問題集やCAI教材の開発において、生徒の誤答傾向を分析し、理解を促す配置を実現した事例が紹介されています。さらに、1960年代からの研究の歩みを振り返りつつ、現代のAIや生成AIに対応した新しいデジタルアーカイブのあり方についても言及しています。最終的に、これらの技術を個別学習の自動化や教員の負担軽減に役立てる、未来の教育デザインの必要性を説く内容となっています。
2.内容
Ⅴ-1.教授項目の系列化(学びの順序)
~教育リソースを用いた教授項目の順序~
Ⅴ-1-1.CMIシステムを用いた教授項目の構造化
Ⅴ-1-2.系列化処理
Ⅴ-1-3.系列化処理の利用
Ⅴ-2.系列化を用いた学習プログラムブック
Ⅴ-2-1.学習プログラムの開発
Ⅴ-2-2.高等学校物理学習問題集「プログラム物理」
(学習システム研究会物理班編)について
Ⅴ-3.CAI用学習ソフトの開発
Ⅴ-3-1.教材作成への適用―波動CAI教材の構成―
Ⅴ-3-2.CAI教材開発
Ⅴ-4.知的操作処理を用いたカリキュラム開発と教育リソース
~AI、生成AI等の利用に適する教育リソース・デジタルアーカイブ~
3.課 題
① 教育リソースのデジタルアーカイブ化は学習指導計画の立案をどのように変革するか。
② 教授項目の順序を決めるための一般的な三段階の手法を述べよ。
③ 教育リソースのメタデータに含めるべき教育的情報を列挙せよ。
4.プレゼン資料
5.動画資料
6.テキスト
第6講 リソースを利用した学習 ~ 多様な学習を支援する教育リソース ~
久世均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
デジタルアーカイブやメタデータを活用した現代的な教育リソースの在り方について解説しています。情報通信技術の発展により、地域の歴史資料やオーラルヒストリーを教室で手軽に利用できるようになった現状を提示しています。こうしたデジタル資源の活用は、児童の課題解決能力を養うだけでなく、教材準備に追われる教師の負担軽減にもつながると説いています。具体例として、沖縄の修学旅行ガイドや高校物理の個別学習、遠隔地との協働学習における実践的な利点が紹介されています。最終的に、産官学が連携して教育リソースを整備し、生成AIなどの新技術と融合させることで、より質の高い学びを実現する方向性を示しています。
2.内容
Ⅵ-1.一般的なリソースの利用
Ⅵ-2.課題解決での教育リソースの活用(オープン教育)
Ⅵ-3.個人学習での資料の活用(高校物理の例)
高等学校物理の個人学習とCMIの利用
Ⅵ-4.調べ学習での教育リソースの活用
Ⅵ-5.遠隔共同(協働)学習の課題解決での利用
Ⅵ-6.修学旅行等の案内の情報
~教育リソースを用いた沖縄おぅらい(修学旅行用)について~
3.課 題
① デジタルアーカイブの活用は教師の負担軽減と学習の質向上をどう両立させますか。
② オープン教育における教師の具体的な支援内容と課題は何か。
③ デジタルアーカイブ活用が教師の働き方に与える影響はあるか。
④ CMIの学習記録を活用することで解決できる課題は何か。
4.プレゼン資料
5.動画資料
6.テキスト
第7講 教育リソースの個別学習での利用
久世均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
個別学習における教育リソースの活用と、その歴史的変遷および実践例を解説しています。1970年代のカナ文字による初期システムから、1980年代の日本語処理とプリント出力による個別指導の発展、そして現代のデジタルアーカイブ活用までを網羅しています。特に沖縄県の小学校での事例では、デジタル化された過去の教育知見を基に「指導を伴う繰り返し学習」を徹底し、児童の学力を劇的に向上させた成果が詳述されています。教師の多忙化や児童の意欲低下といった課題に対し、データ分析に基づく適切な介入と、短い個別指導の積み重ねが重要であると結論付けています。最終的に、一人ひとりの学習歴に応じた最適な教材提供を可能にするシステムの構築と、管理職を含めた組織的な取り組みの意義を提示しています。
2.内容
Ⅶ-1. デジタル化初期の個別学習資料の提供(1970年代)
Ⅶ-2. 教育情報処理システム(1980年代)の個別学習資料の提供
Ⅶ-3.教育実践研究資料を用いた集団・個別学習の展開
Ⅶ-3-1.授業(大学院)での資料の提供
Ⅶ-3-2.教育実践についてのシンポジウムより
Ⅶ-3-3.正答率の変化点以後の個別学習について
Ⅶ-3-4.教育リソース(教材・学習材)、デジタルアーカイブの活用
3.課 題
① 個別学習支援における教育リソースとデジタルアーカイブは、時代と共にどう変遷しましたか。
② A小学校で学力向上を実現した「繰り返し学習」の仕組みを述べよ。
③ 1980年代における教材データベース流通の課題を説明せよ。
④ 1970年代のCMIにおける学習資料の提供方法を述べよ。
4.プレゼン資料
5.動画資料
6.テキスト
第8講 個別学習の自動化と教育リソース
久世均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
OECDの報告に基づいた個別学習の自動化レベル(0〜5段階)と、それを支える教育リソース・デジタルアーカイブの役割について論じています。自動化の進展には、学習者の生理学的データや行動データを分析する「検出」、学習歴を統合的に判断する「診断」、そして最適な教材を提供する「行動」のサイクルが不可欠です。教育現場では、教師が情報を確認するダッシュボードの活用や、AIによる教材の系列化処理が重要な技術的基盤となります。過去のCMIシステムから最新のAI技術までを紐解き、各レベルにおける学習支援の変遷を体系的に整理しています。最終的には、全国で共通利用可能な教育リソースの基盤整備が、学習の質向上と教師の負担軽減に寄与することを提言しています。
2.内容
Ⅷ-1-1.個別学習の構成
Ⅷ-1-2.個別学習と教育リソース
Ⅷ-2.個別学習の自動化のレベルと教育リソースの利用
Ⅷ-2-1.個別学習の自動化レベル0と教育リソース・デジタルアーカイブ
Ⅷ-2-2.個別学習の自動化レベル1:教師補助
Ⅷ-2-3.個別学習の自動化レベル2:部分的自動化
Ⅷ-2-4.個別学習の自動化レベル3:条件付き自動化
Ⅷ-2-5.個別学習の自動化レベル4:高度自動化
Ⅷ-2-6.個別学習の自動化レベル5:完全自動化
Ⅷ-2-7.学びのデザインと教育リソース・デジタルアーカイブ
3.課 題
① 個別学習の自動化におけるレベル分類と、各段階での教師の役割はどう変化しますか。
② 個別学習の自動化を構成する三つの基本要素を説明せよ。
③ 学習状況の検出に用いられる計測データの種類を挙げよ。
④ 教育リソース・デジタルアーカイブが果たす役割を述べよ。
4.プレゼン資料
5.動画資料
6.テキスト
第9講 教育リソース・デジタルアーカイブとデジタル教育文化
久世均(岐阜女子大学・教授)
1.何を学ぶか
教育リソース・デジタルアーカイブを教育のデジタル化における重要な基盤と位置づけ、その構築と活用のあり方を多角的に考察しています。学習者の状況を把握する検出・診断機能や、教師の授業準備を支える情報提供の仕組みについて、過去の教育工学の研究や最新のAI技術を踏まえて解説しています。また、単なるデータの蓄積に留まらず、編集や加工を通じて新しい価値を生む**「デジタル文化創造」という概念を提唱し、著作権処理の重要性にも触れています。全国的な教育統合ポータル**の整備を提言し、個別の学習状況に最適化された教材提供が可能なシステムの必要性を説いています。最終的に、生成AIやメタバースといった新技術との融合により、主体的な学びを支える教育環境の実現を目指す展望を示しています。
2.内容
Ⅸ-1.学習テクノロジーの機能をもつ情報端末
Ⅸ-1-1.学習状況の検出の機能
Ⅸ-1-2.診断
Ⅸ-1-3.教師への情報提供(ダッシュボード等)
Ⅸ-1-4.教育リソース・デジタルアーカイブの利用
Ⅸ-2.教育リソース・デジタルアーカイブと情報の利用
Ⅸ-2-1.指導案の作成 …データとしての利用
Ⅸ-2-2.課題解決の資料として …情報として
Ⅸ-2-3.知識としての資料の利用
Ⅸ-2-4.知恵を働かせる …知恵・wisdom
Ⅸ-3.新しいデジタル教育文化の創造に向けて
Ⅸ-3-1.権利処理の重要性
Ⅸ-3-2.情報(資料)の保管・流通
Ⅸ-3-3.デジタルアーカイブとデジタル文化
Ⅸ-3-4.「受け手の情報」に対応した「情報の提供」
Ⅸ-3-5.記録するメディアと利用するメディア
Ⅸ-4.教育リソースデジタルアーカイブ(DA)の課題
Ⅸ-4-1.木田宏オーラルヒストリーから教育リソースの活用を考える
Ⅸ-4-2.新しい学びを支える教育リソースの設置
Ⅸ-4-3.カリキュラムは学校が作る。その支援をするのが、教育委員会指導主事。
Ⅸ-4-4.国立が教育総合ポータルを管理すべきかの課題
Ⅸ-4-5.学びの展開を支援する教育統合ポータル
3.課 題
① デジタルアーカイブは教育の質的向上や教師の働き方改革にどう貢献するか。
② OECDが提唱する学習状況の検出における3つの分類は何か。
③ OECD報告書による学習プログラム構成の三つの分類を答えよ。
④ デジタル文化創造において、特に再検討が必要な権利処理は何か。
4.プレゼン資料
5.動画資料
6.テキスト
第10講 セカンドGIGAへの展望と課題
堀田龍也氏(東京学芸大学大学院教育学研究科・教授)
1.動画資料
2.資 料
3.内 容
1. GIGAスクール構想の現状と進展
GIGAスクール構想は、2020年のスタート以来、小中学校の児童生徒に1人1台の情報端末を配備し、授業改善を進めてきました。特に2022年度以降は多くの地域で本格的な活用が始まり、当初は「とにかく使ってみる」段階でしたが、現在は教科の学習と並行して、児童生徒一人ひとりが自分のペースで納得して学べるような授業改善へと移行しています。
1.1. 授業風景の変化
• 個別最適化された学びと協働学習: 児童生徒が教科書を読み込み、端末で情報をまとめ、クラウド上で共有することで、互いの進捗を確認し、助け合いながら学習する場面が増えています。教師は個々の進捗や努力に合わせて助言や指導を行います。
• 「学びに価値を感じる」ことの重要性: 当初はふざけてしまう児童生徒もいますが、学びに価値を感じ始めると、自分のペースで学べ、困ったときに教師だけでなく友達にも聞けるため、主体的に学びに向かう態度が育まれます。
• 体験とデジタルの融合: 理科の実験では、体験の重要性を前提としつつ、実験の経過を動画で撮影するなど、デジタルを活用して学びを深める事例が増えています。デジタルはリアルな学びを支えるツールとして機能しています。
• デジタルだからこそ可能な学び: 小学1年生がゴミ収集車の仕組みを学ぶ際に、写真を拡大して観察するなど、デジタルデバイスだからこそ可能になる詳細な観察や情報整理が行われています。
• 情報取り出しスキルの重要性: 児童生徒が自分のペースで学ぶには、教科書などの情報から必要な情報を自力で取り出すスキル(情報取り出し)が不可欠であり、義務教育段階でその訓練を積むことの重要性が強調されています。
• デジタル教科書の活用: 中学校の英語デジタル教科書では、ネイティブ音声でリスニング練習を繰り返せるため、児童生徒が自分のペースで反復学習を行うことが可能になります。小学校の算数デジタル教科書では、平行四辺形の面積を求める際に、図形を「切ったり動かしたり」して視覚的に理解を深めることができます。
1.2. アウトプットと学びの深化
• スライドによる共同編集: 児童生徒がスライドで学習内容をまとめる際、クラウド上で共同編集することで、他の児童生徒のまとめ方を参考にしたり、自分のまとめ方を多様化させたりすることができます。
• 進捗の可視化と相互支援: 個々の児童生徒の学習進捗を一覧で共有することで、「一人ですらすら」進める子から「一人でできた次も人に聞くんじゃないか」と自信がない子まで、それぞれの状況に合わせて助け合う文化が生まれています。
• 教え合いによる学びの深化: 早く進む児童生徒が、わからない友達のために説明動画を作成するなどの活動は、クラスへの貢献だけでなく、問題の本質をより深く理解することにつながり、高度な学びを促します。
• 「自分の学びは自分で責任を持つ」主体性の醸成: 堀田先生は、「分からないことは調べる」「他の人に聞く」「自分でできるようにする」といった、自分の学びに対する責任を持つ姿勢が主体性を育むと強調しています。
• 個別指導の質の向上: 自律的に学ぶ児童生徒が増えることで、教師は発達に障害のある子や心の弱い子、外国人児童生徒など、より手厚い支援が必要な児童生徒に時間を割くことができるようになります。
• 学習権の保障: 端末の持ち帰りやクラウドでの情報共有が日常的になることで、不登校や体調不良などで学校に来られない児童生徒もオンラインで学習に参加し、学習機会が保障されます。
• 心理的安全性と多様な学び方: 児童生徒が一人で学ぶだけでなく、友達と協力して学ぶことも増えています。教室内の心理的安全性が確保されることで、児童生徒は安心して学びに取り組めます。また、自分の考えが似ている人との確認や、異なる意見の人との意見交換など、状況に応じて多様な学び方を選択できるようになることが推奨されています。
1.3. 教師の役割と学級経営
• 振り返りの重要性: 学習内容だけでなく、自分の学び方(うまくいった点や改善点)を振り返る活動を区別して行うことで、より深い学びにつながります。
• 「教える」ことの継続: 児童生徒に任せる場面が増えても、教師が分かりやすく説明したり、明確な指示を出したりする場面は依然として重要です。実物投影機などを活用した丁寧な説明は、デジタル化が進んでも変わらず必要とされます。
• 学習規律と学級経営: 児童生徒が安心して学べる環境を提供するために、教師の学級経営の力量が試されます。清掃活動や机の整頓など、集団で学ぶ上での基本的な規律は引き続き重要です。
• 基礎的学力の定着: ドリル学習など、基本的な学びを疎かにすることなく、デジタルの利点を活かしながらも基礎を大切にする姿勢が重要です。
• タイピングスキルの必要性: 情報活用能力の基礎として、キーボード入力(タッチタイピング)の習得が非常に重要であり、児童生徒にしっかりと身につけさせるべきだと強調されています。
1.4. ICT活用の効果と学力
• Jカーブ効果: ICT活用は、導入当初は慣れないために効果が見えにくいものの(Jカーブ)、慣れてくると子どもの変化や教師の授業デザインの変化によって、劇的に効果が向上するという研究結果が紹介されました。
• 学力向上への寄与: GIGAスクール構想によって進められた「主体的・対話的で深い学び」に取り組んでいる学校では、全国平均や県の平均と比較して学力が高い傾向にあり、特に「思考・判断・表現」の能力が大きく伸びています。
• 知識・技能と思考・判断・表現のバランス: 基礎的な知識・技能はもちろん重要ですが、それを踏まえた上で、自分の力で考え、他者とコミュニケーションを取りながら学ぶ力を育むことが大切です。
2. 学力に関する誤解とCBT化の動向
2.1. 学力評価の多層性と注意点
• 学力の多層性: 「学力が上がった/下がった」と一括りにするのではなく、どの学習内容や活動が重要だったのか、どの児童生徒に合っているのかなどを、より詳細に分析する必要があります。
• 他校との比較の難しさ: 全国学力・学習状況調査の結果を単純に比較することの限界が指摘されています。問題も異なり、点数のわずかな差で優劣を判断するのは適切ではありません。
• 基礎学力と応用的な学び: 基礎的な学力が高度な学びを支えるのは当然であり、ICT活用は基礎的な学力を効率的に習得させ、より高度な学びに時間を割くためのものです。
• デジタルと紙の二項対立の超越: 「紙の方が良い」という意見は、紙で学んできた世代の前提に立っており、デジタルに慣れ親しんだ現代の児童生徒にとっては当てはまらない可能性があります。デジタル批判にはビジネス的な背景もあるため、冷静な判断が求められます。
• 「学ぶ力」「学ぶ意欲」の重要性: 学力は、学んだ結果身についた力だけでなく、「学ぶ力」や「学ぶ意欲」、学ぶスキルも含まれます。生涯にわたって学び続ける現代において、後者を育むことが非常に重要です。
2.2. CBT化の進展と準備の必要性
• 全国学力・学習状況調査のCBT化: 全国学力・学習状況調査がCBT(Computer Based Testing)に移行することが公表されています。2025年度の中学校理科から始まり、2027年度には小学校の国語・算数、中学校の国語・数学もCBT化されます。
• CBT化への準備: 各教育委員会は十分なネットワーク速度を担保し、学校はCBT経験を積む必要があります。文部科学省が提供するCBTプラットフォームの活用や、動画を用いた出題形式、マウス操作による回答など、従来の紙のテストとは異なる形式への慣れが求められます。
• 個別最適化された評価: CBT化により、児童生徒それぞれの理解度や進捗に合わせて問題を変えることが可能になり、採点や集計も迅速に行われるため、より早いフィードバックが可能になります。
3. 次期学習指導要領に向けた議論の方向性
2024年12月25日、文部科学大臣から中央教育審議会に対し、次期学習指導要領(2030年全面実施予定)に関する諮問が出されました。
3.1. デジタル化の課題意識と基本的な考え方
• 日本のデジタル化の遅れ: デジタル化における課題として、日本の現状の遅れや、実体験における格差、デジタル化の負の側面(依存、いじめなど)が挙げられています。
• デジタルとリアルの融合: 今後は「デジタルかリアルか」「デジタルか紙か」といった二項対立ではなく、デジタルの力でリアルな学びを支えるという基本的な考え方が示されています。バランス感覚を持って、最適な組み合わせを積極的に考えていくことが求められています。
3.2. 審議すべき内容のポイント(デジタル関連)
• 生成AIの影響と学習内容の問い直し: 生成AIの急速な発展は、学校で学ぶべき内容そのものを問い直すきっかけとなります。検索すれば分かるような知識の詰め込みではなく、教科の本質的な見方・考え方や、より大局的な学びが重要になります。
• 情報活用能力の抜本的向上: 情報社会において、情報活用能力(情報をうまく取り扱う能力、端末を使いこなす能力)の抜本的な向上が求められています。小学校からの教科としての情報教育や、現在の技術家庭科、高等学校の情報科のあり方を含め、カリキュラム全体の改善の中で検討されます。
• 教科書のあり方の検討: 教科書が分厚く、教師の負担となっている現状を踏まえ、今後の教科書の内容や分量、デジタル化の範囲などが検討されます。児童生徒が自立して学ぶことを前提とした教科書のあり方が模索されます。
• デジタル学習基盤を前提とした学び: 端末やネットワーク、クラウドといったデジタル学習基盤を前提に、児童生徒が自分で学びを自己調整し、教材や方法を選択できるような指導計画や学習環境をどう構築していくかが議論されます。当然ながら、その中での教師の指導性のあり方も重要な論点となります。(文責:久世)
第11講 デジタルアーカイブと知的財産権
吉川 晃(岐阜女子大学)
1.目 的
デジタルアーキビストとして、アーカイブを計画し、そして資料収集し、そして構築し、そして利用許諾し、また運用していくという、こういったときに必要な権利処理について説明する。
2.学習到達目標
① デジタルアーキビストに著作権処理の能力が必要であることについて具体的に説明ができる。
② 著作者の権利について具体的に説明できる。
③ 著作権の契約書を作成できる。
3.課 題
① デジタルアーキビストに著作権処理の能力が必要であることについて具体的に説明しなさい。
② 著作者の権利について具体的に説明しなさい。
③ 著作権の契約書を作成しなさい。
4.プレゼン資料
5.動画資料
6.内容
1. デジタルアーキビストと権利処理
デジタルアーキビストは、アーカイブの計画、資料収集、構築、利用許諾、運用といった一連のプロセスにおいて、権利処理に関する正確な知識を持つことが不可欠です。権利処理の基本となるのは著作権ですが、それに加えて肖像権や個人情報保護、さらには法律ではない慣習への配慮も求められます。
この分野の学習に最も重要な情報源は、文化庁の著作権テキストです。これは毎年更新される無料の教材であり、常に最新の知識を得るための基本資料となります。また、肖像権や個人情報保護に関しては、関連学会や委員会のハンドブックなども参考になります。
2. 著作権の基礎
(1) 著作権の構成と特徴
著作権法には、著作者の権利と著作隣接権の2つの権利が存在します。
著作者の権利:著作物(文芸、学術、美術、音楽など)を創作した人に認められる権利です。
著作隣接権:著作物を伝達する役割を担う人に認められる権利です。具体的には、実演家、放送事業者、有線放送事業者、レコード製作者の4者です。
著作権にはいくつかの重要な特徴があります。
無方式主義:著作権は、登録などの特別な手続き(方式)を踏まなくても、創作した時点で自動的に発生します。このため、プロ・アマ問わず、著作物を創作した人は権利者となります。一方で、誰が権利者であるかを特定しにくいという側面もあります。
人格権と財産権:著作者の権利は、人格権と財産権に分かれています。
人格権:著作者の人格的な利益を保護する権利で、譲渡はできません。
財産権:著作物を利用する人から金銭的な対価を受け取る権利で、譲渡が可能です。
保護期間:原則として、著作者の死後70年間保護されます。正確には、著作者が亡くなった年の翌年1月1日から起算して70年間です。人格権は著作者の生存期間中に保護されますが、死後も著作者の名誉や声望を害するような侵害行為は禁止されています。
国際条約:日本の著作権法は、ベルヌ条約(著作権)やローマ条約(隣接権)といった国際条約に基づいて制定されています。国内法を改正する際にも、これらの条約を遵守する義務があります。
(2) 著作物と著作者
著作物:法律上、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されます。ここで重要なのは、アイデアそのものではなく、そのアイデアを表現した形が保護されるという点です。また、創作的とは「ありきたりではないこと」を指します。
著作者:著作物を創作した人です。ゴーストライターが執筆した場合、法律上はゴーストライターが著作者となりますが、契約によってその権利を依頼主に譲渡しているケースが多いです。
二次的著作物:翻訳、編曲、映画化など、既存の著作物を改変して創作された著作物です。元の著作物とは別に、二次的著作物として独立して保護されます。
編集著作物:複数の著作物や素材を編集し、全体として創作性を持つ著作物です。新聞、雑誌、事典などが該当します。デジタルアーカイブもこれに該当するケースが多いため、理解しておく必要があります。
法人著作:法人が著作者となることも可能です。その場合、以下の条件をすべて満たす必要があります。
法人の企画に基づき、その法人の業務に従事する者が職務上創作すること。
法人名義で公表されること。
就業規則等に、職員を著作者とする定めがないこと。
(3) 著作者の権利
著作者の権利は、人格権と財産権に分けられます。
人格権:
公表権:著作物を公表するかどうかを決める権利。
氏名表示権:著作者の名前を表示するかどうか、またはどのような名前(本名、ペンネームなど)を表示するかを決める権利。
同一性保持権:著作物の内容や題号を、著作者の意に反して無断で改変されない権利。デジタルアーカイブの作成において、特に注意が必要です。
財産権:多様な権利がありますが、特に重要なのは以下の2つです。
複製権:著作物を無断で複製されない権利。
公衆送信権:著作物を無断で公衆(不特定多数、または特定多数の人々)に送信されない権利。インターネット上へのアップロードや、ダウンロード可能な状態にすることも含まれます。
(4) 著作権の例外規定とライセンス
著作権は文化の振興を目的として保護されていますが、権利が強すぎるとかえって文化の発展を阻害する可能性があります。そのため、例外的に著作権者の許諾なく利用できる場合が、法律で列挙されています。
私的使用のための複製:個人的、家庭内など、限られた範囲内で使用するための複製は認められています。ただし、仕事目的や、コピーしたものを他人に頒布する行為は認められません。
授業目的公衆送信補償金制度(SARTRAS):オンライン授業などで著作物を利用する場合、補償金を支払うことで、個別の許諾なしに利用できる制度です。学校などがSARTRASという団体と契約し、まとめて補償金を支払うことで、円滑な教育活動を可能にしています。
写り込み:写真や動画の撮影時に、背景や被写体の一部として著作物が写り込んでしまう場合、それが主たる被写体ではなく、分離することが困難な場合は、著作権侵害とはなりません。
引用:他人の著作物を自分の著作物の中で利用する場合、以下の条件を満たせば引用として認められます。
引用部分が明瞭に区別されていること(例:かぎ括弧でくくる)。
自分の著作物が主、引用部分が従という主従関係が保たれていること。
公表された著作物であること。
公正な慣行に従い、目的上正当な範囲内で行うこと。
出典を明示すること。
著作者の意に反する改変をしないこと。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス):著作権者自身が、一定の条件下で著作物の自由な利用を許諾する意思表示を行う仕組みです。このライセンスが付与されたコンテンツは、その範囲内であれば許諾なく利用することができます。
3. デジタルアーカイブの実務と注意点
(1) 著作隣接権
著作隣接権は、著作物を伝達する役割を担う人々を保護する権利です。
実演家:俳優やダンサー、演奏家など、著作物を演じたり歌ったりする人。実演家人格権(氏名表示権、同一性保持権など)があり、名誉や声望を害するような改変は禁じられています。アーカイブの対象が動画や音声である場合、特に注意が必要です。
レコード製作者:音を最初に固定した原盤を制作した人(レコード会社など)。
放送事業者、有線放送事業者:放送事業関係者。
隣接権の理解は、アーカイブ化する資料がこれらの権利とどのように関わるかを判断するために不可欠です。
(2) 契約書の作成
デジタルアーカイブの構築にあたり、著作権者から権利を譲り受ける(著作権譲渡)実務が必要になる場合があります。
財産権の譲渡:財産権は譲渡が可能ですが、すべての権利を譲渡してもらうには、著作権法第27条(二次的著作物創作権)および第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)の権利も譲渡されることを、契約書に明記する必要があります。
人格権の扱い:人格権は譲渡できません。そのため、アーカイブの運用上、著作物の改変が必要な場合は、事前に内容を確認する機会を設けたり、「著作者人格権を行使しない」という特約を結んだりすることで、円滑な運用を図ります。
文化庁のウェブサイトには、著作権契約書作成支援システムがあり、契約書作成の参考になります。
(3) 肖像権
肖像権は、法律で明文化された権利ではなく、判例で認められた権利です。人は、みだりに自分の姿を撮影されたり、公開されたりしない権利を持っています。
違法性の判断:撮影や公開が、その人の人格的利益の侵害が「社会生活上の受忍限度を超える」場合に違法とされます。
ガイドラインの活用:写真などをアーカイブ化する際には、原則として本人の許諾を得ることが望ましいです。許諾が得られない場合の判断基準として、デジタルアーカイブ学会のガイドラインなどが参考になります。
(4) 慣習への配慮
著作権や肖像権といった法律上の権利だけでなく、慣習への配慮もデジタルアーキビストの重要な役割です。
慣習とは:地域社会が大切にしている神聖な場所や儀式など、法律ではないものの、その尊重を怠るとコミュニティの信頼を失いかねない事柄です。
アーカイブ化における注意点:神聖な場所への立ち入りや、儀式の無断撮影などは、地域の方々との関係を損なうだけでなく、場合によっては法的紛争に発展する可能性もあります。
デジタルアーキビストの役割:アーカイブ化を進める際には、地域の人々と丁寧に交渉し、適切なやり方で協力を得るための橋渡し役を担う必要があります。
まとめ
デジタルアーキビストには、著作権、著作隣接権、肖像権、個人情報保護といった多岐にわたる権利処理に関する正確な知識が求められます。特に、著作権の基礎となる人格権と財産権、そして保護期間や例外規定の理解は不可欠です。また、実務においては、契約書の適切な作成や、地域の慣習への配慮が円滑なアーカイブ運営には欠かせません。常に最新の情報源を参照し、正確な知識に基づいて実務を行うことが、デジタルアーキビストとしての行動規範となります。
Ⅳ レポート課題
Ⅴ アドバイス
Ⅵ 科目修得試験:定期試験
Ⅶ テキスト
Ⅷ 参考文献
1)岩田晃(1968)、ティーチングアナライザーを用いた授業、TM研究第1 報
2)後藤忠彦(1968)、ティーチングマシンのシステム、TM研究第1報
3)後藤忠彦、森幸雄、成瀬正行(1970)、集団反応曲線分析の手法について(1)、学習システム研究会No.1
4)成瀬正行、後藤忠彦(1970)、磁気テープの方法によるRA反応の記録報、電子通信学会ET70
5)Flanders.N.A.(1970)、And going Teaching behavior, Addism – Wesleg
6)(Observational System for Instructional Analysis): Hough J.B and Duncan J.K (1970) Teaching: description and analysis. Boading. Mass Addison–Wesley
7)Cruickshank,D.R(1974)`The protocol materials movement :On exemplar of efforts to Web Theory and practice in teacher education.’ Journal of Teacher Education, 25, 4 (Winter, 1974) 300-ll
8)Bloom, B. S., Madaus, G. F., & Hastings, J. T. (1971). Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York McGraw-Hill.
9)広瀬弘、森幸雄、後藤忠彦、成瀬正行(1972)、CMIシステムについて、岐阜大学教育学部研究報告Vol.5 No.1
10)OECD国際学会(1975)、カリキュラム開発に関する報告、文部省
11)大塚明朗(1976)、新しい教育工学の展開、第一法規
12)招野和夫(1976)、授業の計画入門、国士社
13)成瀬正行、後藤忠彦(1977)、反応装置による教授項目の系列化、日本教育工学誌Vol.2 No.4
14)坂元昂(1977)、CAI学習プログラムの評価、機械振興協会
15)後藤忠彦、成瀬正行、樋田陽子、磯野紀代(1978)、小学校用CMIシステム(1)、電子通信学会教技ET-78-5
16)後藤忠彦(1980)、SIS-TEMⅢ – A Computer – Based Educational System, Edus, Technol , Res. 4-1,2
17)後藤忠彦(1986)、コンピュータと教育情報システム、東京書籍
18)OECD(2021)、OECD Digital Education Outlook 2021 pushing the formtiers with AI, blockchain and Robots.(濱口久美子訳(2022)、OECD教育白書、明石書店
19)Burns. T. and F. Gottschalk(eds)(2012)、西村美由起訳(2022)感情的ウェルビーイング-21世紀デジタルエイジの子どもたちのために、明石書店
20)眞喜志悦子、長尾順子、宮城卓司、井口憲治(2023)
21)齋藤陽子(2023)、教育リソースの発展と利活用Ⅰ、遠隔教育振興会
22)櫟彩見、齋藤陽子、林知代(2023)、教育リソースの発展と利活用Ⅱ、遠隔教育振興会
23)齋藤陽子、横山隆光(2024)、学習の理解度・積極的参加を求めて、一遠隔教育振興会
24)加藤真由美(2024)、「沖縄おぅらい」デジタルアーカイブ、遠隔教育振興会
25)後藤忠彦、久世均、横山隆光、齋藤陽子、又吉斎(2025)、個別学習の自動化の課題Ⅰ、一般社団法人遠隔教育振興会
Ⅷ 資料
※ AI動画並びにAIプレゼンは、テキストを で分析し生成したものです。