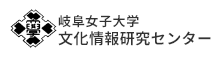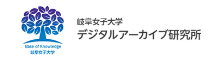【授業】教育開発とメタバース
【授業】教育開発とメタバース
Ⅰ はじめに
メタバースを活用した教材開発は、没入型の疑似体験を可能にし、言語や文化体験の学習に適した環境を提供している。AIとの連携により個別最適化が進み、学習者ごとの習熟度に応じた教材がメタバースでも提供される。また、VRやAR技術の発展に伴い、よりリアルな歴史・科学体験が可能になり、グローバルな教育連携が加速し、多言語対応やインタラクティブな学習空間の拡充が進展する。
Ⅱ 授業の目的・ねらい
教材開発の意味とメタバースの活用、AIとの連携による個別最適化などについて理解し、メタバースやAIを利用した教材を開発することができる。
Ⅲ 授業の教育目標
第1講~第15講の各研修目標に基づいて、テキストと動画教材を利用して教材開発とメタバースやAIの活用ついて理解し、各講の課題に取り組むことで、教材開発のスキルの習得を図る。
第1講 教材開発
1.何を学ぶか
教材の意味、教材開発のプロセスについて学ぶ。
2.学修到達目標
・教材の重要性が理解できる。
・教材開発のプロセスを説明できる。
3.課題
① 教材の重要性について説明しなさい。
② 教材開発のプロセスについて整理しなさい。
4.プレゼン資料
5.映像資料
6.資料
第2講 学習者のニーズ
1.何を学ぶか
学習者のニーズを具体的な学習目標に結びつけること、教育現場で直面する課題に対応して教育の質を向上させることについて学ぶ。
2.学修到達目標
・学習者のニーズについて理解することができる。
・ニーズと学習目標について説明することができる。
3.課題
① 学習者のニーズについて整理しなさい。
② ニーズと学習目標についてまとめなさい。
4.プレゼン資料
5.映像資料
6.資料
第3講 学習目標と行動目標
1.何を学ぶか
学習目標と行動目標は、教育の質を高めるための不可欠な要素であり、教材開発において、これらの目標を明確に設定し、効果的に連携させることについて学ぶ。
2.学修到達目標
・学習目標と行動目標について理解することができる。
・学習目標および行動目標と教材開発について説明することができる。
3.研究課題
① 学習目標と行動目標について整理しなさい。
② 学習目標および行動目標と教材開発の関係について整理しなさい。
4.プレゼン資料
5.映像資料
6.資料
第4講 教材の構成
1.何を学ぶか
教材開発においては、学習者のニーズなどの要素を総合的に考慮し、学習目標、学習内容、学習者の特性、利用可能なリソースなどを踏まえた上で、最適な教材構成を設計することについて学ぶ。
2.学修到達目標
・教材開発の観点から見た教材の構成について理解することができる。
・教材の設計手法について説明することができる。
3.課題
① 教材開発の観点から見た教材の構成について説明しなさい。
② 教材の設計手法について整理しなさい。
4.プレゼン資料
5.映像資料
6.資料
第5講 マルチメディア教材
1.何を学ぶか
マルチメディア教材は、多様なメディア、メタバース、AIを組み合わせることで、実生活に即したシミュレーション、インタラクティブな要素、個別化学習などを実現できることについて学ぶ。
2.学修到達目標
・マルチメディア教材を構成する主要な要素とその特徴について理解することができる。
・AIと学習データを活用したアダプティブ教材について説明することができる。
3.研究課題
① マルチメディア教材を構成する主要な要素とその特徴について整理しなさい。
② AIと学習データを活用したアダプティブ教材について説明しなさい。
4.プレゼン資料
5.映像資料
6.資料
第6講 メタバースの活用
1.何を学ぶか
メタバースの最も魅力的な特徴の一つは仮想空間が提供する没入感であり、これらの特徴を活用した教材開発について学ぶ。
2.学修到達目標
・教材開発とメタバースの関係について理解できる。
・メタバースの歴史について理解できる。
3.課題
① 教材開発とメタバースの関係について説明しなさい。
② メタバースの歴史について整理しなさい。
4.プレゼン資料
5.映像資料
6.資料
第7講 バーチャルスクール
1.何を学ぶか
バーチャルスクールの概要、および、メタリット・デメリットについて学ぶ。
2.学修到達目標
・バーチャルスクールの概要を理解することができる。
・バーチャルスクールのメタリット・デメリットについて説明することができる。
3.課題
① バーチャルスクールの概要について説明しなさい。
② バーチャルスクールのメタリット・デメリットについて整理しなさい。
4.プレゼン資料
5.映像資料
6.資料
第8講 個別最適化された学習の可能性
1.何を学ぶか
地理的環境条件の異なる小学校の5年生を対象とした遠隔協働学習において、「指導の個別化」と「学習の個性化」を仮想的な環境で実現できる可能性について学ぶ。
2.学修到達目標
・個別最適化と協働学習について理解することができる。
・メタバースでの遠隔協働学習について説明することができる。
3.課題
① 個別最適化と協働学習について整理しなさい。
② メタバースでの遠隔協働学習について説明しなさい。
4.プレゼン資料
5.映像資料
6.資料
第9講 表現力の育成
1.何を学ぶか
現実世界では周囲の視線や評価を過度に意識して発言することをためらう子供でも、自分の姿を晒すことなくアバターを通して、臆することなく自身の意見を表明したり、物語の登場人物になりきって感情豊かに演じたりすることが可能になることが表現力の育成につながることについて学ぶ。
2.学修到達目標
・メタバースが表現力を高める可能性を理解することができる。
・メタバース授業の概要について説明することができる。
3.課題
① メタバースが表現力を高める可能性について説明しなさい。
② メタバース授業の概要について説明しなさい。
4.プレゼン資料
5.映像資料
6.資料
第10講 地域学習
1.何を学ぶか
地理的な制約や天候に左右されることなく、いつでも史跡の疑似体験が可能となる仮想空間「沖縄の学習・観光の部屋」を利用した学習について学ぶ。
2.学修到達目標
・文化遺産学習とメタバースの利用について理解することができる。
・メタバースを利用した授業例について説明することができる。
3.課題
① 文化遺産学習とメタバースの利用について説明しなさい。
② メタバースを利用した授業例を考えなさい。
4.プレゼン資料
5.映像資料
6.資料
第11講 プロジェクト型学習
1.何を学ぶか
下呂温泉メタバースを利用した教育DXと観光DXの学習の概要について学ぶ。
2.学修到達目標
・高等教育における教育DXと観光DXの学習の概要を理解することができる。
・メタバースにおける観光情報提供の仕組みの概要を理解することができる。
3.課題
① 高等教育における下呂温泉メタバースを利用した教育DXと観光DXの学習の概要を整理しなさい。
② 下呂温泉メタバースにおける観光情報提供の仕組み整理しなさい。
4.プレゼン資料
5.映像資料
6.資料
第12講 海洋教育
1.何を学ぶか
特別支援教育における仮想空間「海洋教育の部屋」の活用について学ぶ。
2.学修到達目標
・「海洋教育の部屋」の設計の概要を理解することができる。
・「海洋教育の部屋」の活用方法について説明することができる。
3.課題
① 「海洋教育の部屋」の設計の概要を整理しなさい。
② 「海洋教育の部屋」の活用方法について説明しなさい。
4.プレゼン資料
5.映像資料
6.資料
第13講 日本語教育
1.何を学ぶか
日本語教育におけるメタバースを利用した民話を素材とする多言語教材の活用について学ぶ。
2.学修到達目標
・日本語指導の現状と課題について理解することができる。
・日本語教育用教材開発の意図と工夫について説明することができる。
3.研究課題
① 日本語指導の現状と課題について説明しなさい。
② 日本語教育用教材開発の意図と工夫について整理しなさい。
4.プレゼン資料
5.映像資料
6.資料
第14講 メタバース開発
1.何を学ぶか
メタバースプラットフォーム、および、メタバース制作の工程について学ぶ。
2.学修到達目標
・メタバースプラットフォームについて理解することができる。
・メタバース制作の工程について理解することができる。
3.課題
① メタバースプラットフォームについて説明しなさい。
② メタバース制作の工程について整理しなさい。
4.プレゼン資料
5.映像資料
6.資料
第15講 3Dモデリングとモーションキャプチャー
1.何を学ぶか
モーションキャプチャー、および、モーションキャプチャーについて学ぶ。
2.学修到達目標
・3Dモデリングについて理解することができる。
・モーションキャプチャーについて理解することができる。
3.課題
① 3Dモデリングについて説明することができる。
② モーションキャプチャーについて説明することができる。
4.プレゼン資料
5.映像資料
6.資料
Ⅳ レポート課題
課題 メタバースやAIを活用した教材開発について1200文字以内で記述しなさい。
Ⅴ アドバイス
課題解説 メタバースとAIを活用した教材開発は、学習の質を向上させる革新的な手法です。メタバースでは没入型学習が可能で、仮想空間内で歴史や科学を体験でき、多言語対応による国際教育の場としても活用されています。AIの導入により、個別最適化された学習が実現し、学習者の習熟度に応じた教材の提供が可能になります。また、生成AIによる教材作成や自動翻訳により、教育のアクセシビリティが向上。今後、メタバースとAIを組み合わせることで、教育のインタラクティブ性が高まり、協働学習の新たな可能性が広がるでしょう。これらの技術の活用法や課題について整理し、論述するとよいでしょう。
Ⅵ 科目修得試験:定期試験
Ⅶ テキスト
Ⅷ 参考文献
①メタバース進化論――仮想現実の荒野に芽吹く「解放」と「創造」の新世界(バーチャル美少女ねむ)
②世界2.0 メタバースの歩き方と創り方(佐藤航陽)
③メタバース未来戦略(久保田瞬・石村尚也)
④メタバースの教科書(雨宮智浩)
⑤ザ・メタバース 世界を創り変えしもの(マシュー・ボール)
⑥授業と教材 教材の正しい理解と活用のために 一般社団法人日本図書教材協会 授業と教材に関する調査研究委員会
⑦教材学概論 日本教材学会編
Ⅷ 資料