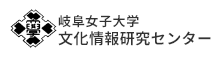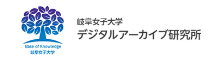【授業】英語学概論
Ⅰ はじめに
本科目で学ぶことで、英語学における基礎的な概念を理解して、今後に応用的な力を付けるための土台とすることである。これにより、語彙、文法、音声などの各分野の土台を知ることで、英語の読み、書き、話し、聞くという4技能の鍛錬につながるようにしたい。
Ⅱ 授業の目的・ねらい
英語学は多岐にわたる分野であり、様々に細かく分類される。概念を知ることは大切であるが、将来方向として、その応用的な力、実践的な力が身につくようにしたい。それにより、大学卒業後に、英語が得意科目として、社会で活躍できることが狙いである。
Ⅲ 授業の教育目標
英語学概論を学ぶことで、将来に英語を教えようとする学生に、英語学教育法と同様に、基礎的な力を与えることである。小中学校レベルの英語が教えられるように、その段階の生徒達から出される質問などに容易に答えられるように英語力を付けたい。
テーマ1 言語の起源と語族
1 何を学ぶか
① 言語起源論のいくつかを考察する。
② 語族の定義を調べる。
③ インド・ヨーロッパ語族の中の英語の位置づけを考える。
2 学習到達目標
① 人間がことばを使えることの意味を説明できる。
② 人類の言語能力の発達の歴史を説明できる。
③ 英語と親族関係にある言語を説明できる。
3 課題
① ゲルマン諸語と英語の関係を調べてまとめる。
② 孤立言語とは何かまとめる。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ2 人間のことばと言語研究
1 何を学ぶか
① ことばの気まま性(arbitrariness)について考察する。
② ことばの二重性、抽象性、規則性について学ぶ。
③ 言語学の各分野、音声学、音韻論、統語論などの概要を理解する。
2 学習到達目標
① 言語学という学問について説明できる。
② 人間のことばの特徴を説明できる。
③ ことばを分析するときの資料の集めかたを説明できる。
3 課題
① ネット上のコーパスを利用して、いくつかの単語の特徴を調べる。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ3 アルファベット
1 何を学ぶか
① ギリシア文字、キリル文字など類似のアルファベットについて考察する。
② 筆記体について理解する。
2 学習到達目標
① アルファベットの起源について説明できる。
② ローマ字(内閣式とヘボン式)の違いについて説明できる。
3 課題
① 自分の名前を筆記体で書けるようになり、サインできるようにする。
② 文字と印刷術の歴史について調べる。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ4 ことばの変化
1 何を学ぶか
① 通時態と共時態の違いを理解する。
② 英語に文法上の性がない事情を理解する。
③ 英語の変化と社会の動きとの関連を理解する。
2 学習到達目標
① 英語の歴史について簡単な説明ができる。
② ことばの変化の理由について説明できる。
③ 発音、語彙、文法の相互関係について説明できる。
3 課題
① 5つほど英単語を選び、その歴史的な変遷を調べる。
② be動詞の歴史的な推移を調べる。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ5 単語とスペリング
1 何を学ぶか
① ローマン・アルファベットと正書法の関係について調べる。
② 大母音推移について理解する。
③ 英語の母音推移、弱母音化について調べる。
2 学習到達目標
① 英語のスペルと発音のずれについて説明できる。
② 英米英語で異なるスペルや発音を説明できる。
3 課題
① 英米英語で書記法の異なる単語をできるだけたくさん集める。
② 黙字がある英単語を集める。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ6 標準英語の成立
1 何を学ぶか
① アメリカにおける標準語の成立について調べる。
② イギリスにおける標準語の成立について調べる。
③ 世界における共通語の意味について調べる。
2 学習到達目標
① 英語の標準語の成立の経緯を説明できる。
② 共通語の意義について説明できる。
③ RPとGAについて説明できる。
3 課題
① 映画My Fair Lady を鑑賞して、英語の方言と社会階層との関係を理解する。
② 英語の中に取り入れられた日本語について調べる。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ7 単語ができる仕組み
1 何を学ぶか
① 形態素から単語へと構成されていく過程を理解する。
② 自由形態素と拘束形態素の違いについて調べる。
③ 転換、逆成などの語彙の誕生について理解する。
2 学習到達目標
① 単語の意味の恣意性について説明できる。
② 形態論と形態素の関係について説明できる。
③ 接頭辞と接尾辞の構造について説明できる。
3 課題
① いくつかの単語の語形成プロセスについて調べる。
② 複合語の主要部について調べる。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ8 言葉と音声
1 何を学ぶか
① 閉鎖音、摩擦音、破擦音、鼻音、側音、半母音について調べる。そして、実際に発音してみる。
② 高母音、中母音、低母音について発声の訓練を行う。。
2 学習到達目標
① 発音器官のそれぞれについて説明できる。
② 有気音、無気音の違いについて説明できる。
③ 調音点について説明できる。。
3 課題
① 口の中に指を入れて、それぞれの発音の時に、舌がどの位置に来るか確認する。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ9 音の組み合わせとアクセント
1 何を学ぶか
① 日本語と英語の実際の発話を聞いて、アクセントの違いを確認する。
② 国際音声記号について簡単な表記を覚える。
2 学習到達目標
① 日本語の高低アクセントと英語の強弱アクセントの違いについて説明できる。
② 母音と子音の違いについて説明できる。
③ 母音を発生するときの口蓋内の様子について説明できる。
3 課題
① 有声歯茎摩擦音、有声軟口蓋閉鎖音などを発話する。そして、それらが使われる単語を複数個見つける。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ10 英語の語彙の多様性
1 何を学ぶか
① 英語に対する、ギリシア語、ラテン語、フランス語の影響を調べる。
② 現代のアメリカ英語に対するスペイン語の影響を考える。。
2 学習到達目標
① 英語に取り入れられた外来語の要素について説明できる。
② フランス語がどの程度、英語に影響を与えたのか説明できる。
③ 語源の研究の意義について説明できる。
3 課題
① 日本語から英語に入った単語を抜き出して、どのようなジャンルの語彙が多いか調べる。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ11 文ができる仕組み
1 何を学ぶか
① 伝統的な文法と変形生成文法が学習者に対する影響を比較してみる。
② 5文型によってどの程度まで文法構造が理解できるか考察する。
③ 句構造標識を考察する。
2 学習到達目標
① 単語から文が作られる過程を説明できる。
② 文法研究の歴史を簡単に説明できる。
③ 変形生成文法の特徴について説明できる。
3 課題
① 任意の英文を取り出して、その句構造標識を示す。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ12 英語の意味
1 何を学ぶか
① 教育の場において、効果的な意味の教え方を考察する。
② 文化的に英語の語彙の持つ二重構造について調べる。。
2 学習到達目標
① 英語の意味と人間の認識の関係を説明できる。
② 指示説、構造意味論、概念論などを説明できる。
③ 意味と文化の関係について説明できる。。
3 課題
① mother, father などの家族を示す英単語は、構造意味論の立場からどのように説明できるか調べる。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ13 英語の意味とコンテキスト
1 何を学ぶか
① 日常会話において、多義性の解消はどのように行われいるか調べる。
② 日本語と英語の意味の構造の違いを考察する。。
2 学習到達目標
① 表面的な意味と深層的な意味の違いについて説明できる。
② 隠喩、換喩などの比喩について説明できる。
3 課題
① My husband is a baby.という文はどのような意味に解釈されるか、それぞれの場合を説明する。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ14 英語と文化
1 何を学ぶか
① 多文化共生社会とはどのような社会であるか調べる。
② サピア=ウオーフの仮説を考察する。
③ 高コンテキスト文化と低コンテキスト文化の違いを考える。
2 学習到達目標
① 伝統的な西洋と東洋との二限対立の分類から、多次元化しつつある現代文化を説明できる。
② 文化と言語の関係について説明できる。
③ 言語相対論について説明できる。
3 課題
① 世界に多発する民族問題と言語の事例を収集する。
② 日本語文化は英語文化からどのような影響を受けているか調べる。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ15 言葉と社会、言葉と国家
1 何を学ぶか
① 世界での多文化主義の国の特徴を考察する。
② それらの国で、言語教育はどのように進められているか調べる。
③ カナダの2言語多文化主義について考察する。
2 学習到達目標
① 多文化主義を標榜している国の言語教育の特徴を説明できる。
② 公用語と国語の違いを説明できる。
③ 英米の旧植民地では英語がどのように取り扱われているか説明できる。。
3 課題
① いわゆる英語圏の国々で使われる英語以外の言語の特徴を調べる。
② 日本では英語はどの程度必要とされているか考察する。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
資料
【授業】在留外国人と言語
Ⅰ はじめに
本科目で学ぶことで、在留外国人の実態とそれらの人々のかかえている言語問題を理解することである。外国人の増加という現象は近年顕著になってきており、我々がどのように対処すべきかは緊急の問題となっている。それらの問題を概観してゆきたい。
Ⅱ 授業の目的・ねらい
多文化共生社会と言われている現代において、どのような問題が生まれつつあるのか、そしてそれらに対して、我々日本人はどのように取り組んできたのか、そして今後はどのように取り組むべきかについていくのか考察を深めることがこの授業の目的・ねらいである。授業を通して、これらの問題は他人事ではなくて、自分事であるとの認識を持つようになりたい。
Ⅲ 授業の教育目標
在留外国人と言語に関して、基本的な概念を理解して、それらの概念を通して、現代の日本が抱える問題点を理解するようにする。言語問題、とりわけ、外国人に言語サービスをどのように提供するか、外国人は日本語が苦手という点をどのように克服するか検討してゆきたい。
テーマ1 在留外国人の定義
1 何を学ぶか
在留外国人という名称と定義について考える。何故に、この名称が選ばれたのか。その他に相応しい名称はないか。在留外国人の数が増えている実際を数字で理解する。
2 学習到達目標
日本語にまだ慣れていないことで、どのような問題点が生じるか説明することができる。言語サービスという概念の誕生とその発展を時系列的にフォローしてゆくで、外国人の比率が数十%以上に達した欧米諸国と比較して、日本はどのような点が異なるか説明することができる。
3 課題
① 言語サービスはなぜ必要なのかレポートにまとめる。
② 自分の住んでいる自治体で外国人に提供される言語サービスの内容をレポートにまとめる。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ2 言語サービスの主体
1 何を学ぶか
言語サービスと多言語サービスの違いについて学び、言語サービスを提供する主体として地方自治体が最適であることを理解する。
2 学習到達目標
① 法的な観点からの、地方自治体の役目を説明することができる。今度はどのような視点から、法整備が行われてゆくべきか説明することができる
② マイナーな言語の話者がかかえる問題点について説明できる。
③ 在留外国人の増加の程度を予想して、地方自治体がどのようなことをするべきか説明できる。
3 課題
自分が経験した外国人とコミュニケーションするときの問題点を互いに紹介しあう。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ3 言語サービスの対象者
1 何を学ぶか
言語サービスの対象者は誰か。げんごサービスの主体とどのように互いと関連する考察する。オーバーステイの外国人はどのように向かい合うか、そしてその子どもたちはどのような教育が必要か。そもそも、言語サービスを行うその法律的な根拠は何か、単なる善意で行っているのか、検討する。
2 学習到達目標
① どのような外国人に言語サービスを提供すべきか説明できる。世界的に話し手の多い言語話者とマイノリティ言語の話者に対してのサービスの違いを説明できる。
② 出身国別の外国人の言語問題の違いを説明できる。
③ 言語サービスの法的根拠を説明できる。
3 課題
① 日本語や英語以外の母語保持教育について考える。
② 緊急事態では、外国人はどの言語に頼るかを説明する。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ4 公務員が提供するサービス
1 何を学ぶか
① 公務員とは全体の奉仕者であることを確認する。
② 在留外国人の数が増加している現在を確認する。
③ 地方自治体で働く公務員が在留外国人に対して、どのような言語サービスを行っているか確認する。
2 学習到達目標
① 外国人雇用管理主任者とはどのような仕事か説明できる。
② Visaやpassportの概念について説明ができる。在留カードの歴史や現在の機能について説明できる。
③ 外国人が住民基本台帳に掲載されるまでのプロセスを理解して説明できる。
④ 市民課や外国人課の役割や外国人に対してのサービスの概要を説明できる。
3 課題
① 外国人雇用管理主任者とはどのような役目を行うかまとめる。
② 外国人実習制度についてまとめる。
③ 在留カードの機能についてまとめる。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ5 やさしい日本語
1 何を学ぶか
外国人向けに提案されてきた易しくされた日本語の歴史や概要を調べて、どのような役割を果たしているか学ぶ。そして、「やさしい日本語」を普及する場合の問題点を考える。「やさしい日本語」は英語や外国人の母語とどのように異なるか学ぶ。
2 学習到達目標
① やさしい日本語の成立に大きく関与した「簡約日本語」について説明できる。
② 「やさしい日本語」の生まれた必要性について説明できる。
③ 「やさしい日本語」を用いることができる。
3 課題
① 外国人に対して日本語で話したときに感じた問題点を、受講者同士で共有し合う。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ6 日本語の国際化について
1 何を学ぶか
①海外で日本語教師が直面する問題点を考える。
②日本語教師として生計をたてる場合の問題点を考える。
2 学習到達目標
① 日本語教育の国際的な広がりについて説明できる。
② 日本語能力試験、日本語教育能力検定試験などの制度を説明できる。
③ 国連での公用語には何があるか説明できる。
3 課題
① 各国で日本語を学んでいる人の最新の数を調べてみる。
② 外国人に対して日本語で話したときに感じた問題点を、受講者同士で共有し合ってみる。
③ 日本語能力検定試験はどのような目的で作られたのか述べよ。
④ 日本語教育と国語教育の違いを述べよ。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ7 日本語が話せない子どもたちの増大
1 何を学ぶか
① 外国人が直面する問題点をいくつか列挙して、その対策を考えてみる。その中で、日本語の能力の有無がどのような問題点を生み出すか考えてみる。
② 国民である場合(国籍を取得した場合)と永住権を持っている場合の違いについて考える。
2 学習到達目標
① 市役所で外国人の世話をする課の仕事の内容を説明できる。
② 外国人への地方自治体の責任を説明できる。
③ 窓口となる公務員の必要な語学力を説明できる。
3 課題
① 近隣の市町村の役場を訪問して、外国人の世話をする部署について調べてみる。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ8 ダブルリミッド
1 何を学ぶか
ダブル・リミテッドとは何か。どのような社会的な背景から生まれたのか考えてみる。減算的バイリンガリズムと加算的バイリンガリズムを調べる。減算的バイリンガリズムを防ぐ手立てを考えてみる。CALPとBICSについて調べる。
2 学習到達目標
① 野生児の事例を調べることで、言語習得の臨界期について説明できる。
② 複数の言語を子どもの時に習得することから生まれる長所と短所を説明できる。
③ ダブル・リミテッドはどのような場合に生まれるか説明できる。
3 課題
自分に子どもができたとして、各国に滞在しなければならないとして、どのような言語教育を与えるか受講者同士で議論し合う。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ9 文化の違い
1 何を学ぶか
① 世界には様々な文化があり、在留外国人もそれらの文化を背景にしていることを理解する。
② 食文化の違い(例えば、イスラム教の子どもが来て、豚肉が食べられないというケースを想定して、どのように対処するかなど)を検討する。あるいは、女性のかぶるベールなど、衣服の習慣なども理解して、日本社会がどのように受け入れるか学ぶ。
2 学習到達目標
① 異文化の子どもをどのように日本に受け入れるべきか説明ができる。
② 異文化の違いで起きる摩擦について説明できる。
③ 異文化間摩擦の克服の仕方について説明できる。
3 課題
① 世界に多発する民族問題と言語の事例を収集する。取りわけ多文化社会がどのように対処してきたか、自分事として考える。
② 近所にハラール対応のレストランがあるか調べてみよう。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ10 社会とルール
1 何を学ぶか
① 西洋人と非西洋人に対しての日本人の態度の違いなどを考える。
② 敬語の使用が社会全体に組み込まれている日本社会の特質を知る。
2 学習到達目標
① 日本の社会でのルールが在留外国人達にどのように映るか説明できる。
② 敬語などの使い方を説明できる。
③ 面接やお辞儀などの文化的な相違を説明できる。
3 課題
① 面接の時の様子の違いを西洋と日本とで比較してみる。
② 握手とかお辞儀の仕方を在留外国人にどのように教えるか考察する。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ11 人権宣言
1 何を学ぶか
① 世界言語権宣言を読みながら、言語権という概念について考える。
② 差別をなくすために、国際連合が果たしている役割を考察する。
2 学習到達目標
① 人権宣言の骨子を説明できる。
② マイノリティの権利宣言の内容を説明できる。
③ 様々な宣言(子どもの権利条約、国際人権規約)などの意義を説明できる。
3 課題
① それぞれの宣言を時系列的にまとめてみましょう。
② これらの宣言が在留外国人の言語活動にどのように影響を与えるか考えてみる。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ12 国籍の取得
1 何を学ぶか
① 日本国籍を取得する手続きを説明できる。
② ビザの更新、永住権の取得、とはどのようなことなのか、検討する。
2 学習到達目標
① 国籍を取得するとどのような面で利点があるのか説明ができる。
② 出生地主義と血統主義の違いについて説明できる。
③ 二重国籍について説明できる。
3 課題
① 近所で不就学の外国人児童を見かけた場合、どのようにするか話し合う。
② 日本国籍を保持していない場合、児童生徒はどのような不利な取扱を受けるか考える。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ13 法廷通訳他
1 何を学ぶか
① 司法通訳とは何か、を知る。
② 司法通訳が必要とされる背景を知る。
③ 日本語が不自由な外国人が、犯罪の被害者、加害者として関与した場合にどのような問題点が生じるか考える。
2 学習到達目標
① 法廷通訳の必要性について説明できる。
② マイナーな言語の通訳人の必要性ついて説明できる。
③ 諸外国のとうてい通訳人について説明できる。
3 課題
① 年間で必要とされる法廷通訳人の数を言語別に調べる。
② もしも弁護、検察、裁判で同じ通訳人が兼ねたらどのような弊害が起こるのか考える。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ14 国際観光都市と多言語
1 何を学ぶか
① 外国人向けの標識やポスター、ホームページなどの充実を検討する。
② 主要都市以外の都市への外国人観光客を呼びこむ方法を考える。
2 学習到達目標
① 外国人観光客と在留外国人との違いについて説明できる。
② オーバーツーリズムの問題について説明できる。
③ 観光業が振興することで、在留外国人の言語サービスにどのように貢献するか説明できる。
3 課題
① 受講生が滞在する市町村へ外国人観光客を増やすための政策をいくつか挙げてみる。
② いわゆる観光地を1つ選び、外国人観光客を迎入れる方策がどのように行われているか現地調査をおこなう。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
テーマ15 望ましい多文化共生社会
1 何を学ぶか
① 多文化共生社会とはどのような社会であるか調べる。
② シンガポールの事例を調べて、どのように多文化共生社会を維持しているか考察する。
③ 日本が今後進むべき社会の姿を思い浮かべる。
2 学習到達目標
① 諸外国で多文化共生社会を標榜している国が直面している問題点を説明できる。
② 先進国で行われている多文化共生社会を説明できる。
③ 外国人の比率が一割を超える社会の状況を説明できる。
3 課題
① 小中小学校では、多文化共生社会を考えさせる教材のあり方を考察する。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
資料
【授業】書道研究Ⅰ
Ⅰ はじめに
日本における漢字仮名交じりの書の発生とその展開については,書跡としての発生は平安から鎌倉にかけての時代に遡るとはいえ,「漢字仮名交じりの書」という書芸術のジャンルが生まれてからは日が浅いため,その内容と形式についての学術的な研究成果の蓄積が不十分な状況にある.しかしその一方で,高等学校芸術科書道においては,漢字の書,仮名の書と並んで取り上げられるなど,社会的・教育的な位置づけが高まりつつある。現代においては「漢字仮名交じりの書」の歴史的な検討やその評価規準の確立が強く求められている。
Ⅱ 授業の目的・ねらい
漢字仮名交じりの書の内容と形式の変遷をたどる.また,日本近代の文化人は,墨書やペン書によって数多くの手紙を遺しているが,その多くは「候文」などの特色ある表記によるものとはいえ,現代につながる漢字仮名交じり文によって書かれており,「漢字仮名交じりの書」の制作において,参考とすべきものの一つとなっている.本講義では,漢字仮名交じりの書の長い伝統を踏まえて,その中で定着した手紙の書式とその表現について学びつつ,さらに現代の漢字仮名交じり書作品へ活用する方法について考える.
Ⅲ 授業の教育目標
手紙の書式と表現について理解し,手紙の持つ「漢字仮名交じりの書」としての表現の特質と,それを現代の書の制作に活用する方法について考えることができる.
第1講 漢字仮名交じりの書の発生と展開
1.何を学ぶか
(1)漢字仮名交じりの書の発生
(2)漢字とかなの調和
(3)漢字仮名交じりの書と書式
2.学習到達目標
(1)漢字仮名交じりの書の発生と展開について,漢字とかなの調和の観点を踏まえて,説明することができる.
(2)漢字仮名交じりの書のさまざまな書式について,その具体例を挙げて,説明することができる.
3.研究課題
(1)鎌倉時代の絵巻詞書に見られる漢字仮名交じりの書について,その特徴をまとめなさい.
(2)近世初期の色紙や巻物に見られる漢字仮名交じりの書について,その特徴をまとめなさい.
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第2講 手紙の歴史と日本語の表記
1.何を学ぶか
(1)日本における手紙の歴史
(2)表記法としての候文
2.学習到達目標
(1)日本における手紙の歴史について,その概略を説明することができる.
(2)候文の漢語的表現に概ね習熟し,その活字化された文献について,読解を試みることができる.
3.研究課題
(1)藤原佐理《離洛帖》の手紙としての魅力について考察しなさい.
(2)候文の漢語的表現について,謙譲などの敬語的な側面から,その特徴をまとめなさい.
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第3講 手紙の書式とその書き方
1.何を学ぶか
(1)手紙の目的と書式
(2)巻紙による手紙の書き方
2.学習到達目標
(1)手紙の目的とそれに応じた書式について,その具体例を挙げて,説明することができる.
(2)巻紙による手紙の書き方について,その概略を説明することができる.
3.研究課題
(1)お見舞・お礼などの手紙の目的を明確にして,かつ具体的な宛先を想定して,巻紙による手紙を書きなさい.
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第4講 手紙の読解と鑑賞―安田靭彦―
1.何を学ぶか
(1)良寛讃仰
(2)正しさと確かさと
2.学習到達目標
(1)安田靭彦が良寛の書の紹介において果たした役割について,年譜などの事歴にもとづいて説明することができる.
3.研究課題
(1)墨法の効果などの点から,安田靭彦の書の特質について分析し,まとめなさい.
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第5講 手紙の読解と鑑賞―土田麦僊―
1.何を学ぶか
(1)平明の天才
(2)穏やかさへのあこがれ
2.学習到達目標
(1)手紙の内容と書きぶりから,筆者の人間性について想像し,説明することができる.
3.研究課題
(1)安田靭彦の書と土田麦僊の書とを比較して,その共通点・相違点について分析し,まとめなさい.
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第6講 手紙の読解と鑑賞―鏑木清方―
1.何を学ぶか
(1)芸術の持つ役割
(2)是非もなきこと
2.学習到達目標
(1)手紙の読解を通じて,戦時における芸術,あるいは芸術家の役割についての,鏑木清方の考えを推察し,説明することができる.
3.研究課題
(1)日本画家の手紙の書の特質について,この講義で取り扱った3人の書を比較しながら,考察しなさい.
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第7講 手紙の読解と鑑賞―黒田清輝―
1.何を学ぶか
(1)明治の洋画壇
(2)本文と追而書
(3)速筆と切り返し
2.学習到達目標
(1)黒田清輝の手紙の書の特質について,用筆や運筆の観点から,説明することができる.
3.研究課題
(1)候文という文体のもつ特質について,くり返し音読してから,話し合いなさい.
(2)本文と追而書の部分の内容を読み比べて,追而書の役割について考察しなさい.
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第8講 手紙の読解と鑑賞―小出楢重―
1.何を学ぶか
(1)人と人とをつなぐもの
(2)書の線と絵画の線
2.学習到達目標
(1)手紙の内容と書きぶりから,筆者と宛名の人物との人間関係について想像し,説明することができる.
3.研究課題
(1)小出楢重の書の魅力について,その画と見比べながら,話し合いなさい.
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第9講 手紙の読解と鑑賞―藤田嗣治―
1.何を学ぶか
(1)作戦記録画
(2)彩管報国
2.学習到達目標
(1)手紙の読解を通じて,藤田嗣治が作戦記録画《アッツ島玉砕》を制作し,発表した事由について,説明することができる.
3.研究課題
(1)歴史的事実を明らかにするうえで,資料としての手紙が果たす役割について,考察しなさい.
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第10講 手紙の読解と鑑賞―伊藤左千夫―
1.何を学ぶか
(1)洒々落々たる味
(2)画に題する歌
2.学習到達目標
(1)手紙の内容と書きぶりから,筆者の人間性について想像し,説明することができる.
3.研究課題
(1)伊藤左千夫の書の魅力について,その詠歌や文章を参考にしながら,話し合いなさい.
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第11講 手紙の読解と鑑賞―長塚節―
1.何を学ぶか
(1)澄明さ・濁りのなさ
(2)結核という病
2.学習到達目標
(1)手紙の内容と書きぶりから,筆者の人間性について想像し,説明することができる.
3.研究課題
(1)長塚節が自分の病気とどのように向き合ったか,その詠歌を参考にしながら,考察しなさい.
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第12講 手紙の読解と鑑賞―斎藤茂吉―
1.何を学ぶか
(1)長塚節と茂吉
(2)粘着気質の人
2.学習到達目標
(1)手紙の内容と書きぶりから,筆者の人間性について想像し,説明することができる.
3.研究課題
(1)斎藤茂吉の編集者としての仕事ぶりについて,考えたことをまとめなさい.
(2)いわゆる「アララギ派」の歌人たちの系譜をたどりながら,歌人と書との関わりについて,考察しなさい.
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第13講 手紙の読解と鑑賞―萩原朔太郎―
1.何を学ぶか
(1)昭和十三年六月六日
(2)表記への「こだわり」
2.学習到達目標
(1)手紙の内容と書きぶりから,筆者の人間性について想像し,説明することができる.
3.研究課題
(1)手紙の内容と筆者の年譜とを照合しながら,手紙の書かれた時日を特定していく過程について,まとめなさい.
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第14講 手紙の読解と鑑賞―高村光太郎―
1.何を学ぶか
(1)光太郎書の変遷
(2)「造形」と「試み」
2.学習到達目標
(1)高村光太郎の手紙の書における書きぶりの変遷について,様式によりその時期を分けて,説明することができる.
3.研究課題
(1)葉書という書式の特徴について,高村光太郎の場合を具体例として,考察しなさい.
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第15講 手紙の書美と制作への活用
1.何を学ぶか
(1)気息の表現―新鮮さ―
(2)初心の表現―純真さ―
(3)率意の表現―自然さ―
(4)手紙に学ぶ
2.学習到達目標
(1)手紙の魅力やその内容と書きぶりとの関わりについて,この講義の内容を踏まえて,説明することができる.
(2)手紙における書表現を漢字仮名交じりの書の制作に活かす方法について,この講義の内容を踏まえて,説明することができる.
3.研究課題
(1)手紙を書くことの意義について,自分が考えていることをまとめた上で,話し合いなさい.
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
Ⅳ レポート課題
課題1
第6講:研究課題(1)について,レポートにまとめなさい.
※冒頭に,自分なりの「題名」を記してから,本文を書いてください。
※レポートは,wordで作成し,PDFファイルで提出のこと.分量は,A4:1枚程度.自分がもっとも適切と考える書式設定で作成してください.
課題2
第14講:研究課題(1)について,レポートにまとめなさい.
※冒頭に,自分なりの「題名」を記してから,本文を書いてください。
※レポートは,wordで作成し,PDFファイルで提出のこと.分量は,A4:1枚程度.自分がもっとも適切と考える書式設定で作成してください.
Ⅴ アドバイス
課題1解説
近代の日本画家は,洋画とは異なる日本画の独自性を求めたといわれています.そのとき彼らが注目したのは,日本画の線のもつ性格(線性)であったとされています.彼らは,線のもつどのような性格に注目したのでしょうか.3人の日本画家と良寛の書との関わりをヒントにして考えてみましょう。
課題2解説
高村光太郎は,生涯にわたって,数多くの書簡を残しています.それらの多くは『高村光太郎全集』に収録されていますが,それらの記録と実際の肉筆とを比較してみると,彼の感じ方や考え方をうかがうことのできる,新たな発見があります.そこから,彼が葉書という書式(メディア)をどのようにとらえていたかを考えてみましょう.
Ⅵ 科目修得試験:レポート試験
手紙における書表現を漢字仮名交じりの書の制作に活かす方法について,この講義の内容を踏まえて,あなたの考えを説明しなさい.
※冒頭に自分なりの「題名」を記してから,本文を書いてください。
※レポートは,wordで作成し,PDFファイルで提出のこと.分量は,A4:1枚程度.自分がもっとも適切と考える書式設定で作成してください.
Ⅶ テキスト
○住川英明著『書道研究Ⅰ』 2024 岐阜女子大学
Ⅷ 参考文献
○野中吟雪著『書を語る』 2017 芸術新聞社
○古谷稔著『漢字かな交じりの書』 1998 雄山閣
○小松茂美編『日本書道辞典』 1987 二玄社
○書学書道史学会編『書道史年表事典』 2007 萱原書房
【授業】国内旅行業務応用
Ⅰ はじめに
本科目は、旅行業務に関する国家試験である旅行業務取扱管理者(国内・総合)の試験科目の一つである「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款」について学習する。約款とは、事業者が不特定多数の相手方(主に消費者)との間で大量の同種取引を迅速・効率的に行うために作成された典型的な内容の取引条項のことである。国家試験で求められる約款に対する知識は、標準旅行業約款、国内旅行運送約款、一般貸切力自動車運送事業標準運送約款、フェリー標準運送約款、そしてモデル宿泊約款である。これら約款で学習するのは、国が定める標準約款である。
旅行業等、その他観光・旅行にかかわる職に従事するためには、理解しておかなくてはならない事柄であり、観光専修においては必須科目としている。
Ⅱ 授業の目的・ねらい
旅行業務取扱管理者の試験科目「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款」に出題される基礎知識、専門知識を学び、合格点レベルの知識習得を目指す。
全講義対面で受講する学生においても、e-Learning動画を視聴することで何度も繰り返し学習することで理解が深まる。
Ⅲ 授業の教育目標
ここでは、15のテーマに基づき、それぞれのテーマの基礎・専門知識を身につけることとする。また、そのテーマに基づいた問題を解くことによって、理解を深めることができる。なお、第1講は対面とする。
第1講 旅行業法と約款、募集型企画旅行・受注型企画旅行・手配旅行・旅行相談・渡航手続き代行(対面)
1.何を学ぶか
旅行業務取扱管理者試験受験科目の一つである「旅行業約款、運送・宿泊約款」を学ぶにあたり、旅行業法と約款の違い、旅行業者等の業務内容である企画旅行、手配旅行、旅行相談および渡航手続代行とは何かを学ぶ。
2.学習到達目標
・旅行業法と約款の違いが分かる
・旅行業等の業務である募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、旅行相談、渡航手続き代行とは何かが分かる
3.研究課題
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第2講 標準旅行業約款<募集型企画旅行契約>①
1.何を学ぶか
標準旅行業約款「募集型企画旅行契約の部」より、約款の適用範囲、約款に出てくるさまざまな用語の定義や旅行者との旅行契約締結の申込、予約、契約の拒否事由について学ぶ。
2.学習到達目標
・約款の適用範囲について理解する
・募集型企画旅行契約の定義について説明できる
・標準旅行業約款の用語について理解する
・募集型企画旅行契約の申込方法および契約の成立について理解する
・「適用範囲」「用語の定義」「契約の締結」に関する問題の解答を導き出すことができる
3.研究課題
・問題集の問題に取り組む
・テキスト:理解度チェック
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第3講 標準旅行業約款<募集型企画旅行契約>②
1.何を学ぶか
標準旅行業約款「募集型企画旅行契約の部」より、旅行者との契約成立後交付する契約書面と確定書面の交付について、契約後の変更や解除の要件、変更する場合の旅行代金の取扱について学ぶ。
2.学習到達目標
・契約書面と確定書面の違いが分かり、説明できる
・募集型企画旅行契約の「契約の変更」と「契約の解除」について理解する
・募集型企画旅行契約の変更及び解除に関する問題の解答を導き出すことができる
3.研究課題
・問題集の問題に取り組む
・テキスト:理解度チェック
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第4講 標準旅行業約款<募集型企画旅行契約>③
1.何を学ぶか
標準旅行業約款「募集型企画旅行契約の部」より、団体・グループ契約における契約締結と代表者の権限と義務について学ぶ。また、旅行業者が旅行者に対して行わなければならない業務の一つである旅程管理について添乗員の業務について学ぶ。
2.学習到達目標
・募集型企画旅行の「団体・グループ契約」の締結と契約責任者の義務について理解する
・募集型企画旅行の団体・グループ契約に関する問題の解答を導き出すことができる
・募集型企画旅行契約の旅程管理について理解する
3.研究課題
・問題集の問題に取り組む
・テキスト:理解度チェック
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第5講 標準旅行業約款<募集型企画旅行契約>④
1.何を学ぶか
標準旅行業約款「募集型企画旅行契約の部」より、第7章「責任」と「特別補償」について学ぶ。旅行には、悪天候による運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止や暴動、戦乱などトラブルがつきものである。このような場合の旅行業者が負う損害賠償責任の有無について学ぶ。
2.学習到達目標
・募集型企画旅行契約の特別補償について理解する
・旅行業者の責任の有無についてケースごとに判別することができる
・募集型企画旅行の旅程管理及び特別補償に関する問題の解答を導き出すことができる
3.研究課題
・問題集の問題に取り組む
・テキスト:理解度チェック
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第6講 標準旅行業務約款<募集型企画旅行契約>⑤
1.何を学ぶか
標準旅行業約款「募集型企画旅行契約の部」より、「旅程保証」について学ぶ。旅程保証制度は、募集型企画旅行の旅程変更に対する苦情の増加を背景に1995年に標準旅行業約款の改正時、導入された。約款で定められる重要な旅程変更が発生した場合に旅行者へ支払われる変更補償金について学ぶ。
募集型企画旅行契約
・旅程保証
・旅行業者の免責事項
2.学習到達目標
・募集型企画旅行契約の旅程保証について理解する
・旅行業者の免責事項についてケースごとに判別することができる
・募集型企画旅行の旅程保証に関する問題の解答を導き出すことができる
3.研究課題
・問題集の問題に取り組む
・テキスト:理解度チェック
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第7講 標準旅行業約款<受注型企画旅行契約>①
1.何を学ぶか
標準旅行業約款「受注型企画旅行契約の部」より、契約の成立、契約の変更と解除について学ぶ。
2.学習到達目標
・受注型企画旅行契約の定義について説明できる
・受注型企画旅行契約の方法について理解する
・受注型企画旅行契約の成立、変更および解除について理解する
・募集型企画旅行契約の成立・変更・解除との違いを説明できる
・受注型企画旅行契約の成立、変更、解除に関する問題の解答を導き出すことができる
3.研究課題
・問題集の問題に取り組む
・テキスト:理解度チェック
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第8講 標準旅行業約款<受注型企画旅行契約>②
1.何を学ぶか
標準旅行業約款「受注型企画旅行契約の部」で定められている旅程管理、旅行業者の責任事項について学ぶ。
2.学習到達目標
・受注型企画旅行契約の旅程管理及び旅行業の責任について理解する
3.研究課題
・問題集の問題に取り組む
・テキスト:理解度チェック
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第9講 標準旅行業約款<手配旅行契約>①
1.何を学ぶか
これまで学習した企画旅行(募集型・受注型)と手配旅行の定義の違いについて確認し、標準旅行業約款「手配旅行契約の部」で定められる契約の成立、契約の変更と解除について学ぶ。
2.学習到達目標
・手配旅行契約の定義について説明できる
・手配旅行契約の成立、変更と解除について理解する
・手配旅行契約に関する問題の解答を導きだすことができる
3.研究課題
・問題集の問題に取り組む
・テキスト:理解度チェック
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第10講 標準旅行業約款<手配旅行契約>②
1.何を学ぶか
標準旅行業約款「手配旅行契約の部」より、団体・グループ手配について学ぶ。
2.学習到達目標
・手配旅行契約の団体・グループ手配について理解する
・手配旅行契約の団体・グループ手配に関する問題の解答を導き出すことができる
3.研究課題
・問題集の問題に取り組む
・テキスト:理解度チェック
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第11講 標準旅行業約款<旅行相談契約>
1.何を学ぶか
標準旅行業約款「旅行相談契約の部」で定められる契約の成立、契約の解除について学ぶ。
2.学習到達目標
・旅行相談契約の定義について説明できる
・旅行相談契約の成立、契約の解除について理解する
・旅行相談契約に関する問題の解答を導き出すことができる
3.研究課題
・問題集の問題に取り組む
・テキスト:理解度チェック
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第12講 国内航空運送約款
1.何を学ぶか
人又は物品を場所的に移動することを引き受ける契約を運送契約といい、そのうち運送の対象が人であるものが「旅客運送」、運送の業域が空中運送である場合を「航空運送」という。本講では、国内航空運送約款で定められている内容について概観しながら、航空券の取り扱い、運賃及び料金システム、受託手荷物・持込手荷物の取り決めについて学ぶ。
2.学習到達目標
・国内航空運送約款の専門用語について理解する
・航空券の仕組みおよび座席予約指定について理解する
・航空運送の制限やその拒否について理解する
・航空運賃について理解する
・国内旅客運送約款で定められている手荷物に関する各種取り決めについて理解する
・国内航空運送約款に関する問題の解答を導き出すことができる
3.研究課題
・問題集の問題に取り組む
・テキスト:理解度チェック
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第13講 フェリー運送約款
1.何を学ぶか
一般旅客定期航路事業者が定める標準運送約款「フェリー標準運送約款」には、「旅客運送の部」、「受託手荷物及び小荷物運送の部」、「特殊手荷物運送の部」、「自動車運送の部」がある。国家試験で問われるのはこの「旅客運送の部」が殆どである。本講では、フェリー運送における運賃及び料金設定、乗船券の適用期間や変更、紛失時の取扱について学ぶ。
2.学習到達目標
・フェリー運賃及び料金について理解する
・運送の引受け条件について理解する
・乗船券の適用期間及び変更について理解する
・フェリー運送約款に関する問題の解答を導き出すことができる
3.研究課題
・問題集の問題に取り組む
・テキスト:理解度チェック
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第14講 貸切バス運送約款
1.何を学ぶか
本講で取り扱うのは、旅客自動車運送事業のなかでも一般貸切旅客自動車運送事業における約款である。一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款における、運送契約成立までの流れと変更時の取扱、運賃及び料金制度について学ぶ。
2.学習到達目標
・貸切バス運賃及び料金及び違約料について理解する
・貸切バス運送の引受け条件について理解する
・貸切バス運行に関する責任の有無について理解する
・貸切バス運送約款に関する問題の解答を導き出すことができる
3.研究課題
・問題集の問題に取り組む
・テキスト:理解度チェック
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第15講 モデル宿泊約款
1.何を学ぶか
ここで取り扱うモデル宿泊約款は令和5年の旅行業法改正に伴い最終改正された約款である。宿泊契約の申込から成立までの流れや契約解除の取り決め、宿泊料金設定、キャンセル料の計算方法について学ぶ。
2.学習到達目標
・宿泊契約の成立・解除について理解する
・宿泊料金と追加料金について理解する
・手荷物、携帯品の保管、駐車の責任の有無について理解する
・モデル宿泊約款に関する問題の解答を導き出すことができる
3.研究課題
・問題集の問題に取り組む
・テキスト:理解度チェック
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
Ⅳ レポート課題
課題1
課題2
Ⅴ アドバイス
課題1解説
課題2解説
Ⅵ 科目修得試験:レポート試験
あり。定期筆記試験(100点満点)
Ⅶ テキスト
『2025旅行実務シリーズ2 旅行業約款、運送・宿泊約款』JTB総合研究所
Ⅷ 参考文献
【授業】英語科教育法Ⅰ
Ⅰ はじめに
本科目を学ぶことで、英語教育法に関する基本的・理論的な知識を得て、英語教員として学習者に英語を教えることができるようになる。なお、この科目「英語科教育法Ⅰ」は理論的な側面を重視しており、「英語科教育法Ⅱ」では、実践的な側面を重視している。これら二つの科目を履修することで、英語教育法を理論と実践の両分野から理解することができるようになる。
Ⅱ 授業の目的・ねらい
世界の英語、異文化理解、言語習得論、各種教授法、テストや評価などの基本項目を理解すると同時に、教育基本法や学校教育法の中で英語教育がどのように位置づけられるか考えてゆく。さらに、学習指導要領に示された目標をどのように授業で、どの教科書を用いるかを議論して検証して行く。各テーマの終了後に課題提出を行い、受講者の理解が確実に深まるようにしたい。
Ⅲ 授業の教育目標
英語教育の基軸となる学習指導要領及び教科用図書 (教科書) について理解し、学習到達目標及び年間指導計画、単元計画、各時間の指導計画について理解する。また、5つの領域(「聞くこと」「読むこと」「話すこと[やり取り]」「話すこと[発表]」及び「書くこと」)の指導及び各領域を支える音声、文字、語彙・表現、文法の指導について基本的な知識と技能を身に付けるとともに、複数の領域を統合した言語活動の指導方法を身に付ける。
テーマ1 英語教育の目的
1 何を学ぶか
国際化時代の英語教育の在り方は従来と大幅に異なるものであり、その進歩の過程を理解して十分に納得できるようになる必要がある。さらには、英語教育の目的が教養英語から実用英語へと変遷した様子を理解して、実用英語教育の一環としての資格英語の教え方を学ぶ。
2 学習到達目標
英語教育の目的は何であるか説明できる。
初等教育、中等教育のそれぞれにおいて必要な英語教育の内容を説明できる。
日本における英語教育の歴史を説明できる。
3 課題
自分の考える英語教育の目的をレポートにまとめる。
日本における語学教育の歴史をレポートにまとめる。
4 動画資料
5 プレゼン資料
テーマ2 英語教師論
1 何を学ぶか
教師、教員、教官、教諭などの類似の名称の違いを調べることで、英語を教える人材がどのような社会的な役割や期待を背負っているか理解してゆく。さらには、理想的な英語教師の人物像、英語運用能力、授業を運営する能力について考察する。そして、英語に関する免許状を種類に沿って理解してゆく。
2 学習到達目標
教師という名称について説明できる。
理想的な教師はどのような人か説明できる。
ALT, 教員免許状について説明できる。
3 課題
自分を担当した先生方がどのような素質を持っていたかレポートにまとめる。
4 動画資料
5 プレゼン資料
テーマ3 英語の学習者
1 何を学ぶか
英語学習に向いている素質とは何であるか考える。学習者の特性(年齢、知能、適性、認知スタイル、動機付け)について、それぞれに対応した教授法はどのようなものか考察する。また、学習者の認知スタイルと教材の理解の仕方の関係も考察する。
2 学習到達目標
学習者の持っている特質を説明できる。
学習者の認知スタイルを説明できる。
学習者の性格や動機付けについて説明できる。
3 課題
英語学習と動機付けの関係についてレポートにまとめる。
場面独立型と場面依存型という二つの認知スタイルの違いをレポートにまとめる。
4 動画資料
5 プレゼン資料
テーマ4 言語習得論
1 何を学ぶか
言語習得における行動主義理論と生得説理論を比較して、それぞれの教授法がどちらの理論に影響を受けているか考察する。関連して、オーディオリンガルメッソードと行動主義理論の関係を調べる。また、Krashen の言語生得理論を調べる。そして、言語習得の過程における一語文から二語文、複語文への発達を調べ、どちらの理論が妥当であるか考える。
2 学習到達目標
子どもの言語発達の段階について説明できる。
ジャン・ピアジェの考えを説明できる。
行動主義理論と言語生得説理論の特質を説明できる。
3 課題
言語習得の臨界期の説明をレポートにまとめる。
行動主義理論と言語生得説理論の違いを表にまとめる。
4 動画資料
5 プレゼン資料
テーマ5 英語教授法
1 何を学ぶか
様々な英語教授法の概要を知ることで、自分が想定する学習者(小、中、高レベル)に相応しい教授法を考える。すぐれた指導法の動画を見る。それらを参考にしながら、コミュニケーション主体の模擬授業を行う。さらにディクテーションやシャドーイングの指導法を訓練する。
2 学習到達目標
英語教授における演繹法と帰納法の違いを説明する。
様々な英語教授法を説明できる。
コミュニケーション主体とは何かを説明できる。
3 課題
自分の関心を持った教授法を一つ選び、概要をレポートにまとめる。
ディクテーションを自分に課して、その様子をレポートにまとめる。
4 動画資料
5 プレゼン資料
テーマ6 学習指導要領
1 何を学ぶか
日本の学習指導要領の歴史について調べる。10年ごとの改訂において、どのような時代背景を反映していたかを考える。また最新の学習指導要領の内容を分析する。諸外国における学習指導要領の特徴を対比して考える。
2 学習到達目標
学習指導要領とは何か説明できる。
学習指導要領の持つ法的拘束力を説明できる。
学習到達目標及び年間指導計画、単元計画、各時間の指導計画について説明できる。
3 課題
各国の学習指導要領の事例を集めて、日本の学習指導要領と比較して報告する。
4 動画資料
5 プレゼン資料
テーマ7 聴くことの指導
1 何を学ぶか
4技能の指導の中で聴くことの位置づけを考える。関連して、すぐれた指導法の動画を見る。また、ディクテーションとシャドーイングの練習を行うこと、さらに日本人が聞き分けに苦手な音の訓練法を知ることで、初等教育、中等教育レベルでの聴くことの指導法を理解してゆきたい。
2 学習到達目標
4技能の中で「聞くこと」の意味を説明できる。
聞くという「能動的な」行動について説明できる。
音声学の基本的な知識を説明できる。
国際音声記号を説明できる。
3 課題
日本人が聞き分けに苦労する音声をレポートにまとめる。。
能動的に「聞くこと」の意味をレポートにまとめる。
4 動画資料
5 プレゼン資料
テーマ8 話すことの指導
1 何を学ぶか
Public Speakingでは、自分が興味を持った話題ならば積極的に話すことにつながるので、学習者の関心のある話す話題の見つけ方、その提示の仕方を考える。とりわけ、小学校においてスピーキングの指導法を考える。学習指導要領で示されたコミュニケーション能力の育成の意味を考える。
2 学習到達目標
話すことの2つの領域(Conversation, Public Speaking)の違いを説明できる。
CEFRで示された「話す力」を説明できる。
Classroom English の大切さを説明できる。
3 課題
Classroom Englishを用いた授業案を作成する。
CEFRの概要をレポートにまとめる。
4 動画資料
5 プレゼン資料
テーマ9 読むことの指導
1 何を学ぶか
読み方の二つの重要な方法である速読と精読を比較する。それぞれの指導の時の留意点を考える。読むことの指導において重要なプレーリーディング活動を調べる。また、読み書きの活動において、文法知識の重要性を考えて、その問題点を考える。加えて、適切な語彙指導法を考える。
2 学習到達目標
歴史的文脈において、文法訳読法が果たした枠割りを説明できる。
ボトムアップとトップダウンの2つの読み方について説明できる。
読むときのスキーマの意味を説明できる。
3 課題
文法の理解とリーディングの関係をレポートにまとめる。
語彙の教え方をレポートにまとめる。
4 動画資料
5 プレゼン資料
テーマ10 書くことの指導
1 何を学ぶか
伝統的な英作文、課題英作文、自由英作文などの特質とその指導法を考える。結束性と一貫性を意識した英文を書く。さらに、パラグラフリーディングを意識した英文の指導法を考える。機械翻訳の活用法について考えて、書くことを指導する際の問題点と活用法を考える。
2 学習到達目標
ライティングへの関心の高める方法を説明できる。
初等教育において、どの程度まで書き言葉の指導を行うか説明できる。
3 課題
子どもたちの書いた英作文を実際に訂正してみる。
各種の機械翻訳を比較してレポートにまとめる。
4 動画資料
5 プレゼン資料
テーマ11 評価と言語テスト
1 何を学ぶか
評価が英語教授の上で果たすべき役割を考える。テストの様々な種類、例えば、主観テストと客観テスト、正誤問題と穴埋め問題などの特質を考える。さまざまな評価、例えば、診断的評価、形成的評価、総括的評価を考える。また、絶対的評価と相対的評価を考える。現在、普及しつつあるCEFRの評価の基本概念を調べる。
2 学習到達目標
色々なテストの種類を説明できる。
評価の視点を説明できる。
テストを信頼性、妥当性、実用性の概念で説明できる。
3 課題
自分が過去に於いて受けてきたテストを、様々な視点で解説する。
4 動画資料
5 プレゼン資料
テーマ12 世界の英語
1 何を学ぶか
英語の歴史から世界への英語の広がりを考える。その歴史的な広がりの中で、地理的な分類、例えば、カチルによる英語の区分け(ENL, ESL, EFL)が生まれてきた経緯を考える。英語教育における英語の規範を考える。
2 学習到達目標
世界の英語の種類を説明できる。
英米英語から国際英語へというパラダイムシフトを説明できる。
アメリカ英語とイギリス英語の違いを説明できる。
3 課題
日本人の英語の特徴をレポートにまとめる。
英語学習における英語の基準は何かレポートにまとめる。
4 動画資料
5 プレゼン資料
テーマ13 小学校の英語教育
1 何を学ぶか
小学校、中学校、高校のぞれぞれのレベルでの英語教育の実態を知ることで、一貫した英語教育の在り方を構想する。早期英語教育における音声教育の可能性を探る。関連した様々な指導法(ライム、早口言葉、歌、ゲーム)などの実践法を理解する。
2 学習到達目標
日本における小学校での英語教育のおこりを説明できる。
小学校での英語音声の指導法を説明できる。
3 課題
学習指導要領では、小学校での英語教育はどのように記されているかレポートにまとめる。
言語の気づきとは何かレポートにまとめる。
4 動画資料
5 プレゼン資料
テーマ14 異文化理解に関する指導
1 何を学ぶか
学習指導要領に異文化理解の必要性が記されていることの意味を考える。英語教育の場で提示すべき多文化共生社会とはどのような社会であるか調べる。言語相対説(サピア=ウオーフの仮説)を考察して、その実例をいくつか調べる。高コンテキスト文化と低コンテキスト文化の違いを考える。さらに、日本特有の文化社会と言語の関係を考察する。
2 学習到達目標
伝統的な西洋と東洋との二限対立の分類から、多次元化しつつある現代文化を説明できる。
文化と言語の関係について説明できる。
言語相対論について説明できる。
3 課題
世界に多発する民族問題と言語の事例を収集してレポートにまとめる。
学習指導要領では異文化理解はどのように扱われているかレポートにまとめる。
4 動画資料
5 プレゼン資料
テーマ15 教材及びICTの活用
1 何を学ぶか
英語教育における英語教材の進歩について考察して、英語教師として今後留意すべき点を考える。AIを用いた英会話の練習の可能性について説明する。生徒達の間に利用が広がりつつある機械翻訳の利点と欠点を考察して、英語教育の場での活用を考える。
2 学習到達目標
英語教材を用途によって、分類できる。
デジタル教材の利点を説明できる。
教材としてのICTを活用できる。
3 課題
小学校での英語教育教材として望ましいものを提示する。
Google 翻訳、DeepL翻訳、ChatGPT翻訳を比較して、レポートにまとめる。
4 動画資料
5 プレゼン資料
【授業】日本書道史
Ⅰ はじめに
現代は,過去の多様な価値観の集積の上に成り立っている.それは,文字文化や書道(書法)文化においても例外ではない.私たちが,広く文字に対して,特に書かれた文字に対してどのように考え,これからどのように関わっていくかを考えるためには,過去の歴史を今日的な視点から的確に捉えることが必要である.日本における文字や書道の歴史を辿ることは,そのまま現在の自己の立脚点を確認する作業である.
Ⅱ 授業の目的・ねらい
文字や書道の歴史を学ぼうとするときに求められるのは,まず過去の書跡や作品等についての正確な知識とその理解である.各時代の社会背景や状況を把握しながら,書跡の内容や形式,書者の事績等を総合的に理解するようにしたい。また,時代ごとのトピックスを的確に捉え,自らの課題に引き寄せ,主体的に学習を深めていく力の育成を目指す.また,現今の書道教育においては,複製等の視覚的教材による鑑賞とそれを充実したものにするための学習指導上の工夫が求められている.対話的な学習を通じて,自己の感じ方や考え方を適切に伝えることのできる能力の育成を目指し,今後求められることになる教育技術の向上につなげたい.
Ⅲ 授業の教育目標
(1)文字文化・書道(書法)文化の広がりの中で,日本の文字や書道の歩みについて的確に捉え,その専門的な事項を理解し,知識化し,活用することができる.
(2)書写における先人の感じ方や考え方を書跡の鑑賞や文献の読解を通して理解し,それらを具体的な書道技法と関連づけて説明することができる.
(3)日本書道史上の様々なトピックスについての討議を通じて,先人の立場や果した役割を理解し,他者の多様な価値観を認めつつ,自らの目標や価値規準の設定・修正に役立てることができる.
テーマ1 日本書道史への視点
1.何を学ぶか
(1)歴史研究の方法とは
(2)美術史における「様式」の考え方
(3)鑑賞の3つの方法
(4)高村光太郎の鑑賞に学ぶ
2.学習到達目標
(1)書道史研究の特色について,概括的に説明することができる.
(2)作品の鑑賞の方法について,事例にもとづいて,具体的に説明することができる.
3.研究課題
(1)書道史研究の特色について,下記のキーワードを使って,まとめなさい.「仮説」「様式」「臨書」
(2)高村光太郎の鑑賞文(鑑賞1~3)について,3つの鑑賞の方法:直感的鑑賞・分析的鑑賞・総合的鑑賞を当てはめて,考察しなさい.
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ2 日本金石文と中国書法
1.何を学ぶか
(1)漢字の伝来と万葉仮名の発生
(2)仏教の伝来による書の発展
2.学習到達目標
(1)古墳時代以前の文字資料について,概括的に説明することができる.
(2)飛鳥時代の文字資料について,中国書法との関わりに言及しながら,概括的に説明することができる.
3.研究課題
(1)古墳時代から上代にかけての金石文に見られる漢字の書体と書風について,まとめなさい.
(2)万葉仮名の発生について,当時の文字資料を例として,順序立てて考察しなさい.
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ3 天平の書と中国書法
1.何を学ぶか
(1)上代の金石文字資料
(2)仏教文化と写経の盛行
(3)万葉仮名による日本語表記
(4)王羲之書法の受容
2.学習到達目標
(1)《多胡碑》などの石刻書風について,概括的に説明することができる.
(2)万葉仮名が広く行われるようになった状況について,正倉院文書等の当時の文字資料にもとづいて,概括的に説明することができる.
(3)王羲之書法の受容の状況について,当時伝来した摸搨本等により,具体的に説明することができる.
3.研究課題
(1)光明皇后《楽毅論》の書風について,当時における王羲之書法の受容と関連づけて,考察しなさい.
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ4 三筆と中国の書法
1.何を学ぶか
(1)遣唐使による唐文化の流入
(2)中唐の書における新旧の諸派
(3)「三筆」と空海書の多様性
2.学習到達目標
(1)空海の代表的な書作品を挙げて,その書風の特徴について具体的に説明することができる.
3.研究課題
(1)空海《風信帖》の書風について,徐浩や張従申等による中唐の書跡と関連づけて、説明しなさい.
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ5 三跡と「和様」
1.何を学ぶか
(1)国風文化の盛行と三跡の登場
(2)小野道風と「和様」の誕生
(3)仮名文における草仮名の使用
2.学習到達目標
(1)三跡それぞれの代表的な書作品を挙げて,各人の書の特徴について,具体的に説明することができる.
(2)平安時代中期の「和様」の書の成立とその特徴について,概括的に説明することができる.
3.研究課題
(1)小野道風の行書作品と藤原行成の行書作品とを比較しながら,和様の成立とその特徴について,考察しなさい.
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ6 平仮名の発生とその表現
1.何を学ぶか
(1)女手の発達
(2)《高野切》の成立と連綿の技法
2.学習到達目標
(1)平安時代中期の女手の発達について,具体的な作品例を挙げて,概括的に説明することができる.
(2)《高野切》の成立とその書としての特質について,具体的に説明することができる.
3.研究課題
(1)《高野切》の成立とその書としての特質について,下記のキーワードを使ってまとめなさい.「女手」「連綿」「古今和歌集」「寄合書き」
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ7 散らし書き・料紙の美
1.何を学ぶか
(1)紙背仮名消息と散らし書き
(2)散らし書きの技法と三色紙
(3)料紙と装丁形式
2.学習到達目標
(1)平安時代中期から後期にかけての,女手による「古筆」の技法について,具体的な例を挙げて説明することができる.
(2)料紙作成の技法と代表的な装丁形式について,具体的な例を挙げて説明することができる.
3.研究課題
(1)散らし書きの技法の発生と展開について,紙背仮名消息と三色紙を例として,考察しなさい。
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ8 和様の個性化と「墨跡」
1.何を学ぶか
(1)古筆の伝承筆者と系統的分類
(2)書流の展開と秘伝書
(3)「墨跡」と中国書法
2.学習到達目標
(1)名称に「伝」のついた古筆を例として,その名称と分類の意義について,概括的に説明することができる.
(2)「流」や「様」をもって語られる,代表的な書流と秘伝書について,概括的に説明することができる.
(3)「墨跡」の代表的な作例について,中国書法の影響に触れながら,具体的に説明することができる.
3.研究課題
(1)いわゆる「流儀書道」の功罪について,代表的な書流と秘伝書を例に挙げて,考察しなさい.
(2)「墨跡」の代表的な作例について,中国宋時代の書の影響に触れながら,まとめなさい.
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ9 光悦の人と作品
1.何を学ぶか
(1)町衆の文化と「嵯峨本」
(2)本阿弥光悦の作品とその新しさ
(3)大字仮名と「寛永の三筆」
2.学習到達目標
(1)本阿弥光悦の書作品,工房における制作という作品制作のあり方等について,概括的に説明することができる.
(2)近衛信尹の大字書など,書に様々な装飾的な工夫が施されたことを作品例にもとづいて説明することができる.
3.研究課題
(1)文化の中心的な担い手が町衆に移行したことによる,書の特質の変化について,説明しなさい。
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ10 和様書道と唐様書道
1.何を学ぶか
(1)和様書道と書の大衆化
(2)唐様書の流行と書論における実証主義の萌芽
2.学習到達目標
(1)唐様書道において,真跡を重視する考え方と法帖を重視する考え方が存在したことを,概括的に説明することができる.
3.研究課題
(1)真跡を重視する考え方と法帖を重視する考え方の両方の立場から,それぞれの所説をまとめなさい.
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ11 僧侶・画人・文人の書
1.何を学ぶか
(1)「逸脱派」の書
(2)良寛の書と明治期以降におけるその受容
2.学習到達目標
(1)当時の和様書道、唐様書道のいずれの流れにも関わらず、個性的な書を書き、後にその書が高く評価されている人々の書について、具体的に説明することができる.
3.研究課題
(1)良寛の書は,明治以降において画人・文人の間で高く評価されている.その理由について,評価する意見とともに考察しなさい.
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ12 幕末の三筆と六朝書道
1.何を学ぶか
(1)書家としての巻菱湖と市河米庵
(2)貫名菘翁における実証主義の展開とその評価
2.学習到達目標
(1)「幕末の三筆」の書作品について,実証主義の展開の観点から,具体的な作品例にもとづいて説明することができる.
(2)「明治の三大家」の書作品について,清朝からの新資料の流入等を踏まえて説明することができる.
3.研究課題
(1)貫名菘翁の書と学書の方法は,なぜ明治の識者から高く評価されたのか,考察しなさい.
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ13 学書理論と資料収集
1.何を学ぶか
(1)書壇の形成と競書雑誌
(2)比田井天来による学書理論の確立
(3)書道資料の収集と出版の盛行
2.学習到達目標
(1)比田井天来の学書理論のあらましを「実用書と芸術書」の観点から説明することができる.
(2)中村不折らによる書道資料の収集とその紹介について,出版された図書等から説明することができる.
3.研究課題
(1)競書雑誌による学書システムの功罪について,考察しなさい.
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ14 現代の書流と漢字仮名交じりの書
1.何を学ぶか
(1)現代書のジャンルと主な作品
(2)漢字仮名交じりの書の展開
2.学習到達目標
(1)現代書のジャンルと昭和期の主な書家の作品について,説明することができる.
3.研究課題
(1)漢字仮名交じりの書には「古典」がないといわれる.近現代の書家たちはその問題をどのように乗り越えようとしてきたのだろうか.討議してみよう.
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ15 まとめ ―書家の書と文人の書―
1.何を学ぶか
(1)高村光太郎の書と書論
(2)會津八一の書と書論
(3)書家の書と文人の書
2.学習到達目標
(1)書家の書と文人の書のそれぞれの特質について,説明することができる.
3.研究課題
(1)書芸術が、書家の書と文人の書に分離している現状を踏まえて、私たちはどのような立場で制作に向き合ったらよいのだろうか.討議してみよう.
4.プレゼン資料
5.動画資料
Ⅳ レポート課題
課題1 「テーマ1~5」の「研究課題」中から,もっとも興味を持った課題を1題選択して,解答してください。
※冒頭に「第〇講 課題 学籍番号 氏名」を書き,自分なりの「題名」を記してから,本文を書いてください。
※レポートは,wordで作成し,PDFファイルで提出のこと.分量は,A4:1枚程度.自分がもっとも適切と考える書式設定で作成してください.
課題2 「テーマ6~13」の「研究課題」中から,もっとも興味を持った課題を1題選択して,解答してください。
※冒頭に「第〇講 課題 学籍番号 氏名」を書き,自分なりの「題名」を記してから,本文を書いてください。
※レポートは,wordで作成し,PDFファイルで提出のこと.分量は,A4:1枚程度.自分がもっとも適切と考える書式設定で作成してください.
Ⅴ アドバイス
課題1解説 テーマ1の講義内容を踏まえて,自分の感じたことや考えたことを記述すること.
参考文献などを広く調べ,その結果を整理し,正しく引用して記述すること.
課題2解説 テーマ1の講義内容を踏まえて,自分の感じたことや考えたことを記述すること.
参考文献などを広く調べ,その結果を整理し,正しく引用して記述すること.
Ⅵ 科目修得試験:レポート試験
次の古典作品のうちから1点を選び,時代・筆者(作者)・内容・書風などの観点から,自分の鑑賞にもとづいて,作品論をまとめなさい.
空海書《風信帖》 藤原行成《白氏詩巻》 伝藤原行成《高野切第三種》 伝小野道風《継色紙》
※冒頭に自分なりの「題名」を記してから,本文を書いてください。
※レポートは,wordで作成し,PDFファイルで提出のこと.
分量は,A4:1枚程度.自分がもっとも適切と考える書式設定で作成してください.
Ⅶ テキスト
○古谷稔著『書道テキスト 第3巻 日本書道史』 2010 二玄社
○住川英明著『日本書道史』 2024 岐阜女子大学
Ⅷ 参考文献
○名児耶明監修『決定版 日本書道史』 2009 芸術新聞社
○名児耶明編『日本書道史年表』 1999 二玄社
○古谷稔著『漢字かな交じりの書』 1998 雄山閣
○古谷稔著『かなの鑑賞基礎知識』 1995 至文堂
○村上翠亭監修『平安かなの美』 2004 二玄社
○斎藤蒼青著『書道テキスト 第11巻 近現代名家の書』 2009 二玄社
○高木厚人著『書道テキスト 第9巻 かな』 2007 二玄社
○永原康史著『日本語のデザイン』 2002 美術出版社
○辻惟雄著『日本美術の歴史』 2005 東京大学出版会
○小松茂美編『日本書道辞典』 1987 二玄社
○書学書道史学会編『書道史年表事典』 2007 萱原書房
資 料
3.テキスト
【授業】日本語文章表現
Ⅰ はじめに
本科目では、基本的な語彙・文法から小論文の作成、学術的なレポートの書き方に至るまで、種々の表現方法を学び、多様な文章表現能力を高めることを目的としている。文章を通じて自己の考えを明確に伝え、論理的に説得する力は、学術的な場だけでなく、社会に出た後も必要とされる重要なスキルである。各課は、具体的な課題に沿って、学習を進める。各課で、対象となる文章の特徴や構成を理解し、実際に書くことを通じて学習を深める。また、批判的思考を養い、多角的な視点から情報を分析し、独自の考えを論理的に組み立てる訓練を行う。
Ⅱ 授業の目的・ねらい
本科目では、明確かつ説得力のある表現能力を習得し、論理的思考をもとにした文章を書くことを目的としている。講義を通じて、日本語の基本的な文法と用語を理解し、小論文や学術的なレポートの作成など、多様な文書を効果的に構成する技術を身につける。また、批判的思考と分析力を養い、継続的な自己改善に取り組むことで、学術的な場だけでなく、将来においても必要とされる表現能力を向上させる。
Ⅲ 授業の教育目標
本科目では、日本語の正確な使用、目的に応じた表現を深く理解し、場に応じて適切に使用できるようになることを目指す。学術的レポート・論文を書く場合は、様々なテキストや情報を批判的に分析し、自身の考えを効果的に、かつ論理的に一貫した文章で表現する能力を養うことを目標とする。さらに、自他の文章を客観的に評価できるようになることも目指す。また、他者からのフィードバックを受け入れることで、継続的に文章能力を向上させる。これらの目標を達成させることで、日本語の文章表現における高い理解と実践的なスキルを獲得し、学術的および社会のあらゆる環境で効果的にコミュニケーションを行う能力を身につける。
テーマ1 「ことばと表現を知ろう」
1.何を学ぶか
この課では、日本語の同音異義語や同訓異義語の違いを理解し、文脈に応じた適切な語彙選択の方法を学ぶ。また、
慣用表現、四字熟語、故事成語といった表現力豊かな語彙の使用法についても習得する。これらの学習を通じて、
豊かで正確な日本語表現の基礎を築く。
2.学習到達目標
・同音異義語、同訓異義語の違いを分析し、文脈に応じて適切に選択できるようになる。
・慣用表現、四字熟語、故事成語を使用した文章を評価し、適切な使用法を創造できるようになる。
3.研究課題
第1 課の範囲内の問題を解き、与えられた文章の中から同音異義語や同訓異義語を見つけ出し、その意味や背景に
ついて簡単なレポートを作成する。
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ2 「文の構造」
1.何を学ぶか
文の組み立てや文の構造の基本的な理解を深める。具体的には、主語と述語の関係、修飾語と被修飾語の関係、読
点・接続詞・副詞の用法、助詞の使い方を学び、効果的な文章の構築方法を習得する。これにより、より論理的で
読みやすい文章を書くための基礎を築く。
2.学習到達目標
・文の組み立てや構造を理解し、正しく使用できるようになる。
・既存の文章に対して、文の組み立てや構造を分析し、その効果を評価できる。
・最も効果的な文の組み立てや構造について考察し、自身の文章に応用できる。
3.研究課題
第1課のⅣ文の構造とⅤの助詞までの問題を解き、理解を深める。与えられた文章を分析し、文の構造や助詞の使い方を評価するレポートを作成する。このレポートでは、文の効果的な構造とその重要性について論じる。
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ3
1.何を学ぶか
日本語の敬語と敬意表現に焦点を当てる。学生は場面に応じた正しい敬語の選択、尊敬語・謙譲語・丁寧語の違いと使用法を理解し、実生活やビジネスシーンで適切な敬意を表現する方法を学ぶ。これにより、円滑で効果的なコミュニケーションが可能になる。
2.学習到達目標
・敬語、敬意表現を身につけ、様々な場面で適切に使うことができる。
・敬語、敬意表現の背景を分析し、特定の文脈での使用を評価できる。
3.研究課題
第3課に関連する問題を解き、敬語表現の理解を深める。与えられたシチュエーションに合わせて、適切な敬語や敬意表現を用いた文章を作成する。
テーマ4
1.何を学ぶか
小論文の目的と特徴を学ぶ。具体的には小論文とは何か、その目的、構成、書き方の基本について理解し、論説文や新聞の社説などを読んで小論文作成のための情報収集やテーマ選定の方法も学ぶ。
2.学習到達目標
・小論文の目的と特徴が理解できる。
・小論文の目的や特徴をもとに、新しいテーマや視点からの小論文の構想を考えることができる。
3.研究課題
論説文や新聞の社説などを読み、関心のあるテーマを探し、主張や論点を抽出し、それに対する自身の意見や考えをまとめる。
テーマ5
1.何を学ぶか
小論文の基本的な構成とその役割を学ぶ。学生は小論文の基本構成を理解し、効果的な論旨の進行を考える方法を習得する。具体的には導入部、本論、結論の各部分がどのように連携し、論旨を明確に伝えるかを学ぶ。
2.学習到達目標
・小論文の基本的な構成が理解できるようになる。
・小論文の基本構成を分析し、より効果的な論旨の進行を考案できるようになる。
3.研究課題
興味のあるトピックを一つ選び、そのトピックに関する文献や情報を調査し、小論文の下書きを作成する。
テーマ6
1.何を学ぶか
自分の考えや意見を筋道立てて説明する方法を学ぶ。具体的には、効果的な書き出しの文と結びの文の作成、読みやすい文章の構築方法、一貫性のある論証の進め方について習得する。
2.学習到達目標
・自分の考え、意見を筋道立てて説明できるようになる。
・効果的な書き出しの文と結びの文を用い、読みやすい文章を構築し、一貫性のある論証を進めることができる。
3.研究課題
小論文の草稿を書く。小論文の草稿をピアレビューに出す。
テーマ7
1.何を学ぶか
他者の論旨や意見を客観的に評価し、自身の小論文作成に応用する方法を学ぶ。具体的には、ピアレビューの方法と効果的なフィードバックの与え方を習得し、他者からの意見を取り入れて自己の小論文を改善する技術を身につける。
2.学習到達目標
・他者の論旨や意見を客観的に評価できるようになる。
・他者の小論文を評価し、正確に伝えるとともに、自身の小論文作成に応用できる。
3.研究課題
他の受講生の小論文の論点や根拠を分析し、それに対する意見や評価をまとめる。受け取ったフィードバックをもとに、自分の小論文を改善する。
テーマ8
1.何を学ぶか
自己紹介を通じて自分をアピールする方法を学ぶ。自己アピールの重要性と目的を理解し、強みやスキル、経験を
効果的に伝える自己分析方法について習得する。さらに、他者の自己紹介を分析し、効果的な自己アピールの要素や方法を探し出す。
2.学習到達目標
・自分をアピールする自己紹介ができるようになる。
・他者の自己紹介を分析することによって、効果的な自己アピールの要素や方法を探し出せるようになる。
3.研究課題
自分の強みやスキル、経験をリストアップし、それをもとに900字程度の自己アピール文を書く。他の受講生の自己アピール文を読み、改善点などをコメントし、ルーブリック評価を行う。
テーマ9
1.何を学ぶか
聞き手や読み手を分析し、効果的な自己アピールを行う方法を学ぶ。具体的には、話す場面や書く場面での自己アピールのポイントと、聞き手や読み手の視点を考慮したアピール方法について学ぶ。
2.学習到達目標
・聞き手や読み手を分析し、効果的な自己アピールを行うことができる。
・他の受講生の自己アピールに対して、その内容の強みや改善点を分析し、具体的な提案や意見を述べることができる。
3.研究課題
他の受講生の自己アピール文を読み、その内容の強みや改善点について分析し、具体的な提案や意見をまとめる。
自分自身の自己アピール文を作成し、ピアレビューを通じてフィードバックを受け、内容を改善する。
テーマ10 「学術的文章の書き方」
1.何を学ぶか
学術的文章と文学的文章の違い、小論文・レポート・論文の特徴と要点を学ぶ。学術的な文章の書き方の基本を理解し、自らの研究や考察を明確かつ効果的に伝えるための文章構成を学ぶ。
2.学習到達目標
・学術的文章と文学的文章の違いが理解できる。
・小論文、レポート、論文の特徴や要点を分析し、それぞれに適した文章を書くことができる。
3.研究課題
興味あるトピックを一つ選び、自由に作文する。同じトピックを学術的文章で書くための分析、研究し、簡単なレポートを作成する。
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ11 「分析と考察をしよう」
1.何を学ぶか
グラフや表を正しく理解し、データを根拠に客観的な結論を述べる方法を学ぶ。また、データをもとに新しい仮説や考察を生み出すことにも焦点を当てる。データの理解と分析に必要なスキルを習得し、具体的な研究や議論に応用する。
2.学習到達目標
・グラフや表について正しく理解できるようになる。
・データを根拠にして、結論を客観的に述べることができる。
・データをもとに、新しい仮説や考察を生み出せるようになる。
3.研究課題
与えられたデータやグラフを用いて、事実や傾向を分析し、その結果をもとに簡単なレポートを作成する。
ステップ2とステップ3の問題から最低2問ずつ選び、それに対する詳細な説明と考察を行う。
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ12 「論文の書き方(1)リサーチと情報収集の基礎」
1.何を学ぶか
リサーチと情報収集の基礎を学ぶ。効果的なリサーチ方法を習得し、信頼性のある情報源を見分ける方法を理解する。また、収集した情報をもとに新しい研究テーマや仮説を考える技術についても学ぶ。
2.学習到達目標
・リサーチと情報収集を行うことができる。
・信頼性のある情報源を見分けることができる。
・収集した情報をもとに新しい研究テーマや仮説を考えることができる
3.研究課題
興味のあるトピックに関する最新の研究や文献を調査し、その中から主要な論点や議論を抽出する。
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ13 「論文の書き方(2)論点の設定と論証の技術」
1.何を学ぶか
明確な論点の設定と強固な論証の技術を学ぶ。情報や知識をもとに新しい論点や視点を創出し、複数の情報源やデータを統合して論証を構築する方法について理解する。
2.学習到達目標
・情報や知識をもとに、新しい論点や視点を創出できるようになる。
・複数の情報源やデータを統合して、強固な論証が行えるようになる。
3.研究課題
トピックに関する既存の意見や論文を分析し、それらの中から新しい視点や論点を提案する。
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ14 「論文の書き方(3)引用の仕方」
1.何を学ぶか
異なる情報源からの情報を分析し、適切な引用の仕方を選択する方法を学ぶ。直接引用と間接引用の違い、引用時のルールや形式、参考文献の書き方などを理解することが目標である。
2.学習到達目標
・異なる情報源からの情報を分析し、適切な引用方法を選択できるようになる。
・情報を適切に評価し、その情報が論証にどれほど貢献するかを判断できる。
3.研究課題
任意のトピックについて、適切に引用をしながら、論の展開をする。形式を整えたレポートを作成する。
4.プレゼン資料
5.動画資料
テーマ15 「論文の書き方(4)総まとめとフィードバック」
1.何を学ぶか
レポートや論文の構造や内容を総合的に評価し、他者からのフィードバックを受け入れて自らの論証をより高いレベルに再構築する方法を学ぶ。
2.学習到達目標
・レポートや論文の構造や内容を総合的に評価し、その強みや弱みを明確に認識できるようになる。
・他者の意見やフィードバックを受け入れ、自らの論証をより高いレベルに再構築できるようになる。
3.研究課題
他の受講生のレポートを詳細に分析し、その論点や論拠、構成について評価や提案をまとめる。自らもフィードバックを受けて、改善したレポートを作成する。
4.プレゼン資料
5.動画資料
Ⅳ レポート課題
課題1
課題2
Ⅴ アドバイス
課題1解説
課題2解説
Ⅵ 科目修得試験:レポート試験
Ⅶ テキスト
米田 明美・山上 登志美・藏中 さやか(2010)『大学生のための日本語表現実践ノート 改訂版』風間書房
Ⅷ 参考文献
石黒圭(2012)『この1冊できちんと書ける!論文・レポートの基本』日本実業出版社
渡邊淳子(2015)『大学生のための論文・レポートの論理的な書き方』研究社
資 料
1._e-Learning科目ガイドブック(日本語文章表現)
3.大学教育推進e-Learningテキスト(日本語文章表現)