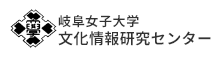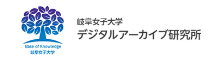【公開講座】デジタルアーカイブ in 岐阜 2025
【公開講座】デジタルアーカイブ in 岐阜 2025
「Multi Campus One Digital University」
いつでもどこでも学習できるオンデマンドな学習環境
日 時:2026年2月11日(水・祝日)9:00~12:00
募集期間:令和7年11月1日(土)~ 令和8年1月31日(土)
会 場:オンライン講座+e-Learning(オンデマンド講座)
主 催:岐阜女子大学教育推進会議
岐阜女子大学デジタルアーカイブ研究所
後 援:日本デジタルアーキビスト資格認定機構、日本教育情報学会、デジタルアーカイブ学会(予定)
受講対象:社会人
チラシ:
お申し込みフォーム: 申し込みフォーム
セッション① AI(人工知能)講座 【データサイエンスから見える新たな学びの未来】
■ 対面講座(オンライン)【2026年2月11日(水・祝日)9:00~12:00】
【スケジュール】
-
9:00 挨 拶
村瀬 康一郎氏(岐阜女子大学・教授)
-
9:10~10:00 教育とデータサイエンス
成瀬 喜則氏(富山大学・名誉教授)

プレゼン資料
-
10:10~11:00 学びのプロセスの可視化と学力
山本 朝彦氏(横浜国立大学大学院教育学研究科・教授 )
-
11:10~12:00 AIと共に生きる時代における教育と研究へのAI活用
藤吉 弘亘氏(中部大学AI数理データサイエンスセンター・教授)

■ e-Learning(オンデマンド講座)
AI(人工知能)概論【Ⅱ】~ データサイエンスから見える新たな学びの未来像 ~
【概 要】
本講座は、教育現場においてデータサイエンスの基本的な知識とスキルを身につけ、実践的に活用できるように設計された教材です。データの収集・整理・分析・可視化の基本的な手法から、教育データの具体的な活用例、さらにデータ倫理やプライバシーの重要性まで幅広く解説します。教員が日常の授業や学校運営において、データを効果的に活用し、より良い教育環境を構築するための基礎知識と実践力を養うことを目的としています。データリテラシーの向上により、教育の質の向上や、個別最適化された指導、教育政策の立案にも寄与できる人材育成を目指します。
【学修到達目標】
① データサイエンスの基本的な概念と用語を理解し、説明できる。
② 教育現場で扱うデータの種類や収集方法、整理の基本的な手法を理解し、実践できる。
③ 基本的な統計分析やデータの可視化技術を用いて、教育データから有益な情報を抽出できる。
④ 教育データの活用例や事例を理解し、自校や授業に応用できるアイデアを持てる。
⑤ データの倫理やプライバシーに関する基本的な考え方を理解し、適切に対応できる。
■具体的内容
| No | テーマ | 講 師(敬称略) |
| 第1講 | データサイエンスとは何か | 白水 始(国立教育政策研究所教育データサイエンスセンター 副センター長) |
| 第2講 | データの種類と収集方法 | 尾関智恵(岐阜大学航空宇宙生産技術開発センター・ 准教授) |
| 第3講 | データの前処理とクリーニング | 笹山和明(株式会社 村田製作所・情報科学アーキテクト) |
| 第4講 | データの可視化と探索的データ分析(EDA) | 荒木貴之(日本経済大学/ 社会構想大学院大学・教授) |
| 第5講 | 統計学の基礎 | 尾関智恵(岐阜大学航空宇宙生産技術開発センター・准教授) |
| 第6講 | 機械学習の基本概念 | 澤井 進(岐阜女子大学・特任教授) |
| 第7講 | 回帰分析と分類モデル | 笹山和明(株式会社 村田製作所・情報科学アーキテクト) |
| 第8講 | クラスタリングと次元削減 | 小松尚登(滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター・助教) |
| 第9講 | データサイエンスにおけるプログラミング基礎 | 小松尚登(滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター・助教) |
| 第10講 | 自治体が実施する大規模学力・学習状況調査とその分析 | 山川喜葉(埼玉県教育局市町村支援部・義務教育指導課長) |
| 第11講 | データの倫理とプライバシー | 芳賀高洋(岐阜聖徳学園大学・教授) |
| 第12講 | データサイエンスの実践的応用例 | 成瀬喜則(富山大学・名誉教授) |
| 第13講 | データ可視化の高度な技術 | 荒木貴之(日本経済大学/ 社会構想大学院大学・教授) |
| 第14講 | AIと深層学習の基礎と応用 | 藤吉弘亘(中部大学AI数理データサイエンスセンター・教授) |
| 第15講 | データサイエンスの未来と教育への展望 | 澤井 進(岐阜女子大学・特任教授) |
セッション② デジタルアーキビスト講座 【デジタルアーカイブにおける新たな価値創造】
■ 対面講座(オンライン) 【 2026年2月11日(水・祝日)9:00~12:00 】
【スケジュール】
-
9:00 挨 拶
江添 誠氏(岐阜女子大学・准教授)
-
9:10~10:00 VRからデジタルエンターテインメントへ
廣瀬 通孝氏(東京大学・名誉教授)
プレゼン資料
-
10:10~11:00 戦災・災害のデジタルアーカイブ(仮題)
渡邉 英徳氏(東京大学・教授)
参考資料
東京大学基金「戦災・災害のデジタルアーカイブ基金」の関連動画
-
11:10~12:00 考古学調査における3次元デジタルアーカイブ
江添 誠氏(岐阜女子大学・准教授)
■ e-Learning(オンデマンド講座)
デジタルアーカイブ概論【Ⅱ】 ~ デジタルアーカイブにおける新たな価値創造 ~
【概要】
デジタルアーカイブは,さまざまな分野で必要とされる資料を記録・保存・発信・評価する重要なプロセスである.このデジタルアーカイブは,わが国の知識基盤社会を支えるものであり,デジタルアーカイブ学会でも,デジタルアーカイブ立国に向けて「デジタルアーカイブ基盤基本法(仮称)」などの法整備への政策提言を積極的に行っている.今後,知識基盤社会おいてデジタルアーカイブについて責任をもって実践できる専門職であるデジタルアーキビストが必要とされている.ここでは,デジタルアーキビストの学術的な基礎として,デジタルアーカイブに関する歴史から我が国の動向並びにデジタルアーカイブの課題を学ぶ.また,この内容は,今後の学修におけるデジタルアーキビストの学びの地図となる.
【学修到達目標】
① 日本の目指す知識基盤社会を支えるのはデジタルアーカイブといっても過言ではありません.初期の文化遺産を中心とした展示やウェブ公開など提示中心から,いかに社会の全領域で知的生産やナレッジマネジメントに活用できるインターフェイス,横断的ネットワークなどの環境を確保するかの段階に入ったといえます.
② ここでは,15のテーマに基づいて,それぞれのテーマの中に研究課題を設定し,また,各講に学修到達目標を設定し,個々に学修の到達を確認することができる.
■具体的内容
| No | テーマ | 講 師(敬称略) |
| 第1講 | デジタルアーカイブの歴史とその課題 | 久世 均(岐阜女子大学デジタルアーカイブ研究所長・教授) |
| 第2講 | デジタルアーカイブプロセス | |
| 第3講 | 知のデジタルアーカイブ | |
| 第4講 | デジタルアーカイブの構築・連携のためのガイドライン | |
| 第5講 | 知の増殖型サイクルの情報処理システムの構成 | |
| 第6講 | 知の増殖型サイクルの知的処理と流通システム | |
| 第7講 | 知の増殖型サイクルを支えるメタデータの構成 | |
| 第8講 | 我が国におけるデジタルアーカイブ推進の方向性 | |
| 第9講 | デジタルアーカイブの構築・共有・活用ガイドライン | |
| 第10講 | 知的財産推進計画に見るデジタルアーカイブ | |
| 第11講 | 地域資源デジタルアーカイブによる知の拠点の形成 | |
| 第12講 | 知の拠点形成のための基盤整備 | |
| 第13講 | デジタルアーカイブにおける新たな評価法 | |
| 第14講 | デジタルアーカイブを活用した地域課題の解決手法 | |
| 第15講 | 首里城の復元とデジタルアーカイブの可能性 |
セッション③ 学校DX戦略コーディネータ講座 【未来を創る教育設計~カリキュラム開発の新しい視点~】
■ 対面講座(オンライン講座) 【 2026年2月11日(水・祝日)9:00~12:00 】
【スケジュール】
-
9:00 挨 拶
齋藤 陽子氏(岐阜女子大学・准教授)
-
9:10~10:00 国際的な視点から見た教育のあり方について
白井 俊氏(東京科学大学・副学長)
-
10:10~11:00 日本の学校カリキュラムの歴史と概要
安彦 忠彦氏(名古屋大学・名誉教授)

プレゼン資料
-
11:10~12:00 カリキュラムの評価と改善
高口 努氏(岐阜女子大学・学長)
プレゼン資料
■ e-Learning(オンデマンド講座)
学校DX戦略コーディネータ(Ⅲ) 未来を創る教育設計 ~ カリキュラム開発の新しい視点 ~
【概 要】
カリキュラム開発の理論と実践は、教育における目標達成のために必要な学習内容、教育方法、評価方法を体系的に設計・実行するプロセスです。理論的には、カリキュラム開発は学習者中心のアプローチを重視し、学習の目的や成果を明確に定義します。加えて、学習者のニーズ、社会的・文化的背景、教育政策を考慮した柔軟で効果的なデザインが求められます。実践的な側面では、カリキュラムを教室で実際に運用し、評価を通じてその効果を確認し、改善を行うことが重要です。
カリキュラム開発のポイントは、学習者の多様性に対応すること、学びの過程が段階的に進行すること、そして、評価とフィードバックを取り入れた反復的な改善が必要であることです。さらに、現代の教育では、テクノロジーやグローバルな視点、持続可能な教育など、最新のアプローチを取り入れることが求められています。これにより、学習者は知識だけでなく、実践的なスキルや問題解決能力を身につけることができます。カリキュラム開発は、単なる知識伝達にとどまらず、学習者を未来に向けて準備させる重要な役割を果たします。
【学修到達目標】
① 学習者中心のカリキュラム設計ができる
学習者のニーズ、興味、能力に基づいて、効果的な学習目標と内容を設定し、カリキュラムを設計できる。
② カリキュラム開発における評価手法を理解し、実践できる
カリキュラムの評価方法を選定し、実施して、その成果を分析し、改善のためのフィードバックを提供できる。
③ 多様な教育手法や学習スタイルを取り入れたカリキュラムを作成できる
さまざまな学習者に対応した教育方法(例:協働学習、プロジェクトベース学習、反転授業)を取り入れたカリキュラムを設計できる。
④ 最新の教育技術をカリキュラムに組み込み、効果的に活用できる
テクノロジーやデジタルツールを活用したカリキュラムを開発し、学習者にとって効果的な学習環境を提供できる。
⑤ カリキュラムの改善と適応を行い、持続的に最適化できる
実施したカリキュラムを評価し、学習者の成果やフィードバックを基にカリキュラムを柔軟に修正・改善できる。
■具体的内容
| No | テーマ | 講 師(敬称略) |
| 第1講 | カリキュラムの定義と重要性 | 森下 孟(信州大学学術研究院教育学系・准教授) |
| 第2講 | 日本の学校カリキュラム開発の歴史と概要 | 安彦忠彦(名古屋大学・名誉教授) |
| 第3講 | 教育理論とカリキュラム | 田中康平(教育ICTデザイナー) |
| 第4講 | 学習者中心の授業デザイン ~デジタル学習基盤を前提に~ | 木田 博(鹿児島市教育委員会・教育DX担当部長) |
| 第5講 | 目標設定と学習成果 | 齋藤陽子(岐阜女子大学・准教授) |
| 第6講 | 内容の選定と組織化 | 今井亜湖(岐阜大学・教授) |
| 第7講 | 教育方法と戦略 | 林 一真(岐阜聖徳学園大学・講師) |
| 第8講 | 学習評価とフィードバックの重要性 | 森下 孟(信州大学学術研究院教育学系・准教授) |
| 第9講 | インクルーシブ教育とカリキュラム | 太田容次(京都ノートルダム女子大学・准教授) |
| 第10講 | テクノロジーの活用 | 田中康平(教育ICTデザイナー) |
| 第11講 | プロジェクトベースの学習 | 成瀬喜則(富山大学・名誉教授) |
| 第12講 | 学力の可視化と授業改善(仮題) | 丹羽正昇(横浜市教育委員会・学校教育部長) |
| 第13講 | 教育デジタルトランスフォーメーション | 金城寛史(沖縄県教育庁教育DX推進課・指導主事) |
| 第14講 | 教科の構造化とカリキュラムの再設計 | 岩木美詠子(福岡市立香椎第1中学校・教頭) |
| 第15講 | 知識の構造化とカリキュラム | 益川弘如(青山学院大学・教授) |
資料: