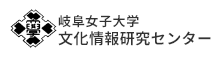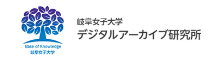【公開講座】デジタルアーキビスト講座 ~ デジタルアーカイブの起源と未来 ~
【公開講座】デジタルアーキビスト講座 ~ デジタルアーカイブの起源と未来 ~
趣 旨:
デジタルアーキビストとは,文化・産業資源等の対象を理解し,著作権・肖像権・プライバシー等の権利処理を行い,デジタル化の知識と技能を持ち,収集・管理・保護・活用・創造を担当できる人材のことをいいます。
ここでは、デジタルアーキビスト資格と絡め知的財産人材の育成を行います。
プログラム:
1.「なぜ、デジタルアーカイブなのか? 地域創成とデジタルアーカイブ活用」
吉見俊哉氏(國學院大學教授・東京大学名誉教授)
動 画
資 料
内 容
1. メディアの歴史とデジタルアーカイブの登場
1.1. コミュニケーションの根源とメディアの誕生
人類の歴史において、ホモサピエンスが生き残った主要な理由は、比較的大きな集団でコミュニケーションをする動物だったことにあります。初期のコミュニケーションはジェスチャーや声によるもので、これらは身体的行為であり、まだメディアは存在しませんでした。メディアが誕生したのは、壁画や楽器の使用からであり、これは人間の身体的行為の技術的な拡張と言えます。そして、文字の発明は、コミュニケーション能力を決定的に変える転換点となりました。ロゼッタストーンはその象徴であり、異なる文字で同じメッセージを記録することで、古代文明の解読が大きく進んだ事例として紹介されました。
1.2. 時間性のメディアと空間性のメディア
カナダのトロント大学の学者ハルド・イニスは、人類史におけるメディアを二種類に分類しました。
時間性のメディア: 書かれたメッセージを、書き手が死んだ後も長い時間、継承・伝達していくメディア(例:石碑)。
空間性のメディア: ある情報を遠くの人に伝える、軽くて持ち運びしやすいメディア(例:パピルス、手紙)。
人類の歴史は、この二種類のメディアが共存しながら発展してきました。現代社会に当てはめると、インターネットは主に空間性のメディアであり、ネットワーク的に情報を共有する「集合知」を形成します。一方、デジタルアーカイブはまさに時間性のメディアであり、過去の記憶や知識を継承し、新しい知識を生み出す「記憶知」としての役割を担います。
1.3. メディア革命と知能の機械化
近代のメディア史における決定的な転換点は、15世紀半ばのグーテンベルクによる活版印刷の発明でした。これにより、同じ情報や知識が大量に複製・伝達されるようになり、近代社会の基礎を築きました。活版印刷は、情報の空間的・時間的な拡張を可能にしました。
さらに、メディア革命は2回起こったと指摘されました。
19世紀末から20世紀初頭: アナログ革命
蓄音機、電話機、映写機、ラジオ、放送ネットワークなどが生まれ、人間の視覚や聴覚を時間的・空間的に無限に拡張しました(例:映画、テレビ)。
20世紀末から21世紀: デジタル革命
コンピューターとインターネットの発展により、人間の視聴覚だけでなく、知能そのものを機械化する段階へと進みました。これは現在のAIの発展につながっています。
1.4. コンピューターの進化と記憶・更新の融合
コンピューターは、当初は純粋な計算機でしたが、やがてパーソナルコンピューターの普及とともに、人々が書いたものや写真を記憶し、再生する装置へと変化しました。そして1990年代にインターネットが爆発的に発展すると、コンピューターは情報を記憶するだけでなく、人々が遠隔地と更新(やり取り)する機械へと進化しました。
現在のAIは、この「記憶する」機能と「更新する」機能が融合したものです。人々が蓄積した記憶情報に基づいて、ディープラーニングを通じて対話する能力を持つようになりました。しかし、この記憶と更新の融合はAIに留まらず、私たちがデジタルで記憶したものをネット社会でいかに共有していくかという問い、すなわちデジタルアーカイブの問いへと繋がっていくと述べています。
2. デジタルアーカイブの定義と現代社会における意義
2.1. アーカイブの歴史的変遷と権力との関係
アーカイブの要件は以下の通りです。
歴史的記録の集積: 個人や組織がその存続期間を通じて生み出した一時的記録の総体。
唯一性: 図書館が複製された本を収集するのに対し、アーカイブは基本的に複製されない唯一性を持つ資料が中心。
アーカイブの概念は古代ギリシャに遡り、「アルコンの住まい」、すなわちポリスの最高統治者(権力者)の家を意味しました。権力者は記録を管理することで支配を行使したため、アーカイブは当初から**権力者の「全てを見渡す権力」**と深く結びついていました。古代中国、ギリシャ、中世ヨーロッパにおいて、アーカイブの中心は常に権力側(宮廷や修道院)でした。
この構図が劇的に転換したのがフランス革命です。王権から権力が奪われたことで、アーカイブは王のアーカイブから国民のアーカイブへと大きく転換し、「ナショナルアーカイブ」のシステムが各国で発展しました。日本においては、このような国民のアーカイブという意識や仕組みが十分に発達してこなかったことが大きな問題であると指摘されました。
2.2. デリダのアーカイブ論と知識の二側面
フランスの哲学者ジャック・デリダは、著書『アーカイブの病』の中でアーカイブには二側面あると議論しました。
掟としてのアーカイブ: 権力者が記録を管理し、権力を掌握する側面。
始まりとしてのアーカイブ(生成としてのアーカイブ): 新しい知識や創造が生まれる場としての側面。
これをより分かりやすく説明するために、「形式知」と「暗黙知」という知識の形式が持ち出されました。
形式知: 言葉によって書かれ、記録として残された知識(例:オーラルヒストリー、個人文書、論文など)。図書館や文書館に収められるのはこの形式知が中心。
暗黙知: 言葉にならない、あるいは断片的ながら、あらゆる知識の源となる知識(例:日常会話、会議中のメモ、試行錯誤のプロセス)。
知識は、暗黙知レベルの無数のコミュニケーションの中から生まれ、最終的に形式知として記録されます。この循環がアーカイブのプロセスの中に常に存在していると説明されました。
2.3. デジタル革命によるアーカイブの変革
20世紀末から21世紀にかけてのデジタル革命は、アーカイブのあり方を劇的に変えました。
境界の消失:
文書館と図書館の区別: 活版印刷以降、複製された書籍を収蔵する図書館と、唯一性を持つ原資料を収蔵する文書館は明確に区別されていました。しかし、デジタル化により、文書も本もスキャンされれば無限に複製可能になり、両者の区別が意味を失いました。
アーカイブ機関間の境界: 図書館、文書館、博物館、美術館といった従来の制度的な境界線が、デジタル化によって溶解しました。デジタルデータとしては全て同じ形式で保存可能になったため、それぞれの機関に属さない写真、映画、録音テープ、設計図などの「文化的な資産」も全てデジタルアーカイブとして蓄積可能になりました。これは、全ての壁が溶解した先にデジタルアーカイブが登場したことを意味します。
制作プロセスのアーカイブ化:
これまで図書館やミュージアムは最終的な完成品を収蔵する施設でしたが、デジタル化により、暗黙知から形式知へと至る**知識や作品の「制作プロセス全体」**もデジタル形式で記録・収蔵可能になりました。これにより、アーカイブは単なる完成品の保管庫ではなく、新たな知的創造の場として再定義されつつあります。フィンランドのヘルシンキ中央図書館は、音楽スタジオや3Dプリンター工房などを併設し、制作プロセス全体をアーカイブ化している未来型の図書館として紹介されました。
このことから、デジタルアーカイブは、行政文書の保存・公開といった公的記録の集積庫としての従来の役割に加え、美術館、博物館、図書館の要素を取り込み、さらにこれまで取りこぼされてきた様々な文化資産(録音、写真、映像、電子データ、オーラルヒストリー、行動履歴など)をも記憶する装置として、公的な場の組織のあり方を問い直していると述べられました。
2.4. 日本社会の「痴呆症」とデジタルアーカイブの必要性
しかし、日本の現状は芳しくありません。フランスの国立映像研究所INAがほぼ全ての放送映像・録音資料を収蔵し公開しているのに対し、日本のNHKアーカイブスは大量のデジタルデータを修蔵しているものの、そのアクセスはNHK職員に限定されており、完全には開かれていません。
現代社会は、インターネットとSNSの発展により、個人の発信や様々な情報(マーケティング、医療情報など)が爆発的に膨らみ、「記憶の海」の中にいます。この情報過多の中で、フェイクニュース、フィルターバブル、ポストトゥルース、炎上、ポピュリズムといった問題が顕在化しています。
日本は特にこの問題が深刻です。過去を蓄積してこなかったため、**「痴呆症」**のような状態に陥っていると指摘されました。日本は常に「次の新しい動き」(マルチメディア、ビッグデータ、ソサエティ5.0、AIなど)に飛びつく「キャッチアップ型」の国であり、過去の蓄積に対して非常に不十分な姿勢をとってきました。公文書の改ざんすら行われる現状は、その根深い問題を象徴しています。過去から学べず、過去を知らない社会になっていると警鐘を鳴らしました。
この「痴呆症」は日本に限らず、インターネット社会が拡大する中で世界中に広がっている現象です。過去の記録を「巨人の肩」と見立て、その上に乗って初めて未来が見えるにもかかわらず、多くの社会は現在や未来のことばかり考えて空回りしていると述べました。
3. デジタルアーカイブの推進と「記憶する権利」
3.1. 縦軸としてのデジタルアーカイブ:「歴史のコモンズ」の構築
現代のネット社会は、情報が空間的に爆発的に広がる「集合知」の社会ですが、同時に「忘却の社会」でもあります。この横軸の広がりに対し、不足しているのが「縦軸」、すなわち**記憶する仕組み(記録知)**です。
近代社会では、図書館、博物館、美術館、文書館といった機関がこの縦軸の役割を担ってきましたが、デジタル化によってそれらがボーダーレス化し、爆発的に広がる可能性を秘めているにもかかわらず、それに対応するアーカイブの仕組みが整備されていません。この縦軸の仕組みが整備されれば、横軸に広がる情報やニュースの真偽を検証したり、過去の出来事をアーカイブの中で再検証したりすることが可能になり、「歴史のコモンズ」が形成されると述べました。
3.2. 日本におけるデジタルアーカイブの歩み
「デジタルアーカイブ」という言葉は和製英語であり、日本では1990年代初頭から尾崎紀男氏らが提唱しました。当時は、文化資産をデジタル化し、データベース化して保管し、ネットワークで発信する仕組みと定義されていました。アレクサンドリア図書館の再建計画や、米国のNII構想、G7での電子博物館構想など、国際的な動きと連動していました。
日本は、デジタル化やインターネット社会のビジョン、実証実験において、韓国や台湾、中国よりも早い時期から取り組んでいました。しかし、日本の社会の決定的な問題は、それらが制度化されたり、社会全体を変えるところまで至らなかったことです。部分的な新しい試みは行われるものの、予算がつかず忘れ去られ、社会全体の構造改革には繋がらないという問題を抱えています。デジタルアーカイブも同様で、90年代初頭に提唱されたものの、2000年代には忘れ去られ、一部の細々とした取り組み(文化遺産オンラインなど)が行われるに留まりました。
しかし、2010年代に入り、「このままではいけない」という意識が生まれました。1994年に長尾真氏(国立国会図書館館長、京都大学総長)が提唱した「電子図書館アリアドネの構想」が全く実現されていないことに危機感を抱き、2014年には「アーカイブ立国宣言」を発表しました。
3.3. アーカイブ立国宣言とデジタルアーカイブ学会の活動
アーカイブ立国宣言では、以下の4つの目標が掲げられました。
国立デジタルアーカイブセンターの設立
デジタルアーカイブを支える人材育成の仕組みの構築
文化資源のデジタルアーカイブのオープンデータ化
根本的な孤児作品(著作権者が不明な作品)の利用可能化対策
これらの実現を阻む「人、法、お金」の三つの壁を突破するための議論が行われました。その継続として、2015年にはアーカイブサミットが開催され、著作権とパブリックドメインのバランス、クリエイティブなアーキビストの育成、アーカイブの標準化・横断化・公開化、そしてそれらのハブとしての国立デジタルアーカイブセンターの設立が目標とされました。
これらの目標実現のため、様々な組織が設立されました。
デジタルアーカイブ学会: 現在会員数800人を超える主要な学術団体。
デジタルアーカイブ推進コンソーシアム(DAPCON): 凸版印刷、DNP、テラタコクといった企業との産学連携組織。
デジタルアーカイブ研究機関連絡会: 博物館、美術館、図書館といった連携機関。
デジタルアーカイブ推進議員連盟: 国会への働きかけのための組織。
学会の役割として、学術発表・交流の場、研究テーマの推進、社会問題への声明発表に加え、「学術的知見に基づき世界的な理念を提起する」ことを挙げ、その柱として「デジタルアーカイブ憲章」を提唱すべきだと述べました。
3.4. デジタルアーカイブ憲章:「記憶する権利」の提唱
「チャーター(検証)」とは、古くはマグナ・カルタ(13世紀、王権の制限と諸侯・都市の自由を認めた英国憲法の原点)に始まり、人民憲章(19世紀、普通選挙運動)、世界労働憲章、国連人権憲章など、市民や民衆が国家や権力に対して、あるべき制度を求める「下からの憲法」のようなものだと説明されました。
松尾氏は、このチャーターの概念がデジタルアーカイブにも必要だと主張します。デジタル革命以前のマスメディア社会では、情報公開とプライバシーの対立が常に議論されてきました。しかし、ネット社会に移行した今、一方では忘れられる権利(個人の情報がいつまでもネット上に残りハラスメント状態になることを防ぐ)が必要であると同時に、他方で社会には「記憶する権利」があるはずだと訴えました。
「記憶する権利」とは、何が実際に起こったのかがデジタル社会で分からなくなることを防ぎ、市民一人ひとりの個人や地域社会、公的機関、国家に至るまで、その記憶を社会の記憶として蓄積する仕組みが整備されるべきであるという考え方です。これにより、アーキビストは「市民の記憶する権利を媒介する媒介者」として再定義されるべきだと述べました。
デジタルアーカイブ学会は、この考え方に基づいて「デジタルアーカイブ憲章」を定めています。その基本理念は、「市民生活を豊かにする公共的知識基盤には、信頼性があり、知識や情報が構造化・体系化されており、ユニバーサル化により言語的・社会的障壁がなく、ネットワーク化により恒常的に効率よくアクセスできる仕組みが必要である」としています。
そして、「記憶する権利」をその根本理念とし、プライバシーや知的財産権に配慮しつつ、過去および現在の知識や情報を記録し、社会に残し、未来に継承する仕組みを整える必要性を強調しました。
デジタルアーカイブ憲章の具体的な行動指針として、以下の項目が挙げられました。
デジタルアーキビストの使命: 提供者と活用者を含む幅広い主体の声を聞き、主体的な参加を促す。情報資産をオンラインで公開し、再利用可能な条件を設定し、相互利用しやすい技術を整える。
社会制度の整備: 方針・計画の策定・見直し、適切な法整備と財政的措置を働きかける。
信頼性の確保: データの由来や改変履歴が把握できるトレサビリティの仕組みやメタデータの充実を促す。
体系性の確保: FAIR原則に基づき、収集した情報資産を構造化・体系化し、誰でも利用しやすい形に整理・提供する。
恒常性の保証: デジタル資源の長期保存とアクセスを保証するためのコミュニティ基盤を構築する。
ユニバーサル化: 多言語による情報発信や国際標準への対応を図り、グローバルに活用できる情報資産を発信する。様々なアクセス障害のある人々による活用を促す。
ネットワーク構築: 情報資産の横断的・国際的なネットワーク構築を図り、地域・分野・官民セクターごとの取り組みを横断的につなげる拠点を構築する。
活用促進: 研究者、エンジニア、企業などに対し必要な情報を提供し、人と情報資産を結びつける。あらゆる年代でデジタルアーカイブを用いた学習機会を増やす。
人材養成: デジタルアーカイブに関わる多様な知識を有する人材を育成する場を設ける。
吉見氏は、この「記憶する権利」を日本社会に確立していくことが、現在の「痴呆症化した社会」を立て直すために不可欠であると強調し、講演を締めくくりました。
(文責:久世)
2.「『デジタル時代のアーカイブ系譜学』~アーカイブの概念史~」
加藤 諭氏(東北大学学術資源研究公開センター 史料館 教授)
動 画
資 料
内 容
1. デジタル時代のアーカイブ系譜学を論じる意義
1.1. アーカイブの普及と多様化
現在、**「アーカイブ」**という言葉は、NHKアーカイブス、YouTubeのアーカイブ機能、市民団体や非営利組織の名称など、多岐にわたる場面で使われ、多くの人々に語られるようになりました。これは、デジタル化されたテキスト、音声、画像、動画といったコンテンツが身近になったことと密接に関連しています。
しかし、アーカイブが広く使われるようになる一方で、その意味や内容が多様化している側面もあります。アナログメディア時代から存在し、人類が記録と記憶を司ってきた概念であるアーカイブが、デジタル化と情報のネットワーク化が進む現代において、どのように捉え方が変化してきたのかに注目する必要があります。
1.2. アナログ時代とデジタル時代のアーカイブ概念の相違
日本では1990年代頃から「アーカイブ」や「デジタルアーカイブ」という言葉が普及し始め、2000年代以降に多くのプレイヤーが関わるようになりました。特に2000年代は、デジタルアーカイブに関する活発な理論的議論が展開された時期です。
伝統的なアーカイブズ学においては、以下の二つの理念が重視されてきました。
保存するものの価値判断: 保存すべき記録は無制限ではなく、人類が価値判断を伴って残してきたものである。何を残すことが有用なのかを突き詰めるのがアーカイブズ学の初発の考え方です。
長期保存と利用規範: 保存された記録が未来永劫利用可能であるために、いかなる規範に従って構築されるべきかという問いが重要です。
しかし、現代のアーカイブ概念(例:YouTubeやWikipedia)には、必ずしもこのような特定の誰かや国・機関によるレギュレーションに基づかない集積物も含まれます。アナログ時代は情報の集積が物理的な蓄積として想像しやすかったのに対し、デジタル時代は情報が潜在的に複製可能で相互に接続されるため、情報の集積概念も変化しています。
私たちは、政治的、経済的、社会的、文化的な文脈の中で、人類が記録や記憶(情報)を生み出し、保存し、利用し、時には忘れ、破壊してきた「アーカイブ的な行為」をどのように扱ってきたのかを歴史的に捉え直す必要があります。
2. デジタルアーカイブの系譜と概念変遷
2.1. 「デジタルアーカイブ」の誕生と初期の文脈
日本の学会では、現在、「日本アーカイブズ学会」(2004年設立)と「デジタルアーカイブ学会」(2017年設立)が主要な存在です。しかし、「デジタルアーカイブ」という言葉は、それ以前の1990年代前半に月尾嘉男氏によって創り出された和製英語です。
月尾氏の当初の問題意識は、情報が国の隆盛に大きく関わる時代が来るという危機感とフロンティア意識にあり、デジタルアーカイブを情報通信政策の中に位置づけようとしていました。当時のキーワードは「マルチメディア」であり、そのコンテンツ論を重視する立場でデジタルアーカイブという言葉が作られました。
このことから、デジタルアーカイブという言葉は、当初は「どんな記録を選んで残すか」「永続性をどう担保するか」といった伝統的なアーカイブズ学の観点から生まれたわけではなかったことがわかります。
2.2. 多様な系譜の合流と概念の拡張(1990年代後半〜2000年代前半)
1990年代半ばから、月尾氏が提唱したデジタルアーカイブの概念は、文化財保護や博物館の分野で最初に導入されました。世界の文化をデジタル化して保存する文化財保護の観点や、マルチメディアなミュージアムを構築する考え方と結びついていきます。
1996年には、国の政策としてデジタルアーカイブ構想が位置づけられ、文化庁、通産省、自治省(情報通信政策、文化財保護、地域振興を担う省庁)が連携してデジタルアーカイブ推進協議会が設立されます。
この時期、すでに図書館情報学分野の長尾真氏による「デジタルライブラリー」や「電子図書館構想」、博物館分野の青木保氏による「デジタルミュージアム」といった言葉が存在していました。これらが徐々に「デジタルアーカイブ」という言葉に置き換えられ、合流していくことになります。
このように、デジタルアーカイブという言葉には、文化学術振興、産業振興、地域振興、博物館、図書館といった多様な系譜と思いが込められていきました。月尾氏の当初の情報通信政策としての意図から、概念が多義的になっていったことがわかります。2000年代前半に書かれた「デジタルアーカイブとは」といった書籍でも、著者によってその考え方が少しずつ異なっていました。これは、関わってきた人々のバックボーンが大きく影響していたと考えられます。
2.3. 長期保存への視点とMLA連携の提唱(2000年代中盤〜)
2000年代に入ると、デジタルアーカイブの概念に長期保存への観点が加わるようになります。1990年代後半に多くの予算がつき、デジタルアーカイブへの期待が高まった一方で、2000年代は予算が停滞する時期でもありました。この頃、初期に作られたデジタルコンテンツのシステムが古くなったり、画素数の問題やネットワークの遅延によりアクセスできなくなるといった問題が顕在化し、「デジタル技術は長期保存に適しているのか」という疑問が生じました。
そこで、デジタルアーカイブには「長期保存」という概念が不可欠であるという認識が強まります。これに最も親和性が高かったのが、改ざんがないこと、アクセスが担保されていること、長期で安定して信頼性のある形で保存されることなどを重視する伝統的なアーカイブズ学の考え方でした。2004年の日本アーカイブズ学会設立も、この長期保存への視点を強める要因となりました。
さらに、2000年代には、図書館(電子図書館)、博物館(デジタルミュージアム)、文書館(アーカイブズ)といった各機関が「デジタルアーカイブ」という共通の言葉を使うようになり、これらを基盤としたMLA(Museums, Libraries, Archives)連携という新しい形の連携が提唱され、デジタルアーカイブがその結節点となっていくという議論も起こりました。
2.4. 東日本大震災と市民参加型アーカイブの出現(2010年代〜)
2010年代に入り、東日本大震災を契機に、デジタルアーカイブの概念に新たな要素が加わります。MLA連携だけでなく、震災のような広域災害における人々の共有の記録や記憶を伝承し、今後の災害対策に役立てるという役割がアーカイブに求められるようになりました。東北大学やYahoo!、Googleなどが震災アーカイブを構築したほか、ハーバード大学や国立公文書館なども、名称に「アーカイブ」が含まれていなくても、その目的や趣旨にアーカイブ概念を含むプロジェクトを多数立ち上げました。
この時期に特に重要になったのが、市民参加型のアーカイブです。スマートフォンの普及により、市民が被災現場の動画や写真を撮影し、SNSで共有することが容易になりました。これにより、これまで国や組織がデジタルアーカイブの担い手であったのに対し、個人の発信が社会に大きな影響力を持つようになりました。
これは、これまでのツリー構造的な、構築されるデジタルアーカイブとは異なる、多元的なアーカイブのあり方を提示しました。また、これまでデジタルアーカイブが、ある程度価値評価が固まったものをデジタル化するという流れであったのに対し、瞬発的に生成されるデジタル画像などが現れ、それらが簡単に消去されうるという問題も生じました。
これにより、「デジタルアーカイブとはこういうものだ」という共通認識が再びシャッフルされることになり、デジタルアーカイブの共通理解や最大公約数をどこに設定するかが新たな論点となりました。デジタルアーカイブ学会による「アーカイブ立国宣言」や「デジタルアーカイブ憲章」は、まさにこの問いに対する答えを模索する取り組みと言えます。現在は、多様な思いや考え方が流入しているため、それらを一つにまとめることは困難であるという共通理解のもと、図書館や文書館、博物館に立脚した考え方から、ネットワーク性やアクセシビリティを含めた、より広範な概念を構築しようとする取り組みが進められています。
3. デジタルアーカイブを支える技術的文脈と政策動向
3.1. Web技術の発展と永続性の確保
デジタルアーカイブは、**ワールドワイドウェブ(WWW)**の技術と密接不可分な関係にあります。1980年代後半にティム・バーナーズ=リーによってURL/URIとWebの概念が提唱され、インターネット上で情報にアクセスすることが可能になりました。
Web技術の進歩は、デジタルアーカイブの永続性を担保する方向へと進化しました。
パーマリンク(2000年〜): コンテンツ管理システムの導入により、URIを維持し、コンテンツを固定するという考え方が生まれました。
PID(永久識別子、2010年〜): 第三者機関との連携によりURL/URIを維持し、DOI(Digital Object Identifier)のような仕組みによって、コンテンツに永久的な識別子が付与され、永続性が確保されるようになりました。
IIIF(2011年〜): 画像コンテンツの相互運用性を高めるための国際的な枠組みです。URIの書式と画像処理ルールを標準化することで、Web上でデジタルアーカイブの画像がより広く利用されるようになりました。
3.2. 日本におけるデジタルアーカイブ政策の推進
月尾嘉男氏が「デジタルアーカイブ」という言葉を作った背景には、郵政省、自治省、通産省といった省庁との連携を通じた情報通信政策の中にそれを位置づけたいという意図がありました。
1990年代前半、日本ではハイビジョン技術の活用と普及のためのインフラ整備が模索されており、そのコンテンツとしてマルチメディア、そしてデジタルアーカイブが着目されました。
1996年: デジタルアーカイブ推進協議会の設立: 文化庁、通産省、自治省が連携し、文化学術振興、産業振興、地域振興の文脈でデジタルアーカイブが推進されることになります。
2000年: 内閣府IT戦略本部の設立とe-Japan戦略: IT戦略本部が発足し、2001年には「世界最先端のIT国家」を目指すe-Japan戦略が策定され、IT化・デジタル化が強力に推進されました。IT戦略本部はその後も名称を変えながら、国家プロジェクトとしてデジタル化政策を牽引していきます。
22000年代以降のデジタルコンテンツ整備:
2001年: アジア歴史資料センターが開設され、国立公文書館などが提供するデジタルコンテンツが国として公式に発信されるようになりました。
2002年: 国立国会図書館が近代デジタルライブラリーを開始。
2005年: 国立公文書館がデジタルアーカイブの運用を開始。
その他、自然史系博物館のS-Net、人間文化研究機構のNIHU-Int、文化庁の文化遺産オンラインなどが公開され、図書館、博物館、文書館といった各機関がそれぞれデジタルアーカイブのポータルサイトを整備するようになりました。
2010年代以降: 知的財産戦略本部による推進とJapan Search構想:
国のIT戦略本部から、デジタルアーカイブ政策の担い手が知的財産戦略本部へと移管されます。知的財産戦略本部は、従来のIT・e-Japan戦略を引き継ぎ、デジタルアーカイブを知的財産政策の中に位置付けました。
2013年頃からアーカイブに関するタスクフォースが設置され、保有コンテンツのデジタル化と活用、分野横断的・統合的なポータルサイトの必要性が議論されました。
その結果、Japan Search構想が生まれ、2020年にはJapan Searchが正式に公開され、分野横断的なデジタルアーカイブの統合ポータルが実現しました。
現在、内閣官房の知的財産戦略推進事務局がデジタルアーカイブ推進を担っていますが、その議論は、単なるポータルサイトの構築だけでなく、産業振興、アーカイブの担い手育成、教育など、より広範な領域に広がっています。
4. デジタルアーカイブの多様性と今後の展望
現在のデジタルアーカイブの系譜を振り返ると、「デジタルアーカイブ」という言葉が、特定の個人の思想や単線的な議論から生まれたものではなく、多様な概念や定義に関わる複数の源流が合流して形成されてきたことがわかります。
デジタルアーカイブは非常に懐が深い言葉であり、様々な流れが合流したり、時としてそこから分かれたりしながら、広くその意味を広げてきました。そしてこれからも、多くの言葉や概念が流入していくでしょう。
このようなデジタルアーカイブの多様な起源を知ることは、私たちが今後デジタルアーカイブをどこへ向かわせるべきかを考える上で重要な指針となります。誰かの特定の意見だけを正しいとするのではなく、より建設的にこれからのデジタルアーカイブの構築や活用に向けて、共通理解を形成していくことが求められています。
(文責:久世)
3.「企業におけるデジタルアーカイブ」
大橋秀亮氏(TOPPAN株式会社 チームリーダー)
動 画
資 料
内 容
1. 自己紹介とデジタルアーカイブへの関わり
私はトッパン株式会社の大橋と申します。現在は上級デジタルアーキビストとして、企業におけるデジタルアーカイブを担当しています。
1998年にトッパン印刷株式会社(当時)東北事業部に入社し、当初は主にジャスコ(現在のイオン)のチラシ制作を担当していました。当時のトッパン印刷は、商業印刷や出版物が花形業務であり、大手企業のカタログ制作や出版社との協業が中心でした。
2005年に関西金融証券事業部に異動した頃から、世の中のデジタルアーカイブへの流れを肌で感じ始めました。私自身が「デジタルアーカイブ」という言葉を初めて耳にしたのは2000年、福島県立美術館の収蔵品管理システム販売を担当した際です。
2008年からは本格的にデジタルアーカイブを担当することになり、世の中は急速に変化しました。2009年には国立国会図書館の長尾真館長による大規模デジタル化が始まり、私はその中で関西館の博士論文デジタルデータの著作権調査に携わりました。その後も、京都歴史博物館の古文書デジタル化(2012年)や沖縄県公文書館の琉球政府文書デジタル化(2013年)、さらには南九州市の知覧特攻平和会館における特攻隊員の遺書デジタル化など、多岐にわたるデジタルアーカイブプロジェクトを担当しました。
2017年には文化庁に出向し、2014年からは大阪公立大学で産学官民連携推進にも携わっています。現在は、デジタルアーカイブの活用にとどまらず、トータルな視点で業務に取り組んでいます。
2. 企業におけるデジタルアーカイブの意義と課題
企業にとってデジタルアーカイブとは何か、という問いに対し、私は**「ステークホルダーのためのアーカイブ」**であると考えています。図書館、公文書館、博物館が「全てのお客様のために」アーカイブを構築するのに対し、企業は「関係する方々(ステークホルダー)にいかに活用してもらえるか」を重視します。
トッパンのように国民全体と関わる規模の企業の場合、そのステークホルダーは広範に及びますが、やはり「誰のために」という視点は重要です。
企業にデジタルアーカイブを提案する際によく聞かれるのは、「売上や利益につながるのか」「宣伝にお金を使った方が良いのでは」「もっと将来につながる経営戦略への投資を優先したい」といった声です。デジタルアーカイブの重要性を理解している企業でも、「今は業績が上がってから」「設備投資が優先だ」といった返答が多いのが実情です。
このような状況を踏まえ、企業へのアプローチとしては、まずBCP対策や業務効率化、知財やノウハウの共有といった、直接的な収益につながる側面を強調して説明します。その上で、最も重要である社史や理念の浸透、企業ブランディングといった目的を伝えていくことが有効であると考えています。
3. 企業デジタルアーカイブの具体事例と活用法
デジタルアーカイブは、電子データの保存・複製が可能で、インターネットを通じてどこからでも閲覧できるため、紙媒体よりもはるかに便利です。具体的な活用事例をいくつかご紹介します。
3.1. 業務効率化とリスク対策:銀行印鑑のデジタル化
かつて郵便貯金(現在のゆうちょ銀行)の通帳には、お届け印の印影が貼付されていました(通称「福印」)。しかし、これはセキュリティ上のリスクが高く、2013年には廃止されました。この廃止に伴い、各支店で保管されていた印影の照合に多大な手間がかかるという課題が生じました。
メガバンクの事例では、この印影を全てスキャンしてデジタル化し、全支店で閲覧できるようにする取り組みが始まりました。これにより、紙での情報共有やFAXでのやり取りといった非効率な業務が不要となり、業務が大幅にスリム化されました。
また、クレジットカードや保険契約などで用いられるサインも、単なる筆跡だけでなく、筆圧、筆運び、書く方向など、あらゆる情報がデジタルアーカイブ化され、本人確認に活用されています。こうした取り組みは、金融機関が大きく変化したデジタルアーカイブの応用例と言えます。
3.2. 知的財産・ノウハウの共有と伝承
熟練者の技術や経験、勘といった無形資産は、音声や映像で記録・形式化し、蓄積・活用することで、その伝承を拡大できます。企業内部のノウハウは通常公開されませんが、その一例として、文化庁の文化遺産オンラインでは、日本の伝統技術(例:蒔絵の作業風景)が映像で記録され、公開されています。
トッパンでも、人間の動きを可視化し、動作の癖や改善点を分析するループトレーニングシステムという商品を開発しています。例えば、ゴルフのスイングや走りのフォームをデータ化し、プロの動きと比較することで、技術習得や改善に役立てています。これも、熟練者のノウハウをデジタルアーカイブ化し、共有する取り組みと言えます。
3.3. 情報共有と人脈管理:名刺のデジタル化
社内での情報共有においても、デジタルアーカイブは活用されています。例えば経済産業省では、4000人の職員を対象に、名刺の情報をスキャンしてデータベース化する実証実験を行いました。これにより、誰が誰と会い、どのような人脈を築いているかを共有し、最新の連絡先情報を把握できるようになりました。
近年では、ZOOM会議などでQRコードを用いた電子名刺の交換も行われるようになり、名刺のデジタルアーカイブ化は情報共有の効率化に貢献しています。
4. 企業ブランディングと社史・理念の浸透
最も重要であると考えるのが、デジタルアーカイブを通じた社史や理念の浸透、そして企業ブランディングです。
創業者が偉大な人物であり、その精神が社員に浸透している企業は、デジタルアーカイブを積極的に活用しています。グローバル展開する企業では、海外の社員に自社の歴史や原点を伝えるために、創業者の言葉や創業からの歴史をデジタルアーカイブとして残し、共有しています。
4.1. 著名企業の事例
京セラ(稲盛和夫氏): 京セラは、創業者稲盛和夫氏の人生哲学・経営哲学である「京セラフィロソフィー」を学び継承することを目的とした「稲盛ライブラリー」を立ち上げています。稲盛氏の生の声を聞ける映像アーカイブや、展示室のバーチャル見学を通じて、彼の精神が全従業員の判断基準として共有されています。
パナソニック(松下幸之助氏): パナソニックの本社には、創業者松下幸之助氏とパナソニックの歴史を伝える建物があり、社員や来訪者に創業者の精神を伝えています。日本を代表する企業が、創業者の精神をいかに大切にしているかがわかります。
オムロン(立石一真氏): オムロンは、創業者立石一真氏の思いや、駅の自動改札機開発といった革新的な取り組みの歴史をデジタルアーカイブで伝えています。また、社名の由来なども詳細に記録されています。
ソフトバンクグループ(孫正義氏): ソフトバンクグループも、孫正義氏の志やビジョンがデジタルアーカイブとして記録され、グループ全体で共有されています。少人数のスタートアップであっても、孫氏のビジョンを共有し、事業に取り組む姿勢は、デジタルアーカイブによる理念浸透の好例と言えます。
これらの事例から、単なる技術や売上・利益の追求だけでなく、企業理念やブランディングといった精神的な側面をデジタルアーカイブを通じて伝えることの重要性がうかがえます。
4.2. トッパンの事例
トッパンも、自社の歴史を伝えるためにデジタルアーカイブに取り組んでいます。最近のテレビCMでは、かつて印刷が花形だった出版事業がデジタル化され、キャッシュレス決済に変わっていくという歴史を感じさせる内容が描かれています。このCMは、社員が自社を誇りに思うこと、そして学生や社会一般にトッパンという企業を知ってもらうことを目的としています。
トッパンは**「トッパンヒストリー」**というウェブサイトで企業情報を発信しており、年代別に区切られた歴史の中で、創業者の精神や、活版印刷からオフセット印刷への転換といった重要な出来事を伝えています。トッパンの場合、特定の創業者に焦点が当たるよりも、常に新しいことに挑戦する「変革の精神」が受け継がれていることを強調しています。
5. デジタルアーカイブの応用と社会貢献
企業のデジタルアーカイブは、単なる社内活用にとどまらず、社会貢献にも繋がっています。
5.1. 文化財・歴史資料の忠実な再現と復興支援
トッパンは、バーチャルリアリティ(VR)映像制作において、歴史的な建物の再現などに忠実な再現性を追求しています。例えば、熊本地震で被災した熊本城の石垣の復興では、崩れる前の石垣の精密なデジタルアーカイブが、崩れた石を元の位置に戻す作業に役立ちました。肉眼では判断が難しい石の形状や凹凸も、デジタルデータで詳細に分析することで、復興作業の精度向上に貢献しています。
5.2. 市民参加型アーカイブと地域活性化
京都の伏見区では、市民から集めた映像や写真を組み合わせてアーカイブする取り組みが行われています。博物館や資料館の資料だけでなく、市民が提供した個人的な写真(例:1982年の七五三の写真)などもアーカイブすることで、当時の風景や人々の暮らしを多角的に記録し、地域住民が参加し、活用しやすいアーカイブを構築しています。これにより、アーカイブが地域コミュニティの中で継承されやすくなります。
5.3. 国宝・文化財の高精細デジタル化と研究活用
京都の国宝「洛中洛外図屏風(舟木本)」もデジタルアーカイブ化されています。通常は近づいて見ることができない屏風の細部(例えば、約1cmの人物の顔や0.数mmの着物の柄)も、高精細なデジタルアーカイブによって拡大して閲覧できるようになりました。さらに、人物一人ひとりにタグ付けを行い、当時の生活様式などを調査するプロジェクトも進行中です。
5.4. 災害アーカイブと3次元データの活用
最近の事例として、石川県の能登半島地震に関するアーカイブが公開されました。Googleマップと連携し、被災地の3次元データと組み合わせることで、どのような被害があったかを詳細に把握できるようになっています。デジタルアーカイブの技術は、このような災害記録や復興支援においても進化を続けています。
6. まとめ
企業にとってデジタルアーカイブは、単に売上や利益に直結するだけでなく、社史や企業理念の浸透、企業ブランディングといった、企業の根幹を支える重要な役割を担っています。もちろん、知的財産やノウハウの共有、業務効率化、BCP対策といった実務的な側面も重要であり、これらの側面からデジタルアーカイブの導入を推進することが有効です。
最終的には、**「ステークホルダーのためのアーカイブ」**として、企業のデジタルアーカイブを構築していくことで、その価値が広がり、企業活動の持続的な発展に貢献していくでしょう。
トッパンでは、東京・飯田橋の印刷博物館(企業のミュージアムではなく、印刷の歴史を伝えるミュージアム)で、新しいシアターなどを通じて印刷の歴史を体験できます。また、大阪公立大学での産学官民連携など、様々な形でデジタルアーカイブを活用した社会貢献に取り組んでいます。
(文責:久世)
コーディネータ:井上 透氏(岐阜女子大学教授)
■ e-Learning(オンデマンド講座)
デジタルアーカイブ概論【Ⅰ】 ~ デジタルアーカイブによる地域活性化 ~