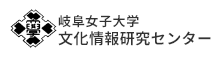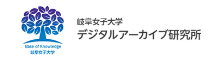【公開講座】AI(人工知能)講座 ~AI時代のデジタルアーカイブ~
【公開講座】AI(人工知能)講座 ~AI時代のデジタルアーカイブ~
1.「AIと人間の学び」
赤堀侃司(東京工業大学名誉教授)
1.動画資料
2.資 料
1.プレゼン資料(赤堀先生)
2.AIと人間の学び 壁の向こうで答えているのはAIか人か? (単行本)発売日 : 2022/3/31
3.内 容
1. はじめに:AIと人間の知能
チャットGPT登場以前に実施したチューリングテストに関する自身の研究を基に、AIと人間の知能のあり方について考察しています。アラン・チューリングが第二次世界大戦中にドイツ軍の暗号「エニグマ」解読に貢献し、その後の1950年に発表した論文「Computing Machinery and Intelligence」で提唱されたチューリングテストは、機械が人間のような知能を持つかを判定する思考実験です。講演者は、このテストを簡略化した形でドイツのギムナジウムや日本の学生を対象に実施し、AIが生成した回答と人間が生成した回答を区別することが現代の高校生にとっても困難であることを示しました。この結果から、チューリングの先見性を再認識しつつ、AIが進化する中で人間が真に持つべき能力について深く考える必要性を提起しています。
2. 人間に求められる質的能力
講演者は、AIの進化が著しい現代において、人間がAIには代替されにくい、あるいはAIを凌駕する形で備えるべき能力として、以下の5つの点を挙げています。
2.1. 共感すること
講演者は、平沢真子先生の中学校での国語の授業実践を例に挙げ、共感が学習理解に与える影響の大きさを強調しています。感動した箇所に線を引いたグループが最も高い学習成績を収めたことから、単なる知識の理解だけでなく、文章や状況に共鳴することが深い理解につながると考察しています。これは、脳科学における情動を司る部位と認知を司る部位の連携とも関連しており、人間が他者と協力し、共に学ぶ上で不可欠な要素であるとしています。所沢市三原中学校での本箱制作や下山口中学校での体育の授業における生徒の自然な協力行動も、互いへの共感や共鳴から生まれるものであり、社会構成主義の観点からも人間の本質的な学びの姿を示していると指摘しています。また、不登校問題や自殺者の増加といった現代社会の課題の背景には、共感の欠如や相互不信がある可能性を指摘し、共感能力の育成が教育の根幹であるべきだと述べています。
2.2. 非認知能力を高めること
ノーベル経済学者ヘックマンの研究であるペリー就学前プロジェクトの事例を通して、非認知能力の重要性を強調しています。この研究では、就学前教育を受けたグループが、40歳になった時点での生活保護受給率、持ち家率、月収、高校卒業率、基礎学力、特別支援対象者となる割合など、あらゆる面で教育を受けなかったグループを大きく上回る成果を出しました。知能指数(認知能力)の差は学校入学後には解消されるにもかかわらず、その後の人生における大きな差は、就学前教育で培われた人間関係力、道徳性、自己発揮といった非認知能力に起因するとヘックマンは結論づけています。
講演者は特に、非認知能力の中でも**レジリエンス(復元力)**に注目しています。失敗しても諦めずに粘り強く続ける力は、コロナ禍や自然災害といった困難な状況を乗り越える上で不可欠であり、学校教育においてもその育成が喫緊の課題であると認識されています。技術家庭科の授業で生徒が本箱を固定するために工夫する姿は、まさにレジリエンスと問題解決能力の表れであり、また、作品を美しく仕上げようとする姿勢は、単に困難に耐えるだけでなく、美意識を追求する人間の本質的な欲求と結びついていると考察しています。
2.3. 大切なことと大切でないことを区別すること
フィンランドの教育メソッドの例を挙げ、「必要な情報と不必要な情報を区別する能力」の重要性を指摘しています。文章読解問題において、必要な言葉と不要な言葉を識別し、解き方を言葉で説明させるフィンランドの教科書は、単なる正解を導き出すだけでなく、思考プロセスを言語化する力を養うことに着目しています。これはアメリカの学者が提唱する自己説明の概念にも通じ、自分の言葉で説明できる状態こそが真の理解であると述べています。
また、俳句の「プレバト」の例を挙げ、プロが「決して良い言葉」と「決してはいけない言葉」を区別できるのは、その分野における深い知識と経験があるからだと説明しています。これは、大切なことと大切でないことの区別が、基礎的でありながら極めて高度な能力であることを示唆しています。AIは膨大なデータから関連性を導き出せるものの、人間が持つ暗黙知を形式知として言語化する力は、依然として人間に求められる重要な能力であるとしています。
2.4. 疑問を持つこと
小学校の校長先生の事例を挙げ、子供たちが給食に関して抱く素朴な疑問(給食費は高いか安いか、いつから始まったか、アレルギーの子はどうするかなど)が、実は奥深い探求につながることを示しています。給食費の安さの背景には国の負担や歴史があり、単なる知識の羅列ではなく、探求心やリサーチクエスチョンの生成能力が重要であると指摘しています。
また、カブトムシの力や昔の暮らしにおけるハサミの有無といった子供の自由研究や素朴な疑問は、一見単純ながらも、著名な生物学者の研究にも通じるような本質的な問いにつながる可能性を秘めていると述べています。人間の「なぜ?」という好奇心や疑問を持つ力は、新たな発見や深い学びの原動力となることを強調しています。
2.5. 関連付けること
中村恵先生の小学校1年生向けプログラミング教育の実践例を挙げ、論理的思考力と関連付けの能力の重要性を説明しています。「忘れ物をしないためにどうしたらいいか」という問いに対し、子供たちが「家に帰る」「明日の準備をする」「時間割を見る」「連絡帳を見る」といった手順を論理的に関連付けて考えることで、プログラミング的思考が育まれることを示しています。
全国学力学習状況調査の結果から、環境問題に関するプレゼンテーションや図形の面積比較の問題など、知識を関連付けて自分の言葉で説明する能力が不足している現状を指摘しています。AIは膨大な知識を関連付けられるが、人間は自らの暗黙知を形式知化し、言語で説明する力をさらに高める必要があると述べています。**スキーマ(枠組み、知識構造)**を理解すること、そしてそれに基づいて物事を関連付け、再構成する能力が、AI時代における人間の強みとなるとしています。
3. 人間に求められるデザイン能力
講演者は、今後のICTの活用において、人間は単なるユーザー(利用者)ではなく、ライターやデザイナーとしての役割が求められると強調しています。スクラッチなどのプログラミングは、頭の中の構想を手順に落とし込み、試行錯誤しながら最適な形を作り出す作業であり、まさにデザインのプロセスであると指摘しています。人間は、シナリオライター、ディレクター、プロデューサーのように、自らが主体となって知識を構造化し、最適なプロセスや成果をデザインする能力が必要であると述べています。
東京書籍の優秀賞を受賞した佐先生の事例では、児童が図形の面積の問題でつまづく原因が「量感が育っていない」ことにあると分析し、児童自身に問題を作成させるという授業デザインを行ったことで、学習効果が大幅に向上したことを紹介しています。これは、子供が主体的に学びに関わり、ICTツールを効果的に活用することで、深い学びが生まれることを示しており、人間のデザイン能力が教育現場でも極めて重要であることを示唆しています。
4. まとめ:AI時代の教育の方向性
講演者は、AIは膨大なデータを基に推論を行うが、必ずしも意味を完全に理解しているわけではない(ニューラルネットワークの隠れ層の解釈の難しさ)と指摘し、人間がAIには代替されにくい、あるいはAIと協調して発揮すべき能力を改めて強調します。
最終的に、AI時代の人間には、以下の能力が求められると結論づけています。
• 共感すること:他者と共鳴し、深い理解と協力を生み出す能力。
• 非認知能力を高めること:レジリエンスを含め、人生を豊かに生きるための感情的・社会的な能力。
• 大切なことと大切でないことを区別すること:本質を見抜き、情報を整理し、思考を言語化する能力。
• 疑問を持つこと:素朴な疑問から探求心を育み、新たな知識を創造する能力。
• 関連付けること:バラバラな情報を結びつけ、論理的に思考し、問題解決に導く能力。
• デザインすること:主体的に学びのプロセスや成果を構想し、具現化する能力。
これらの能力を育むことが、AIが高度に発達する社会において、人間が人間らしく、そして創造的に生きるための教育の方向性であると提言しています。
4.AI資料 AI時代の人間と教育に求められる六つの能力
(1)スライド資料
(2)動画資料
2.「人とAIの学習研究から考えるこれからの教育」
益川弘如(聖心女子大学教授)
1.動画資料
2.資 料
3.内 容
1. はじめに:AIと教育の新たな関係性
聖心女子大学の益川弘如教授は、学習科学、認知科学、教育工学を専門とし、普段は小中高校の教員と共に子供たち主体の授業づくりに取り組んでいます。特に、人はどのように学び、どうすれば深く学べるのかという認知科学の研究と、AIの知能を人の賢さと比較する研究を並行して進めてきました。本講演では、この知見を基に、AIとの共存が不可避な時代において、人間が培うべき**「価値ある学び」**とは何かについて考察が展開されます。
デジタルアーカイブ技術の進展は、時間や場所を超えて情報にアクセスし、知識を創造する基盤を提供します。しかし、生成AI、特にチャットGPTのような技術が教育現場に導入される中で、「思考力を発揮する学び」を実現できるのかという問いが浮上しています。チャットGPTに年齢制限が設けられていても、実際には容易に利用できてしまう現状を鑑み、教育現場は先回りして生成AIの賢い使い方を子供たちに教える必要性を強調しています。
2. 生成AI活用のための学習観と授業観
生成AIの活用は、その目的に応じて大きく2つのアプローチに分けられます。
効率化のための使い方: 定型文の作成など、頭を使わずに効率的に良い文章を得ることを目的とする場合。AIから答えをもらい、コピー&ペーストで済ませる形になりがちです。
学ぶ学習のための使い方: 自分なりの知識を構成・構築するために、AIをヒントやサポート、あるいは異なる視点を得るためのツールとして活用する場合。
教員自身の学習観や授業観が、生成AIの効果的な活用に大きく影響します。もし「学ぶことは誰かから教わって覚えること」という学習観であれば、生成AIは単に答えを得るための手段となってしまい、子供たちの深い思考を促しません。しかし、「学ぶことは他者との対話などを通して自分なりに知識を構成すること」という学習観であれば、生成AIは子供たちが自ら答えを創造するための補助ツールとして機能し、思考を深めることができます。
文部科学省が2023年7月に発表した「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」でも、この二分法が明確に示されています。単にAIが生成したものを自分の成果として提出する行為は不適切とされ、一方で、グループでの議論を深めるためのアイデア出しや、足りない視点を見つけるためにAIを活用することは適切であるとされています。同じ道具であっても、目的意識によってその効果は大きく変わる、という点を強調しています。
3. 生成AIを活用した授業事例(相模原市立中野中学校)
文部科学省の生成AIパイロット校である相模原市立中野中学校での実践事例が紹介されました。この学校は、生成AIの導入以前から、以下の**「学びのスタンダード」**を基盤とした授業づくりに取り組んでいました。
子供たち同士の対話中心の授業: 友達の発言を受け止め、自分の思いを伝えることを重視。
教師の役割: 子供たちの実態に合わせて主体的・対話的で深い学びを実現するため、教師の発話時間を減らし、生徒の活動時間を確保。問い返し(「どうして?」「なぜ?」など)を中心に、深い学びを促す。
ICTの活用: 1人1台のタブレット端末を活用し、自分の思いを書き込んだり、友達の考えを自由に見たり比較したりできる環境を整備。
このようなベースがあったからこそ、単にAIから答えをもらうだけでなく、思考を深める形で生成AIが活用された事例が報告されています。
3.1. 中学校2年生 英語科:世界遺産を紹介する授業
世界遺産を紹介する英作文とプレゼンテーションを行う授業で、生成AIが活用されました。
英語表現の工夫とサポート: 事前に、今日のテーマ(例:「沖縄の良さについて伝えよう」)に関連する表現を生成AIに入力するルール(プロンプト)を生徒に提示。生徒は生成AIに表現例を生成させ、難しい表現は「10ワード以内で」「中学校2年生でもわかる単語で」などと何度も聞き返しながら、自分にとって使いやすい表現を見つけ出しました。
即興会話の練習: 音声入力機能を使って、生成した英文を読み上げ練習。発音の悪い部分は誤変換されるため、自己チェックが可能に。
グループワークでのブラッシュアップ: 4人グループで、それぞれ異なる世界遺産(日本の文化遺産、海外の自然遺産など)を紹介するプレゼンを練習。多様な語彙や表現に触れることで、互いに「ここが分かりにくい」「もっと簡単な表現がいい」などのコメントを出し合いました。その後、チャットGPTを使って指摘された部分の表現を改善。最終的にどの表現を選ぶかは生徒自身が判断しました。
AI翻訳ソフトの活用: ディベートの授業では、AI翻訳ソフト(DEEPLなど)も活用され、生徒たちはどのような状況でどのツールを使い分けるべきかという議論も行いました。
この授業では、「学びのスタンダード」である対話的な学習の中に、ICTが活動を深める仕掛けとして組み込まれていました。
3.2. その他の教科での活用事例
数学科:水の体積を求める授業
生徒自身がチャットGPTに関連する問題を作成し、チャットGPTが出題した問題を解く活動を行いました。これにより、教員が用意するよりも多様な問題に取り組むことが可能に。難易度が高い問題が出た場合は、生徒自身が解けるレベルになるよう、プロンプトを工夫して問題を修正させました。
理科:雲の生成と状態変化を記述する授業
雲ができる仕組み(水蒸気が水滴になる状態変化)を文章で表現する活動を実施。生徒がまず自分で文章を作成し、その表現が科学的ではない部分をチャットGPTを使って改善しました。AIが提供する解説的な表現と、生徒自身の分かりやすい表現を比較・検討することで、科学的な記述力を高めました。
美術科:ボックス作品の紹介文作成
作成したボックス作品について、チャットGPTに紹介文の相談を行いました。自分の作品の特徴をテキスト化して入力し、AIからの提案を受けて、「もっと工夫した点を盛り込むにはどうしたらよいか」と再入力し、より適切な紹介文を生成しました。
国語科:画像生成AI(Canva)を活用した文学作品の表現
これまでに学習した文学作品(例:走れメロス)や俳句、短歌から題材を選び、画像生成AIでそのイメージ画像を生成。生成された画像が作品のイメージを適切に表現しているか、そうでない場合はどのようにプロンプトを工夫すれば理想の画像になるかを話し合いました。このプロセスを通じて、生徒たちは文学作品の内容を深く復習し、表現力を磨きました。
これらの事例は、生成AIが単なる答えの提供ツールではなく、子供たちの思考を深め、対話を促し、学びを豊かにするためのツールとして活用できる可能性を示しています。
4. 人間とAIの学習研究から考えるこれからの教育
講演者は、今回の事例を通して、AI時代における教育のあり方について、いくつかの重要な考察を述べました。
4.1. 人間の「わかる」と「知識の定着」
人間の「わかる」とは、単に情報をコピー&ペーストしたり、丸暗記したりすることではありません。自分なりの言葉で説明できるようになることが重要です。そのためには、多様な情報へのアクセス、他者との議論、そしてAIを含む様々なツールの活用が不可欠です。
認知科学では、私たちの理解は社会的に構成されると言われています。教員がどれほど分かりやすく説明しても、それが生徒の頭の中にある既存の知識(レベル1)と直接繋がらないと、表面的な理解(バブル型の理解)に留まってしまいます。このような知識は忘れやすく、真の定着にはつながりません。
重要なのは、学習者が取り込もうとしている情報を、自分が既に持っている知識と繋げ、自分の言葉で表現してみることです。これを話し言葉で実践し、友達と対話することで、自分の理解が正しいかどうかの検証や、より深い理解への修正が可能になります。他者との共感が得られれば、その知識は確固たるものとなり、忘れにくい知識として定着していきます。
4.2. 人と人との対話の重要性
AIの進化により、「人と人との話し合い活動は不要になるのではないか」という議論も存在しますが、講演者はこれを否定します。AIは質問に答えることはできても、「一緒に考え、悩み合う」ような相互作用はできません。
人と人との対話では、共通の問いや目標に向けて、**「どうかな、多分なんだけど」といった形で思考を投げかけ合い、互いの理解を深めていくことができます。AIとの相互作用も新たな学びの可能性を秘めていますが、人間同士の対話は、「理解の進化」**という点で本質的に異なる価値を持っています。
4.3. 人間とAIの思考特性の違い
講演者は、AIと人間の思考特性の違いを、心理学の有名な「4枚カード問題」と「神社の祭り問題」を例に説明します。論理構造が全く同じであるにもかかわらず、人間は後者の問題(経験に基づくイメージ思考が可能な問題)を容易に解くことができます。これは、人間が持つ**「経験に基づいたイメージ思考」**という強みを示しています。
一方、AIは論理構造が同じであれば、問題の難易度は変わりません。これは、AIが「何を考えなくていいのか」を判断できず、記号の持つ「意味」を理解していないことによるものです。AIは記号のネットワークを通じて意味を理解しているかのように振る舞いますが、それは確率に基づいた処理であり、人間のような本質的な意味理解ではありません。
この違いを踏まえると、AI時代に人間が養うべき学習能力として、以下の点が挙げられます。
フレーム問題の克服: 問題文から頭の中でイメージを構築し、何を考えなくていいのかを判断する力。現代の子供たちは、文章題を読んでイメージができず、思考が停止してしまう傾向があると指摘します。
記号設置問題の克服: 単なる丸暗記ではなく、なぜそうなったのか、その意味を理解する力。歴史を例にとり、単なる暗記ではなく、時代変遷の意味を理解し、その理由を説明できる能力の重要性を強調します。
最後に、小学6年生を対象とした全国学力学習状況調査の算数の問題(リンゴの果汁20%の飲み物を2人で分けた場合の果汁の割合)を例に挙げます。この問題の正答率はわずか20%で、多くの児童が「半分にしたら果汁の割合も半分になる」と誤答してしまいます。これは、文章を機械的に読み飛ばし、**「イメージして共感しながら考える」**ことができていないためであると指摘します。「友達とジュースを半分こして薄くなったら嫌だよね」といった日常生活の感覚(共感)と結びつけて考えられるかどうかが、本来求められる学力であるとし、技術が進化する今だからこそ、このような人間らしい学びがより一層求められていると締めくくりました。
3.「人工知能(AI)とデジタルアーカイブの現状と未来」
澤井進(岐阜女子大学特任教授)
1.動画資料
2.資 料
3.内 容
1. はじめに:AIとデジタルアーカイブの共生
岐阜女子大学特任教授の澤井進氏は、AI時代の教育シリーズ最終回として、「AIとデジタルアーカイブの現状と未来」について講演しました。講演の冒頭で澤井氏は、自身のAI研究の初期から現在に至るまでの経緯、特に第5世代コンピューター開発機構やマルチメディア振興協会、デジタルアーカイブ推進協議会での活動に触れ、デジタルアーカイブという和製英語の誕生に自身が関わったエピソードを紹介しました。
本講演の趣旨は、AIとデジタルアーカイブの関係を「機関車と燃料車の関係」に例え、両者の不可分な一体化が未来のブレークスルー、すなわち「デジタル文化遺伝子」を形成するというものです。デジタルアーカイブは良質な燃料(データ)をAI機関車に供給し、AIはその燃料を効率的に活用することで、これまでの独立した発展から一体化へと移行し、未来を駆動すると説明されました。
2. AIとデジタルアーカイブの発展経緯
AIとデジタルアーカイブは、これまでそれぞれ独立した形で発展してきました。
2.1. AIの歴史と進化
AIの歴史は、チューリングの時代から現在まで続いています。初期の知識探索や推論、機械学習、特徴表現を経て、現在はディープラーニング、特に2017年に登場したトランスフォーマーがAI革命の中心となっています。チャットGPT、Gemini(旧Bard)、Bing AIなど、今日の主要な生成AIは、このトランスフォーマー技術を基盤としています。
機械学習の新しいプログラミング方法: 従来のプログラミングが「ルール+データ=答え」であるのに対し、機械学習は「答え+データ=ルール」という逆のアプローチを取ります。
生成AIの爆発的普及: 2022年11月にOpenAIが発表したチャットGPTは、わずか2ヶ月で1億ユーザーを獲得し、生成AIブームの火付け役となりました。これらは大規模言語モデル(LLM)を対話的に操作する仕組みを採用し、膨大な知識量を瞬時に提示する能力は人間を超えるとされています。
AIの限界と人間の役割: 生成AIは強力な道具ですが、あくまでツールであり、その出力結果は「データが悪いと間違った答えを出す」という限界があります。AIが提示する答えの「嘘を見抜く力」や、それを「対話を通じて思考を深めるための一方法として捉える」視点が人間に求められます。
トランスフォーマー革命: Googleが開発したトランスフォーマーは、その「注意機構(Attention)」メカニズムによって、英語からフランス語の翻訳タスクでプロの翻訳者をも上回る評価指数を達成し、AIの性能を飛躍的に向上させました。これは入力された情報をトークンベクトルに変換し、デコーダーが確率的に最も適切な出力を生成する仕組みに基づいています。
2.2. デジタルアーカイブの登場と理念
デジタルアーカイブは、インターネットの普及とほぼ同時期に登場しました。澤井氏によると、1993年に富士通の山本会長の依頼で、筑波大学の春月教授が**「デジタルアーカイブ」という和製英語を提唱**したのが始まりです。その目的は以下の5つでした。
消滅していく遺産や芸能の保存
非公開の資産の公開
人類共有の資産の保存
文化衝突の回避
デジタルアーカイブとは、「世界各地の遺跡や文化遺産、伝統芸能、芸術作品、産業遺産など、人類が創造し蓄積してきた資産をデジタル情報で記録し、分散データベースに保管し、通信ネットワークを通じて世界中の人々が自由に閲覧できるシステム」と定義されました。
2023年6月6日にはデジタルアーカイブ憲章が学会で策定され、デジタルアーカイブを「人々の様々な情報資産をデジタル媒体で保存し、共有し、活用する仕組みの総体」と定義し、社会の記憶する権利、オープンな参加、社会制度の整備、信頼性の確保、体験の確保などをその理想として掲げています。
3. AIとデジタルアーカイブが作る未来
澤井氏は、チャットGPTとGeminiにそれぞれ「デジタルアーカイブの現状と未来」「AIの現状と未来」「デジタルアーカイブを活用するAIとは何か」「AIが活用するデジタルアーカイブとは何か」を尋ねた結果を共有しました。両AIの回答は共通して、デジタルアーカイブは膨大なデータの保存とアクセスを可能にし、AIの進化がその検索や分析能力を高め、データ活用性を向上させると述べています。
3.1. デジタル文化遺伝子の提唱
澤井氏は、AIとデジタルアーカイブの一体化がもたらす未来像として、**「デジタル文化遺伝子(Digital Cultural Genes)」**という概念を提唱しました。
遺伝子: 生物が子孫に形質を伝える設計情報(DNAなど)を指す先天的要素。
文化的遺伝子(ミーム): リチャード・ドーキンスの「利己的な遺伝子」で提唱された、楽曲、思想、衣装、ツールの作り方など、人が後天的に文化を通して蓄積・継承する情報。
デジタル文化遺伝子: この文化的遺伝子のデジタル版であり、AIとデジタルアーカイブの統合によって、文化がデジタル技術を通じて無害かつ正確に広く保存され、伝播され、熟成され、新たな創造へと繋がるもの。
チャットGPTとGeminiにこの概念を教え込んだところ、両AIは「デジタルアーカイブを活用したAI技術は文化遺産の保存・共有・研究に新たな可能性を提供する」「人類の文化遺産を理解し未来へと継承していく上で重要な役割を果たす」と肯定的な回答を示し、その機能や強み、弱みを整理しました。
3.2. AIとデジタルアーカイブの一体化
AIが新しい産業革命の「機関車」ならば、デジタルアーカイブはそれを動かす「石炭」であると澤井氏は例えます。インターネットによる画像、動画、自然言語といったビッグデータが爆発的に増える中、AIの学習には、無害で正確な学習データ、すなわち精錬されたデジタルアーカイブが不可欠です。例えば、自動翻訳の精度向上のためには、人間がチェックし、翻訳例を蓄積したデジタルアーカイブが必須となります。
AIとデジタルアーカイブの一体化は、以下のような形で文化の創造に貢献すると考えられます。
古文書の解読・翻訳: 崩し文字の現代語翻訳(例: 徒然草、源氏物語の源氏絵巻詞書の崩し文字を現代語に翻訳)
白黒写真のカラー化: 古い写真や映像をカラー化し、当時の風景や人々の生活をより鮮明に再現(例: NHKによる古い映像の4K化)
AIによる芸術への応用: バッハ調の作曲、心の中でイメージした内容の画像化(fMRIと機械学習の組み合わせによる脳活動の可視化)
AI文化そのもののデジタルアーカイブ化: チューリングから始まるAIの歴史そのものをデジタルアーカイブ化し、文化的遺産として保存。
オーラルヒストリーの活用: 著名な研究者や有識者の講演記録などをデジタルアーカイブ化し、共有・活用(例: 長尾先生のAI哲学最前線)。
4. AI時代の倫理と教育のレール
AI技術は自動運転や画像診断など、私たちの暮らしに急速に浸透していますが、その価値の共有や倫理的な問題への対処が課題となっています。EUではAI倫理に基づく輸入規制を計画しており、日本も「AI倫理のレール作り」が求められています。
OpenAI自身も10年以内に超知性が誕生する可能性を示唆し、その制御のために、過去の弱いAIモデル(GPT-2など)で最新の強力なAIを制御することを検討していると述べています。澤井氏は、AIの賢さを下回る人間がAIをコントロールすることは困難であるとし、この課題を解決するためにも、デジタル文化遺伝子の概念が不可欠であると考えています。
知的創造サイクル(創造、保護、活用、そして再び創造)を効率化するためには、AIとデジタルアーカイブの一体化が重要です。これは、単にAIにデータを投入するだけでなく、教育における指導案や、増川教授が指摘した「人間の強みを生かす」「対話する」といった明確な教育方針という「レール」の上で生成AIを活用することで、初めて成果が上げられることを意味します。学習データは正確で偏見がなく、安全なものでなければなりません。
澤井氏は、アメリカのデトロイト市で進行中の自動運転プロジェクト「Cavnue」の例を挙げ、電磁誘導線が埋め込まれた専用レーンを全自動運転車が運行し、まるで列車に乗っているかのような体験を提供していることを紹介しました。これは、AIを活用したシステムを社会に実装する上で、「レール」となるインフラやルール作りがいかに重要であるかを示しています。
5. 結論:人類の結晶たるデジタル文化遺伝子
澤井氏は、AIとデジタルアーカイブの一体化によって生まれる「デジタル文化遺伝子」こそが、人類の結晶であると締めくくります。人類はこれまで、DNAという遺伝子や、図書や本といったミームを通じて知識や文化を継承してきました。今後は、デジタル技術によって無害で正確に、そして広く保存・発信され、熟成されたデジタル文化遺伝子が、AIと連携しながら新たな創造へとつながっていく未来を描いています。
講演の最後に、澤井氏はGoogleが提供するAI作曲ツールを実演し、簡単なメロディーを入力するだけで、バッハ調のハーモニーが自動生成される様子を示しました。これは、AIが人間の創造性を拡張し、新たな文化を生み出す可能性を具現化した一例です。